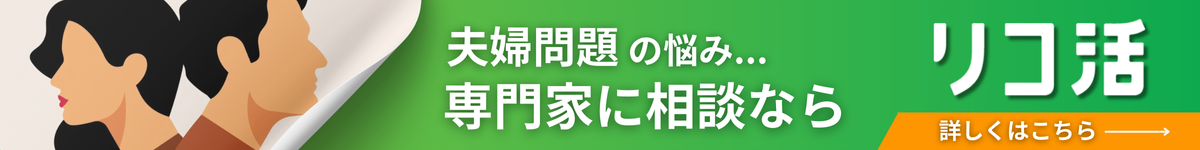パートナーの実家依存は、日々の些細なやり取りや生活環境から生じるストレスの原因となりがちです。本記事では、実家依存になる背景やその影響、具体的な対処法について、体験談を交えながら詳しく解説します。
森澤 雅代
修復・離婚・妊活・不妊・浮気・不倫など、夫婦全般のお悩みはもちろん、再婚のお悩みにも寄り添う夫婦カウンセラー。
詳しく見る
NPO法人日本家族問題相談連盟認定上級 プロ夫婦問題・離婚カウンセラーの資格取得後、販売サービスにて、夫婦・恋愛・人間関係に関する電話・メール・チャット・対面のカウンセリングの経験をもつ。

【体験談】パートナーの実家依存が気持ち悪い……
まずは、実際の事例を通して、実家依存がどのような形で現れるのかを見ていきましょう。夫婦のどちらか一方が実家へ頻繁に帰り過ぎることで、相手に不信感やストレスを与えるケースは少なくありません。
産休期間を実家で長期的に過ごす、週に何度も実家に泊まるなどの行動は、パートナーからすれば「気持ち悪い」と感じる原因にもなり得ます。さらに、夫側だけが義実家と交流を深めすぎたり、妻ばかりが実の両親に頼りすぎたりするなど、行き過ぎた依存が夫婦関係をぎくしゃくさせます。
経済面での依存

主人は35歳なのに、毎月実家からお金をもらっています。自分で稼いでいるのに、給料は全て趣味に使い、生活費は実家頼み。「お金をもらうことが親孝行だから」と言いますが、夫婦の自立を考えると気持ち悪いです。
(30代女性)
意思決定での依存



妻が何かを決める時、必ず義母に電話で相談します。家具の買い替えも、子どもの習い事も、全て義母の意見が最優先。僕の意見は後回しで、夫婦関係が崩壊しそうで気持ち悪いです。
(40代男性)
日常生活での依存



旦那は実家から離れて暮らしているのに、毎週帰省して母親に晩御飯を作ってもらいます。私のいないところで「母親の味が一番」と言っているそうで、気持ち悪くて仕方ありません。
(20代女性)
精神面での依存



妻は些細なことで実家に頻繁に相談します。子育ての悩みも、仕事の愚痴も、全て義両親に話がいく。僕たち夫婦で解決する機会がなく、正直気持ち悪い距離感です。
(30代男性)
子育てでの依存



妻は育児の判断を全て義母に委ねます。子どもの体調が悪くても、まず義母に電話。私よりも義母の意見を重視するのが本当に気持ち悪いです。このままでは離婚も考えてしまいます。
(30代男性)
実家依存症のパートナーのチェックリスト
実家依存症のパートナーによくみられる特徴をチェックリストにまとめました。以下の項目に当てはまるものがあれば、パートナーは実家依存症かもしれません。パートナーが実家に行ったり親が自宅に訪ねてきたりする頻度が高いほど、実家依存症の傾向が高いと考えられます。





チェック事項に一つでも当てはまることがあれば、要注意です。
親と仲が良く、自立していない妻は、何かあると実家に逃避してしまい、夫に愛想をつかれ、離婚の誘因となることもあります。
妻は実家依存症の自覚がないため、話し合うことは簡単ではありません。
妻だけではなく、親からも夫の方がおかしいと非難されてしまうこともあるのです。
実家と物理的な距離はもちろんのこと、心の距離も置き、夫と二人で家庭を築く覚悟が必要ですが、夫も妻を大事にし、結婚生活のどのような困難も二人で乗り越えることが大切です。


なぜパートナーが実家依存になっているのか
次に、なぜ実家依存が起こるのか、その背景にある家族関係や経済的・心理的要因を探ります。


家族関係が濃密
親と子の結びつきが強すぎると、子どもは精神的にも生活面でも自立しにくくなります。特に、親が子どもを手元に置いておきたいという思いが強い場合、結婚しても帰省頻度が増えやすくなるでしょう。
こうした濃密な家族関係が続くと、パートナーに対して「自分たちの家庭を優先してほしい」という要望が通りにくくなります。結果として、夫婦間の距離が広がり、コミュニケーション不足やトラブルの原因となるのです。
経済的な要因
不安定な収入やローンの返済が重くのしかかるなかで、親からの金銭的援助に頼ってしまい、そのまま実家依存が深まるパターンは珍しくありません。夫婦ともに働いていても、家計が苦しいときには親へ支援を求めたくなるものです。
一方で、親の援助を受け取ることが当たり前になってしまうと、計画的な家計管理や貯蓄の重要性を学ぶ機会を逃す可能性があります。自分たちの力で生活基盤を築いていくことは、夫婦にとって大切な成長のプロセスです。
自立を妨げる心理的な要因
自己肯定感が低かったり、幼少期に危機的な出来事を親に助けてもらった経験を繰り返していたりすると、成人後も親を頼り続ける構図ができあがりやすくなります。子どもとしては、それが安心材料であり、不安を解消する手段になっているのです。
本来は夫婦同士で気持ちや考えを共有することで問題解決力を育んでいくべきですが、心理的依存が根強いと、いつまでも親を介した解決法を選んでしまいます。これが長期化すると、親離れだけでなく夫婦の自立も大きく阻害されていくのです。
文化的・社会的な背景
三世代同居や近居が当たり前とされる地域では、実家の手厚いサポートを受けることが自然な生活スタイルだと考えられています。そのため、結婚しても親との距離感が変わりにくく、結果的に夫婦としての自立が遅れがちになります。
近年では都心部を中心に核家族化が進んでいますが、地方や家庭によっては依然として親子の結束が強い文化が残っています。こうした文化的背景があると、夫婦のどちらかが当たり前のように実家を頼るケースが発生しやすくなります。
義実家との関係で起きやすい問題
パートナーが実家に依存すると、自然と義実家との距離が近くなり、様々なトラブルが発生しやすくなります。
配偶者の意見よりも義実家の意見を優先するようになったり、親世代の価値観に合わせようとしたりするうちに、夫婦は対等に話し合う機会を失っていきます。こうした状況が続けば、家庭内の意思決定が義実家主導になってしまい、夫婦の不満や摩擦が絶えなくなります。


子育てや育児方針の衝突
育児は夫婦で協力して進めたいものですが、義母の干渉が強い場合には夫婦の育児方針がスムーズに進まないことがあります。例えば、食事の与え方やしつけ方法など、親世代と現代育児の感覚が噛み合わず、対立することも多いようです。
こうした衝突が続くと、それぞれの子どもへの対応が異なることから、子どもにも混乱が生じます。
家事分担への義母の過剰な介入
夫婦で決めた家事分担に対して、義母が口を出しすぎる例も散見されます。特に、料理の量や掃除の頻度などに対して「もっとこうしたほうがいい」というアドバイスが連発されると、しだいに息苦しさを感じるでしょう。
家事はそれぞれの家庭によってやり方やペースが異なるため、義母の常識に合わせるのが必ずしも正解とは限りません。夫婦のペースを大事にしながら、必要以上の干渉を防ぐコミュニケーション方法を探ることが重要です。
経済的に頼らざるを得ないことによる軋轢
家計管理を親に頼るあまり、ローンの返済や日常の生活費を義実家が肩代わりしているケースは、後になって大きなトラブルに発展するリスクがあります。何らかの理由で親との関係が悪化した場合、それに伴って経済的な支援が突然断たれることも考えられます。
配偶者からすると、「自分たちで管理できるはずの家計をなぜ義実家に依存するのか」と疑問を抱くのは自然なことです。お金の問題は感情的になりやすいため、普段から夫婦でしっかり話し合っておく必要があります。
同居・近居による居心地の悪さ
実家依存が進むと、親子の距離を物理的に近づけようとする動きも出てきます。同居の誘いがあったり、近距離に引っ越したりすると、親が日常的に干渉しやすくなり、夫婦のプライバシーが失われがちです。
特に夫婦関係がまだ安定しないうちに同居を始めると、親側が常に介入し、夫婦間のコミュニケーション不足を招いてしまいます。長期的な視点で「本当に同居がベストな選択なのか」を冷静に見極めることが重要です。
パートナーの実家依存が夫婦関係に与える影響
一方が実家を優先しすぎると、他方は疎外感や不満を強く抱き、日常的な会話やスキンシップまでぎこちなくなることがあります。また、実家を頼る頻度が高い人ほど、配偶者への思いやりや責任感が低下していると捉えられやすいため、相互の信頼関係に亀裂が入る原因となりがちです。


夫婦喧嘩の増加と原因
親を巻き込んだ議論が当たり前になると、夫婦単独での問題解決が困難になります。どちらかがすぐに実家へ相談してしまうため、「自分の意見が尊重されない」と感じる場面が増加し、喧嘩も絶えません。
互いへの不信感が強まってくると、些細なきっかけでも感情的にぶつかり合うことが増えるでしょう。放っておくと深刻な溝になり、離婚に発展するケースも考えられます。
子どもへの心理的な影響
親同士の不和は子どもにも自然と伝わり、情緒の安定を保つのが難しくなることがあります。親が実家に依存している様子を見た子どもは、どちらを頼るべきかわからず混乱しやすいでしょう。
また、家族間のコミュニケーションが不足すると、子どもが自己表現をしにくい環境が生まれます。長期的に見れば、人間関係の築き方や自立心の形成にも大きな影響を与えかねません。
仕事と家庭のバランスが崩れる
お金の面で実家の助けを受けている場合には、「自分で稼がなくても困らない」といった安易な考えを持ってしまい、キャリア形成を疎かにするおそれがあります。
また、夫婦関係がぎくしゃくすると、家に帰っても気が休まらないため、疲労感が増し、生産性が下がってしまうこともあるでしょう。
パートナーに期待できない
パートナーの実家への共依存を許容し続けると、夫婦間でお互いの足りない部分を実家が補う構図が出来上がり、夫婦の自立心が育たなくなることがあります。
このような夫婦は、問題が生じてもお互いを支え合うどころか、さらに外部(実家)を頼るという流れが固定化しやすくなります。これにより、いつまでたっても夫婦としての成長が期待できなくなるでしょう。
実家に依存するパートナーが気持ち悪いと感じる時の対処法
実家依存が深まっていくと、放置していても状況がよくなることはほとんどないようです。離婚という手段に踏み切る前に、第三者の意見を取り入れたり物理的な距離をとったりするなど、具体的かつ柔軟な方法を検討してみることが得策です。


ママ友や友人の意見を聞く
身近な人に相談してみると、同じような悩みを経験した人の具体的なアドバイスを得られることがあります。自分だけで抱え込んでいると視野が狭くなりがちですが、第三者の客観的な意見で冷静になれるかもしれません。
また、友人やママ友の視点を取り入れることで、自分自身の固定観念に気づけるケースもあります。ときには「実家依存はよくあること」「自分のケースは実家依存ではない」と知り、安心感を得ることもあるでしょう。
距離感を適切に保つよう伝える
夫婦生活において、実家と密接に関わりすぎることが必ずしも悪いわけではありません。親孝行であればよいのですが、「共依存」と呼べるほど近い関係であれば、夫婦の時間やプライバシーを確保できるよう配慮が必要です。
そこで大切なのは「適度な距離感」を設計することです。頻度やタイミング、相談内容などを夫婦で振り返り、義実家との関係性を見直すようパートナーに伝えることが大事です。
家族と義実家の優先順位の決め方を整理する
結婚後は、自分たちが築いた家庭を最優先する必要があります。これは決して親をないがしろにするという意味ではなく、あくまで夫婦の生活基盤をしっかり固めるためのステップだと考えましょう。
夫婦で話し合い、「どんなときに義実家を頼り、どんなときには夫婦で解決するか」など具体的な基準を設けてみるとスムーズです。そうすることで、実家依存に陥るリスクが格段に下がります。
義実家と物理的に距離を置く
どうしても干渉が強く、精神的に落ち着かない場合には、引っ越しや同居解消などで物理的な距離を確保することも一つの方法です。近居や同居では気を抜いた瞬間に日常の様々なシーンで干渉が入りやすく、ストレスは高まります。
引っ越しは大きな決断かもしれませんが、その後の夫婦関係を考えれば、検討してもよいかもしれません。
夫婦カウンセラーに相談する
長期的に実家依存が続き、簡単に解決しないときには、夫婦カウンセラーなどの専門家に意見を求めることが重要です。専門知識を持った第三者であれば、感情を整理しながら建設的に問題を解決へ導く手法を提案してくれます。
相談の内容は人それぞれですが、実家依存に付随する義父母との関係や家計管理の課題など、多面的にサポートしてもらえる可能性が高いです。


離婚を検討する
どれだけ時間をかけても実家依存の問題が改善されず、生活に支障が出続ける場合は、最終的な手段として離婚を考える選択肢も存在します。離婚は人生の大きな節目となるため、周囲への相談や法律専門家のサポートを得ながら慎重に進めることが大切です。
結果的に夫婦関係を修復できないとしても、「人生において何を優先させるのか」という価値観が明確になり、お互いにとってよい未来を築ける可能性もあるでしょう。


実家依存のパートナーが気持ち悪いと感じたらよく話し合おう
実家依存は一気に解決する問題ではありません。夫婦が理解し合い、互いの考えや気持ちを丁寧に伝え合うことで、少しずつ状況を改善していくことが大切です。
実家依存と感じるほどの行動は、当人にとっては当たり前の習慣かもしれません。しかし、配偶者が「気持ち悪い」と感じるほどの依存度は、夫婦の絆を弱める要因であることは間違いありません。すぐに完璧な解決を目指すのではなく、まずは対話を通じてお互いが納得できる方向性を少しずつ探っていきましょう。
夫婦間のコミュニケーションを増やし、第三者の視点も取り入れながら現状を客観視することで、過度な実家依存を和らげるきっかけになるはずです。時間はかかるかもしれませんが、自分たちの家族にとって最適な形を模索する努力が、じわじわと効果を発揮していくでしょう。