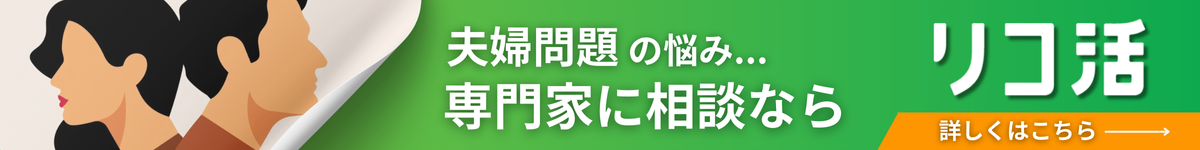「家庭内別居のルールがわからない」



「ストレスを感じずに進める方法はあるの?」
そう思う方もいるでしょう。
家庭内別居を円満に進めるには、具体的なルール作りと実践が大切です。本記事では、家庭内別居のやり方と円満に進めるための5つのポイントを解説します。


高草木 陽光
これまで9,000人以上のカウンセリングを行い、夫婦問題・家族問題で悩む人を解決に導くお手伝いをする夫婦カウンセラー。
詳しく見る
美容師、育毛カウンセラーを経て、結婚して専業主婦となるが、夫の束縛や価値観の押し付けに違和感を覚え「結婚生活とは何か」ということを深く考え始める。書籍に「なぜ夫は何もしないのか なぜ妻は理由もなく怒るのか」(左右社)、「心が折れそうな夫のためのモラハラ妻解決BOOK」(左右社)、メディア実績にNHK総合「あさイチ」、フジテレビ「ホンマでっか!?TV」、テレビ朝日「羽鳥慎一 モーニュングショー」、「ABEMA Prime」などがある。


家庭内別居とは?


夫婦関係が冷え切り、同じ家に住んでいてもお互いを他人のように感じることはありませんか。
家庭内別居には夫婦それぞれの事情があり、一概に悪い状況とは言えない場合もあります。ここでは、家庭内別居の意味や、そのような状況に至る主な理由について詳しく解説していきます。
家庭内別居の定義
家庭内別居とは、同じ家に住みながらも、夫婦がお互いに距離を置き、別々に生活する状態のことです。
たとえば、寝室を分けたり、会話をほとんど交わさなかったり、食事の時間を別々にしたりすることが一般的です。一つ屋根の下に暮らしているにもかかわらず、まるで他人のような関係に感じます。
このような状態になる理由はさまざまですが、多くの場合、夫婦関係の冷え込みが原因です。それでも、すぐに離婚を選択せず、家庭内別居を続ける夫婦も少なくありません。
家庭内別居を選ぶ主な理由
家庭内別居を選ぶ理由は、夫婦によってさまざまですが、大きく分けると2つに分けられます。
- 離婚に踏み切れない心理的・経済的な要因
- 子どもや家族への影響を最小限にするため
離婚に踏み切れない心理的・経済的な要因
離婚に踏み切れない理由の一つは、心の準備ができていないことが考えらえれます。長い間一緒に生活してきた相手と完全に別れることは、簡単ではありません。親戚や友人への説明が面倒に感じたり、周囲からの視線を気にすることもあるでしょう。
経済的な問題も大きな壁となります。新しい住まいを用意したり、離婚に必要な手続きにお金がかかったりするため、すぐに行動できない場合も多いです。
共働きであっても、離婚後の生活費や子どもの養育費を考えると、現状を維持する方が安心だと感じます。
子どもや家族への影響を最小限にするため
離婚をすると、子どもの学校や住む場所が変わることがあります。親が離婚したことを友達に知られるのを嫌がる子どももいるでしょう。こうした環境の変化が、子どもの心に負担をかけるのではないかと心配する親は少なくありません。
家庭内別居を選べば、家族としての形を維持しながら、子どもの生活リズムや精神的な安定を守れます。たとえば、夫婦が同じ家に住むことで、子どもに安心感を与えられます。
さらに、高齢の親や親戚への配慮も、家庭内別居を選ぶ理由の一つです。離婚は家族全体に影響を与えるため、周囲に心配をかけたくないと考える人も多いです。この方法なら、親族間の調和を保ちながら、夫婦それぞれが距離を取ることができます。
家庭内別居のルールを作る前に確認すべきこと


家庭内別居をスムーズに進めるためには、事前にお互いの意図や具体的なルールを明確にすることがポイントです。ただ単に距離を取るだけでは、新たなトラブルが生まれるかもしれません。
家庭内別居を始める前の3つのポイントは以下のとおりです。
- お互いの意図を明確にする
- 家庭内別居の範囲を具体的に決める
- 家族や子どもへの説明の仕方
お互いの意図を明確にする
家庭内別居を始めるとき、家庭内別居を選ぶ理由を明確にしましょう。それぞれが持つ目的や考えを話し合い、共有することが大切です。
たとえば、「しばらく距離を取って関係を見直したい」という場合もあれば、「もう関係を修復するつもりはないが、経済的な理由で離婚は避けたい」という場合もあるでしょう。
この段階でお互いの気持ちが食い違っていると、後々さらに大きな問題に発展しまうかもしれません。
家庭内別居を選んだ目的とは?
家庭内別居を選ぶ理由は、夫婦によって異なります。そのため、相手がどのような気持ちでこの方法を選んだのかをしっかり理解しましょう。
具体的には、「この状態をどのくらい続けるつもりなのか」「最終的にどうしたいのか」を話し合うことで、今後の生活をスムーズに進められる基盤が整います。
家庭内別居の範囲を具体的に決める
家庭内別居を成功させるためには、ルールや役割分担を具体的に決める必要があります。
共有スペースの使い方や子どもへの配慮も事前に話し合い、具体的なルールを設けることでトラブルを防げます。また、家庭内別居を進める中で状況が変わることもあるため、ルールを定期的に見直しましょう。
お互いに曖昧な状態で進めると、生活の中で摩擦が生まれやすくなります。
生活空間や役割分担をどうするか
具体的には、寝室やリビング、キッチンといった生活空間をどう分けるのかを話し合います。また、食事や洗濯などの家事をそれぞれがどのように分担するのかも重要なポイントです。
「食事は完全に別々」「洗濯は共用の時間を決める」といったルールをあらかじめ決めておけば、衝突を防げるでしょう。
家族や子どもへの説明の仕方
家庭内別居を始めるときには、家族や特に子どもに対してどのように説明するかを考えておきましょう。子どもがいる場合、親の不仲に気づいて不安を感じることがあります。そのため、適切なタイミングで状況を説明しなければなりません。
家庭内別居を始めても、家族としての関係は変わらないことを伝えると、子どもが混乱せず安心できるはずです。また、両親が話し合いをしている姿を見せることで、自分たちを大切に考えていると感じられるでしょう。
家庭内別居を円満に進めるための5つのポイント


家庭内別居を成功させるには、明確なルールを作り、お互いが守ることが不可欠です。ルールが曖昧だと、誤解やトラブルが増える原因になります。
家庭内別居をスムーズに進めるための具体的な5つのポイントは以下のとおりです。
- 生活空間を分ける
- お金の管理ルールを設定する
- コミュニケーションの頻度を決める
- 子どもの生活を優先する
- 定期的なルールの見直し
1.生活空間を分ける
家庭内別居の基本は、生活空間をきちんと分けることです。お互いのプライバシーを守り、ストレスを軽減するためには必要なポイントです。
部屋の配置や共有スペースのルール
まず、それぞれが使う部屋を決めましょう。たとえば、寝室は別々にするのが一般的ですが、リビングやキッチンなどの共有スペースをどう利用するかも話し合いましょう。
「リビングは交代で使う」「キッチンは使用時間を決める」など、具体的なルールを作るとトラブルを防ぎやすくなります。
2.お金の管理ルールを設定する
家庭内別居中でも、家計の管理は避けてとおれません。お金に関する取り決めをしておかないと、後々不満が溜まりやすくなります。
収入や家計分担の取り決め方
家賃や光熱費、食費などの費用をどのように分担するかを事前に決めておきます。「家賃と光熱費は折半する」「それぞれが自分の食費を負担する」といった具体的なルールを話し合いましょう。
また、収入の差が大きい場合は、無理のない範囲で分担方法を調整する必要もあります。
3.コミュニケーションの頻度を決める
家庭内別居中でも、最低限のコミュニケーションは欠かせません。必要な連絡事項をスムーズに伝えるための仕組みを作りましょう。
必要最低限の連絡事項やタイミング
たとえば、子どもの学校行事や緊急の連絡事項について、どのように情報共有するかを決めます。口頭で伝えるのが難しい場合は、メールやメモを活用するのも一つの方法です。
また、週に一度など、定期的に話し合いの時間を設けると、誤解やトラブルを防ぎやすくなるでしょう。
4.子どもの生活を優先する
子どもがいる場合、家庭内別居中でもその生活リズムや心の安定を最優先に考える必要があります。
教育や日常の安定を保つための方法
夫婦間の問題が子どもに悪影響を及ぼさないようにするためには、教育や生活のサポートを引き続き行うことが大切です。
たとえば、「子どもの送迎はどちらが担当するか」「進学や習い事の決定はどうするか」などを具体的に決めておくと、スムーズに進められます。また、親としての役割を果たし続けることで、子どもが安心して過ごせる環境を作ることができるでしょう。
5.定期的なルールの見直し
家庭内別居を始めてからも、状況に応じてルールを見直しましょう。最初に決めたルールが、時間とともに合わなくなることもあります。
問題が生じた場合の修正方法
ルールを見直すときは、必ず話し合いを行い、双方が納得できる形で変更しましょう。たとえば、「共有スペースの使い方を変える」「子ども関連の役割分担を見直す」といった調整を行います。
お互いが歩み寄る姿勢を持つことで、家庭内別居を長期的に維持しやすくなります。



家庭内別居をしている人は、時間をかけて「結果的にそうなってしまった」という人が多い印象です。夫婦の事情に関係なく、険悪な雰囲気は子どもへも伝わります。
「夫婦」としては難しくても「子どもの父親と母親」という立ち位置で協力し合うことが大事です。夫婦間の感情は抜きにして子どものためにも家族旅行等のイベントは継続してください。家庭内別居とはいえ、お互い「共同生活の一員としての礼儀」をわきまえて生活することは必要です。
家庭内別居でよくあるトラブルとその対処法


家庭内別居は、夫婦間の距離を保ちながら生活を続ける方法として有効ですが、必ずしもすべてがうまくいくわけではありません。ルールを作っても、日々の生活の中で摩擦やトラブルが生じることがあります。
家庭内別居でよくある3つのトラブルをまとめると以下のとおりです。
- 経済面でのトラブル
- 家事分担を巡るトラブル
- 感情的な衝突やストレス
経済面でのトラブル
お金に関する問題は、家庭内別居で最も起こりやすいトラブルの一つです。生活費の分担が不公平に感じられたり、相手が支出のルールを守らなかったりすると、不満が積み重なっていくことがあります。
お金の使い方や負担割合を巡る衝突
家計の管理については、最初に細かく取り決めをしておきましょう。たとえば、家賃や光熱費はどう分担するのか、食費は共有にするのかなど、具体的なルールを明確に決めておくことでトラブルを防ぎやすくなります。
問題が発生した場合は、家計簿アプリなどを活用して支出を見える化する方法も効果的です。お互いに状況を確認しながら冷静に話し合い、必要であれば分担ルールを見直すことで、衝突を防げるでしょう。
家事分担を巡るトラブル
家事に関する不満も、家庭内別居中に起こりやすいでしょう。一方が家事を多く負担していると感じたり、決めた役割が守られなかったりすることで、不満が大きくなることがあります。
不公平感を解消する方法
家事については、どの作業をどちらが担当するのかを最初に具体的に決めておきましょう。たとえば、掃除は交代制にする、洗濯はそれぞれが自分の分を行う、といった役割分担を明確にしておけば、トラブルの発生を抑えられます。
ただし、家庭内別居が続く中でルールが現実と合わなくなる場合もあります。その場合は、現状に合わせた役割分担の見直しが必要です。定期的に話し合いの時間を設け、お互いが納得できる形で調整していきましょう。
感情的な衝突やストレス
同じ家の中で生活を続けていると、感情的な衝突やストレスが発生することもあります。相手の言動にイライラしたり、生活スタイルの違いに不満を感じたりすることが原因です。
お互いの感情をコントロールするための工夫
感情的なトラブルを防ぐには、相手に過度な期待をしないことが重要です。相手を変えようとするのではなく、自分自身の感情を整理することに意識しましょう。日記をつけて気持ちを客観的に見つめたり、信頼できる友人やカウンセラーに相談することで、ストレスを軽減できます。
また、問題が発生する前に話し合いの機会を設けることも効果的です。月に一度など定期的にコミュニケーションの時間を確保し、冷静に意見を交換することで、誤解や摩擦を最小限に抑えられるでしょう。
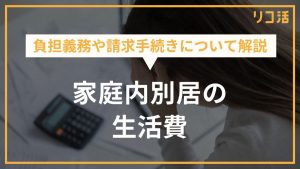
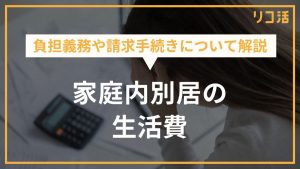
家庭内別居を円満に進めるために大切なこと


いかがでしょうか。
本記事のポイントをまとめると以下のとおりです。
- 家庭内別居の基本を理解する
- 家庭内別居のルールを作る前に準備を整える
- コミュニケーションの頻度を決める
- 円満に進めるためにルールを作る
- トラブルとその対処法を知っておく
夫婦関係を修復するのは簡単なことではありませんが、家庭内別居を通じて、新しい家族の形を見つけることができるかもしれません。
本記事の内容を参考に、より良い未来に向けた一歩を踏み出してみてください。