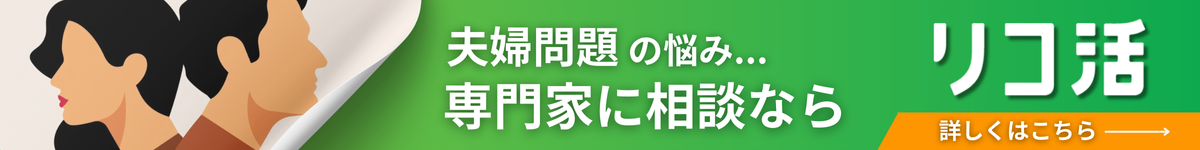モラハラと共依存の関係は、多くの夫婦が気づかないうちに陥る危険な状態です。相手への過度な依存や、自分よりも相手の感情を優先する習慣は、やがて夫婦関係の崩壊へとつながります。本記事では、モラハラ共依存の特徴、なぜ抜け出せないのか、そして脱出する具体的な方法までを、チェックリスト付きで詳しく解説します。自分らしい人生を取り戻すための第一歩を踏み出しましょう。
渡辺 里佳
30代半ばで離婚を経験し、子どもたちが成人する頃に「夫婦関係や離婚に悩む人の助けになりたい」「人の役に立ちたい」という想いが膨らみ、2011年、夫婦問題研究家・岡野あつこ主宰の「離婚カウンセラー養成スクール」に通学。
詳しく見る
夫婦問題に特化したカウンセリングを学び、同年9月「離婚カウンセラー」資格を取得、52歳でカウンセラーに。
心理を深く学ぶため、日本プロカウンセリング協会認定「心理カウンセラー2級」資格を取得。現在、法務省認証の民間調停機関「家族のためのADRセンター」主催の「パパとママの離婚講座」の講師を担当。ライター、エディターとしても活動している。

共依存とは?
共依存とは、相手に過度に依存し、自分の感情や欲求よりも相手の感情や欲求を優先してしまう状態です。夫婦間の共依存とは、一般的に夫婦の一方が相手に精神的に依存し、依存されている側も、相手の依存を助長する存在になっている関係を言います。夫と妻両方の性格や思考パターン、言動が複雑に絡み合って起こります。双方、またはどちらか一方が「自分は相手にとって不可欠な存在である」と思っており、相手から自立できずにいる状態です。
共依存が進行すると、夫婦関係の崩壊や、モラハラ・DVなどに発展することがあります。
夫婦間の共依存チェックリスト
夫婦が共依存の関係にあるかどうかの目安となるチェックリストを紹介しますので、一度チェックしてみてください。当てはまる項目が多いほど、共依存に陥りやすい傾向があるかもしれません。
夫婦間の共依存チェックリスト

※このチェックリストは自己確認のためのものです。当てはまる項目が多い場合は、専門家(カウンセラーや相談窓口)に相談することをおすすめします。

モラハラの加害者・被害者夫婦が共依存してしまう理由は?
モラハラ(モラルハラスメント)は言葉や態度で相手を傷つけるハラスメントの一つです。夫婦間でも起こる精神DVですが、加害者・被害者ともに相手から離れられず共依存しているケースが多くみられます。モラハラで苦痛を感じているのに共依存してしまう理由について解説します。

幼少期の家庭環境
共依存の関係に陥っている人の多くは、虐待やDVなど問題のある家庭で育ったという報告もあるようです。こうした人は、夫・妻の愛情を確かめるため、必要以上に相手に執着する傾向があり、共依存に陥りやすくなります。
また、成人してからも、幼少期を過ごした家庭環境の悪影響を受けている人をアダルトチルドレンと呼びます。アダルトチルドレンに該当する人は、人格形成に重要な時期に愛情を受けた経験が少ないのが特徴です。このため、対人関係や自己認識に問題をかかえていることが多く、夫・妻に対してDVやモラハラをしてしまうことがあります。
自己肯定感の不足
自己肯定感は成長過程における環境や体験を元に形成され、自分の存在をポジティブにとらえる感覚です。幼少期に虐待を受けていたり、思春期に学校でいじめに遭ったりすると、十分な自己肯定感が育たないまま大人になることがあります。
自己肯定感が低い人は、自分に自信がなく相手に嫌われることを恐れるため、モラハラ被害を受けても離れようとしません。さらに夫・妻のモラハラを助長させることが多く、共依存になりやすいと考えられます。
境界線の曖昧さ
境界線(バウンダリー)とは、自分と他者を区別する心理的な境目のことです。健全な境界線があれば、「自分の感情と相手の感情は別物」「自分の責任と相手の責任は区別できる」という認識ができます。しかし、モラハラと共依存の関係では、この境界線がとても曖昧になっています。
モラハラ被害者側の境界線の曖昧さとして、相手の機嫌が悪いと自分も不安になり、相手が怒ると自分が悪いと感じるなど、パートナーの感情状態が自分の感情を直接左右することがあります。「彼(彼女)が怒っているのは私のせいだ」と自動的に考えてしまうのです。
一方、モラハラ加害者は相手の境界線を尊重せず、言動や交友関係、考え方にまで介入し、コントロールしようとします。自分の否定的な感情や特性を相手に投影し、「お前がイライラさせる」「お前のせいで怒るんだ」と責任転嫁します。自分と相手の区別があいまいで、自分の問題を相手の問題として扱います。
経済的なパワーバランス
夫婦のどちらか一方が家計を支えている場合、収入が多い方へパワーバランスが偏り、共依存の関係が生じるきっかけになることがあります。特に専業主婦(夫)の場合、パートナーから関係を断たれると経済的に困窮するため、必要以上にパートナーに尽くしてしまいがちです。
また、経済的な優位性を理由に、パートナーを精神的にも支配しようとモラハラをする夫・妻も存在します。収入が低い側からすると、生活がかかっているため、モラハラを受けてもなかなか別れを切り出すことができません。
パートナーの精神疾患
家庭内にうつ病などの精神疾患で心理的に不安定な人がいる場合、その夫・妻とともに共依存に陥るケースがあります。パートナーの病状を理解し、献身的に尽くしているうちに「自分がいなければこの人は生きていけない」と錯覚しやすくなるためです。
精神疾患を抱えている側も、パートナーに頼りがちになり、自分の力で状況を変える気力を失いがちです。同様の現象は、うつ病だけでなく、アルコールやギャンブルなどの依存症でもよく見られます。
人間関係が希薄
夫・妻ともに交友関係が狭く、周囲に援助が見込める家族がいない場合も、共依存が起こりやすい状況です。問題が起こったときに、助けを求められるのはパートナーのみなので、常に夫・妻を失いたくないという不安を抱えていなければなりません。
DVやモラハラなどが起こっても、客観的な助言を得られないため、共依存の夫婦関係になっていることに気付かず孤立してしまいます。
モラハラ共依存夫婦の末路は?
一見、問題がないように見える共依存は、気付かないうちに夫・妻双方に心理的な負担をかけていることがあります。モラハラや夫婦関係の悪化など、共依存の先に待ち受けている末路について説明します。

共依存を深める
客観的に見て不自然な共依存の関係でも、お互いが納得していれば、問題ないようにみえます。しかし、共依存であることに気付かないまま生活を続けていると、次第に共依存の関係がエスカレートしがちです。
ついには互いが「パートナーしか頼る人がいない」と考えるようになり、社会的に孤立してしまいます。そして、一方がモラハラやDVをエスカレートしても、周囲は全く気付かないという危険な状況になる恐れがあります。
子どもへの悪影響
モラハラ加害者は、子どもを支配の道具として利用したり、子どもの前で被害者を貶めたりすることがあります。また、被害者も精神的余裕がなくなり、子どもに適切な関わりができなくなることがあります。
また、モラハラと共依存の関係を目の当たりにして育った子どもは、それを「正常な関係」のモデルとして内在化してしまうことがあります。その結果、将来自分自身が同様の関係に陥りやすくなります。
関係性が崩壊する
精神的な共依存関係では、夫か妻のどちらか一方が、相手に嫌われることを極端に恐れているケースがあります。この場合、パートナーからモラハラなどで理不尽な要求をされても、拒否できずに自分が無理をしてでも応えようとします。
しかし、共依存の関係が深まるにつれ、パートナーからの要求もエスカレートし、精神的・身体的な負担も増大していきます。長年我慢してきた被害者が、ある出来事をきっかけに「もう限界だ」と感じ、最終的には、夫婦関係でいることに耐えられなくなり、離婚や別居という結果になることもあります。
モラハラ夫・妻との共依存を脱出する方法
共依存は夫と妻双方の性格や思考パターンなどが複雑に絡み合って起こるため、関係から脱却するのは簡単ではありません。しかし、一歩一歩段階を踏めば、共依存の関係を改善し、お互いによりよい結果が得られる可能性があります。モラハラ夫・妻との共依存から抜け出したい人のために有効と思われる方法を紹介します。

共依存していることを自覚する
共依存夫婦はパートナーへの執着が強く、視野が狭くなっていることが多いため、自分たちが共依存であると自覚するのが困難です。また、支配欲の強い夫・妻にマインドコントロールされた状態だと、自分がモラハラを受けていても、それを当然のように錯覚してしまいます。
しかし、日常において夫・妻の存在が抑圧的に感じるなどの小さな違和感が、モラハラや共依存に気付くきっかけになることがあります。現在の夫婦のあり方に問題がないか、冷静に見直してみると、気づかなかった共依存の関係を発見できるかもしれません。
周囲の人に相談する
「自分たち夫婦は共依存ではないか」と感じたら、すぐに友人や知人など身近な人に相談しましょう。家族以外の人の意見を聞くことで、視野が広がり、モラハラや共依存の問題を自覚できるかもしれません。
また、友人・知人とリラックスして接する中で、夫・妻と一緒にいるときの自分は、相手が望む姿を演じていたことに気付くかもしれません。相手を優先し、自分は我慢する癖は、モラハラ被害を受けたり共依存関係に陥ったりしている夫・妻によくみられる特徴です。
夫婦カウンセリングを受ける
夫婦関係が共依存に陥っている場合は、専門家のサポートを受けることは大きな助けになるでしょう。夫婦カウンセラーがパートナーとの間で起きているモラハラや共依存のパターンを客観的に認識し、それを変えるための具体的なスキルも教えてくれます。
夫婦カウンセリングは必ずしも二人一緒に受ける必要はないため、パートナーが参加を拒否したり、一緒に参加することで状況が悪化する可能性がある場合は、一人でカウンセリングを受けることも有効でしょう。夫婦カウンセラーが客観的な立場から、相談者の状況が共依存関係に陥っているのか、離婚や修復の可能性についてもアドバイスを受けることができます。
 夫婦カウンセラー渡辺 里佳
夫婦カウンセラー渡辺 里佳夫婦問題カウンセラーの私のところにも、モラハラを受けている方からのご相談は少なくありません。男女ともに、自己肯定感の不足、不安症気味の傾向にあります。
妻の場合は、本文にあるように、経済的なパワーバランスの偏りが原因となるケースが多いです。ねじれた共依存の関係は、なかなか抜け出せなくなるのが怖いところです。関係性を自覚し、視野を広げるためにも、専門家の力が必要です。年月とともに深刻化しますので、早めの相談が大切です。
他の自分の居場所を作る
夫・妻と一緒にいる時間が長いほど、共依存の関係がエスカレートする傾向があります。普段生活する場所のほとんどが家庭または職場という人は、長時間過ごせる居場所を新たに作るといいでしょう。
地域活動や習い事など、定期的に家族と離れた場所で過ごすことで、モラハラや共依存の進行を抑えられる可能性があります。また、新しいコミュニティに参加することで、友人関係が広がり、夫婦関係を見直すきっかけを得られるかもしれません。
物理的に距離を置く
長年続く共依存から脱却するには、一定期間の別居などで、物理的な距離を置くことも有効な手段です。夫と妻双方の性格や考え方も関係する共依存は、どちらかが変わらない限り、解決が難しい問題です。しかし、大人になってから自分の性格や考え方を変えるのは、容易なことではありません。
そこで、モラハラや共依存の温床となっている自宅から思い切って別居に踏み切り、環境から変えてみましょう。夫・妻がいない環境で冷静になって考えることで、離婚も含め、共依存克服のためのよりよい選択肢が見つかるかもしれません。
離婚を検討する
モラハラの関係が長期間続き、相手に変化の意思がない場合、離婚を検討することも一つの選択肢です。
離婚を考える際に特に注意すべき点は、モラハラ関係においては、話し合いによる解決が非常に難しいということです。関係自体が平等ではなく、力の不均衡があるため、直接の話し合いでは不利な立場に立たされる可能性が高いのです。
そのため、離婚を検討する場合は、早い段階で弁護士に相談することで、適切な対応策を提案してくれるでしょう。
モラハラ夫・妻との共依存から脱出しよう


夫婦がお互いに依存し合う共依存の関係は、夫と妻双方の性格や考え方、思考パターンなどが絡み合って起こるため、自覚しづらく解決が難しい問題です。しかし、共依存の裏側にはDVやモラハラなどが隠れていることも多く、共依存が疑われるなら、早期に対処すべきでしょう。
夫婦の共依存が疑われる場合はチェックリストなどで確認し、まず身近な友人などに相談するのが良い方法です。自分たちだけで解決が難しい場合は、モラハラやDVが深刻化する前に、カウンセラーや弁護士といった専門家に相談しましょう。