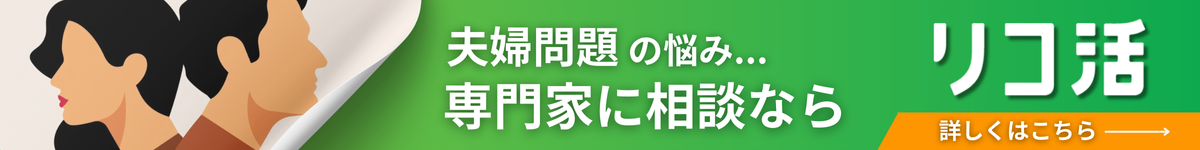離婚する際、養育費などの金銭面でもめるケースが少なくありません。特に養育費は子供が成人になるまで支払われ続けることが多く、後から滞納や不払い、減額や増額の要求が問題になることもあります。離婚の際の養育費の額などの決め方について、子供3人の夫婦を例に解説します。
鈴木 成公/新大塚法律事務所(第一東京弁護士会所属)
ホームページ:https://www.shin-ohtsuka.com/
離婚等の家族に関する案件や男女トラブルの案件を多く取り扱っている事務所です。法律的な観点だけでなく、人生の再出発に向けた総合的なアドバイスを様々な角度からさせていただきます。
詳しく見る
弁護士、依頼者がお互いに「正直であること」。信頼関係を築くことで、依頼者の目的を達成できると考えます。私は、依頼者の言葉を表面的に受け取り、その通りに進めていくことが「寄り添うこと」だとは思いません。依頼者の根底にある目的を把握し、良い着地点に運ぶ弁護士でありたいと思っています。

離婚したら養育費はいくら支払う?

離婚する夫婦の間に子供がいるときは、子供をどちらかが引き取るか(親権)を決める必要があり、親権を持たない親は一般的に子供が成人になるまで養育費を支払います。しかし、養育費の額をいくらにするか、話し合いが難航することも少なくありません。また、離婚後に養育費の滞納や不払い、増額や減額の申し出などでトラブルになることもあります。
養育費で揉めてます。
子供3人(全員15才以下)私が引き取ります。
毎月3万賞与時7万の養育費希望です。これでも少なく算出したつもりです。
私は手取り10万賞与なし、旦那手取り19〜21万賞与あり
私の提示する数字じゃ、これから扶養も抜けて手取りが減るし毎月どのくらいかかるかわからない。生活できるかわからない。とりあえず払える時は払うから。と公正証書を作りたくないのか話が進まないです。
子供3人いる父親です。養育費について悩んでおります。性格の不一致から妻に離婚を切り出されました。当初約束した金額は3人で、6万円で、入学等特別なお金が必要なときは支援するという約束だったのですが、突然7万5千円にしてほしいと言われました。上がった1万5千円分はボーナスで、ということなのですがボーナスで払うのはどうなのでしょうか?悩んでいます。
できるだけ互いに納得して養育費の額を決めるにはどうすればいいのか、養育費の相場や計算方法などを、子供が3人いる夫婦を例に解説します。
養育費とは子供の生活に必要な費用
離婚する際、夫婦の財産を公平に分ける財産分与や、配偶者の不法行為に対する慰謝料など、金銭に関わる問題を解決する必要があります。この中で、養育費は子供のためのお金です。よく、離婚を早く成立させるために「慰謝料も養育費もいらない」という人がいますが、これでは、本来子供のために受け取るべきお金を放棄してしまうことになります。
また、逆に慰謝料とは違って、離婚の理由や原因によって養育費の額が増減することはない、というのが基本的な考え方です。通常、「浮気で子供にも迷惑をかけたから、その分、養育費に上乗せする」ということはありません。養育費はどのような考え方で決められるのかを解説します。
養育費を払うのは親の義務
民法766条では、離婚協議をする際、「子の監護に要する費用の分担」について取り決めを行うことが定められています。これが養育費で、親である以上、離婚した後も子供の生活や教育に関する費用は互いに分担して負担しなければならないのです。そして、話し合いでは「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」ともされています。
また、親が離婚した後も、子供には離婚前と同等の生活を維持する権利があり、親はその権利を保障しなければなりません。これを「生活保持義務」といいます。養育費は、この義務に基づくものとも考えられています。こうしたことから、養育費の支払いは、親としての当然の義務だと考える必要がありますし、受け取る側も子供のために使わなければなりません。
養育費の額はどうやって決める?
養育費の金額は、夫婦それぞれの事情によって決められます。子供1人当たりいくらなどといった一律の相場があるわけではありません。養育費を決める際に、まず考えなければならないのは、夫婦それぞれの収入です。極端な話、子供を引き取る側に十分な収入があれば、養育費を決める必要はありません。
現実的には収入の少ない母親が子供を引き取るケースが多く、夫が妻に養育費を支払うのが一般的です。事情によっては逆のケースもあり得ます。ただし、支払う側も収入を超える負担はできませんし、自分の生活もありますから、互いの収入額を見ながら、相応の負担額を決める事になります。だからといって「生活が苦しいので、払えない」ということにはなりません。
また、子供の年齢や、子供の数によっても金額は変わります。特に子供の教育費にはお金がかかるので、中学、高校生の子供に対する養育費は小学生以下の子供より高くなる傾向があります。
このほか、生活保持義務の観点から、これまでの生活水準を維持できる額を確保する必要もあります。こうしたことから、夫婦の収入や生活水準、子供の年齢や数などさまざまな事情を考慮して養育費の金額が決められます。
養育費を決める際のポイント
多くの場合、離婚は夫婦の話し合いによって、双方が条件に合意することで成立します。これを協議離婚といいますが、養育費もほとんどのケースで、この条件の話し合いの中で決められます。話がつかなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
調停とは裁判所を介した話し合いで、離婚するかどうかを含めて話し合う離婚調停と、離婚を前提に養育費の支払いや額だけについて話し合う養育費請求調停があります。調停でも話し合いがつかないと、調停不調として調停が打ち切られます。
離婚調停が不調となった場合、裁判を起こして裁判所の判断を仰ぐこともできます。養育費請求調停が不成立になると、自動的に審判という手続きに移行し、裁判所が審問で双方の言い分を聞いたうえで、審判結果を夫婦それぞれに伝えます。
調停や裁判で養育費の額が決まれば、調停調書や判決文が作成されます。裁判で和解した場合は和解調書です。これらには法的な効力がありますから、将来、養育費の支払いが滞った場合も、強制執行などの強い手段がとれます。しかし、話し合いで決めた内容を口約束で済ませてしまうと、後から合意内容を反故にされてしまう恐れがあるので注意が必要です。
このため、通常は離婚協議書を作成し、お互いに持ち合いますが、離婚協議書では法的な効力が十分ではありません。強制執行などの可能性を考えて、公正証書にしておくことが大切です。公正証書は公証役場で作成し、公文書として扱われるため、強い法的効力を持ちます。
子供が3人いて離婚した場合の養育費の相場は?
養育費の算定表とは
養育費を算定する場合、通常は裁判所が公開している養育費算定表を使います。これは、東京や大阪の家庭裁判所の裁判官が研究結果として公表しているものです。夫婦それぞれの年収や子供の人数、子供の年齢を当てはめれば、標準的な養育額の目安を知ることができます。算定表は実際の離婚協議や、調停、裁判でも参考として使われています。
養育費算定表は最高裁判所のホームページで公開されているので、だれでも簡単に養育費を計算できます。
算定表の見方
具体的な算定表の使い方について説明します。
1.両親の年収を確認する
養育費算定表を使って養育費のシミュレーションをする前に、両親の年収が必要です。養育費の支払いでは、養育費を支払う側を義務者、養育費を受け取る側を権利者と呼びます。算定表を見る前に、権利者と義務者の年収を確認しておきましょう。
2.必要な算定表を選ぶ
養育費算定表は「子供の数」と「子供の年齢」で表が分かれています。たとえば、子供3人で計算する場合、年齢によって算定表は次の4つに分かれます。
・表6 養育費子3人表(第1子、第1子及び第3子0~14歳)
・表7 養育費子3人表(第1子15~19歳、第2子及び第3子0~14歳)
・表8 養育費子3人表(第1子及び第2子15~19歳、第3子0~14歳)
・表9 養育費子3人表(第1子、第2子及び第3子15~19歳)
子供の年齢に合った表を選びましょう。
3.養育費算定表の年収が重なるマスを確認する
養育費算定表は、縦軸が義務者の年収、横軸が権利者の年収になっています。それぞれの年収を選んで、両方のマスが交わったところが、目安となる養育費の金額となります。
子供3人の場合の養育費シミュレーション
たとえば、16歳、12歳、8歳の3人の子供を妻が引き取るケースを想定しましょう。この場合、それぞれの年収によって、算定額がどのように変わるのかを見ていきます。ただし、夫も妻も給与所得者(会社員や公務員)とします。
・夫の年収が800万円、妻は専業主婦(収入なし)
月額20万円~18万円
・夫の収入が400万円、妻は専業主婦
月額10万円~8万円
・夫の収入が800万円 妻は年収120万円
月額16万円~14万円
・夫の収入が400万円 妻は年収120万円
月額8万円~6万円
・夫の収入が800万円 妻は年収300万円
月額14万円~12万円
・夫の収入が400万円、妻の収入が300万円
月額6万円~4万円
このほか、子供の年齢によっても額は変動しますし、給与所得者か自営業者かでも変わります。ほかにも子供に高額な教育費や医療費がかかる場合などは、特別な事情として加算されることがあります。離婚を考える際に、一度養育費がいくらぐらいになるのか、シミュレーションしてみるといいでしょう。
給与所得と自営の収入の両方を得ている場合は、いくつかの計算方法がありますが、例えば、給与所得を自営の収入に換算してから合算し、自営業者として計算するなどで対処します
一度決まった養育費は変えられない?
養育費は一度決めた後も、事情の変化で増額を求めたり、減額を求めたりできます。例えば、養育費を支払っている側が、失業したり病気になったりすることもあります。明らかに収入が減少する場合は、負担額が減るのも仕方のないことです。
また、子供の進学や病気で支出が大幅に増えることもあります。こうした場合の事情の変化を理由に、養育費の増額について話し合いを求めることができます。
養育費を払う期間は?
養育費をいつまで払い続けるのかという支払い期間は、夫婦の合意があれば自由に決められます。「成人になるまで」「20歳まで」とするのが一般的です。なかには「大学を卒業するまで」「自立するまで」とするケースもあります。
ここで、問題になるのは2022年の民法改正で成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことです。支払期間を「成人になるまで」としていた場合、「18歳までに短縮されるのではないか」と不安になる人もいるのではないでしょうか。
この点については、法務省が民法改正前に取り決めていたものについては、民法改正の成人年齢引き下げの影響は受けないという見解を出しています。つまり、民法改正前の取り決めであれば、20歳のままだということです。ただし、民法改正後の取り決めであれば、18歳までということになります。「20歳まで」などと年齢を明記してあれば問題はありません。
支払う養育費を減額する方法
離婚当初は養育の支払に応じていたものの、収入の減少で支払いが困難になることもあります。「いつまで、多額の負担に耐えなくてはならないのか」と思うこともあるでしょう。しかし、条件さえ整えば、養育費を減額できることもあります。養育費を減額できるケースについて解説します。
減額が認められる条件とは
養育費を減額するには、合理的な理由が必要です。たとえば、次のような理由が考えられます。
・倒産やリストラなどで失業した
・病気やけがで働けなくなった
・養育費を支払う側が再婚をし、子供が生まれた
・再婚をして、再婚相手の子供と養子縁組した
失業したといっても、自己都合で退職したり、個人事業主として独立したりした場合は、減額が認められない可能性があります。また、再婚しただけでは減額理由にはならず、再婚をして新しく子供が生まれたり、再婚相手の子供と養子縁組したりして、扶養家族が増えたときなどに減額が認められることがあります。
養育費を受け取る側の事情で減額が認められることもあります。たとえば次のようなケースです。
・再婚して、再婚相手と子供が養子縁組した・収入が大幅に増加した養育費を受け取る側の収入が大幅に増加して、生活にゆとりができた場合などは減額の求めがみとめられることがあります。しかし、収入増が最初から見込まれていた場合は、減額理由にはならないでしょう。
また、養育費を受けとっている側が再婚し、子供と再婚相手が養子縁組した場合は、法律上、再婚相手に子供を扶養する義務が生じます。このため、養育費が減額されたり、免除されたりする可能性があります。
以上のような事由で、養育費の減額が認められる場合があるので、可能な限り、相手の事情の変化を把握できるようにしておくことも必要です。
離婚協議書や調停調書などに、養育費の支払期間が終了するまでの間、相互に、勤務先の変更、再婚及び養子縁組などの事情が生じた場合は、元配偶者に通知することを義務付けておくといいでしょう。
減額を相手に申し入れる
養育費の額は基本的に当事者間で話し合って決めるもので、当事者同士で合意すれば、金額を変更しても問題はありません。まずは事情を話して、減額を相手に申し入れましょう。やむをえない事情があれば、相手も話し合いに応じてくれるかもしれません。
もし、話し合いの結果、減額で合意ができても、相手が後から「減額に応じたつもりはない」と主張してトラブルになる恐れもあります。合意書を作成したり、合意内容を公正証書として残しておいたりするほうがいいでしょう。
養育費減額調停を申し立てる
当事者間で話し合っても、養育費の減額で合意できない場合は、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てることができます。養育費減額調停では、裁判官や調停委員を介して、養育費の減額が妥当かどうかについて話し合います。調停で合意することを調停成立と言います。話し合いで決着しなければ、調停不成立となり打ち切られます。
調停の期間は約半年程度です。調停不成立となった場合は、養育費減額審判に移行します。審判手続では、裁判官が調停時に当事者双方から聞いた話の内容や提出された証拠(資料)、家庭裁判所の調査結果などに基づいて、養育費の減額が妥当かどうか判断を下します。
審判結果に納得がいかないときは、即時抗告して異議を唱えることができます。即時抗告せずに、2週間経過すると審判の結果が確定します。
減額してほしいときは弁護士に相談を
養育費の減額には、相手もよほど生活に余裕がない限りは簡単には応じてくれないでしょう。説得には、法律や裁判例などの知識も必要です。夫婦問題に詳しい弁護士に相談すれば、よいアドバイスが得られるでしょう。
リコ活なら、養育費に関する悩みも、夫婦問題に詳しい弁護士に無料でオンライン相談できます。ぜひ、無料登録して、お気軽に相談してみてください。
養育費がいくらになるか悩んだら専門家に相談を
養育費は子供が幸せに暮らせるよう支払うお金で、支払いは親の責務といえます。離婚時には感情的になって「養育費はいらないから離婚してほしい」「養育費の支払いには応じない」などと考えることもありますが、親としてしっかり養育費について取り決めましょう。
養育費は、子供の人数や双方の収入などの事情に応じて目安となる額も決まってきます。どのように話し合いを進めていいのかわからないときは、夫婦問題に詳しい弁護士に相談してみましょう。