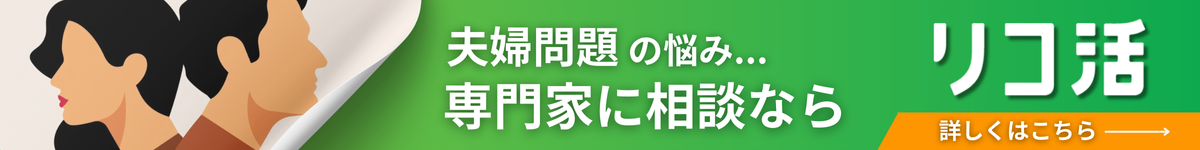離婚を考え始めると、家庭裁判所でどこまで相談できるのか、不安や疑問を抱える方も少なくありません。実際のところ家庭裁判所は離婚そのものについての相談窓口ではなく、主に離婚調停といった法的手続きの場として機能しています。特に離婚調停を利用する場合は、提出すべき書類や申立費用、家庭裁判所での話し合いの進め方など、知っておくべきポイントが多数あります。
本記事でわかること
・家庭裁判所で離婚相談はできないが、調停の手続き案内は無料で受けられる
・離婚の4つの流れと各段階でできること
・あなたの状況に合った適切な相談先の選び方
・家庭裁判所の手続案内窓口の利用方法
離婚・相続・交通事故など、人生の転機に寄り添う法的サポートを提供。依頼者との信頼関係を重視し、専門的な情報をわかりやすく伝える姿勢に定評がある。
詳しく見る
子どもの権利委員会に所属し、離婚に伴う子どもの問題にも積極的に取り組む。敷居の低い相談スタイルと温かな人柄で、地域に根ざした弁護活動を続けている。

家庭裁判所で離婚相談はできる?
離婚のイメージとして真っ先に思い浮かぶのが「家庭裁判所」という方もいるかもしれませんが、実際にどんなことができるのでしょうか。
名称のイメージから「家庭にまつわる相談を一手に引き受けてくれる場所」という印象を抱く方もいるでしょう。しかし、家庭裁判所は法的手続きに特化しており、具体的な相談窓口としての機能を果たすわけではありません。
離婚に関する悩みごとは、法的な解決だけでなく、心理面や将来の生活設計など複合的な視点が求められるため、そうしたサポートは弁護士や夫婦カウンセラー、市役所の相談窓口などが担当するケースが多くあります。
その一方で、夫婦間だけで離婚の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるといった方法が重要な解決策となります。まずは家庭裁判所でできることを見てみましょう。
家庭裁判所でできる「離婚手続き」についての相談
家庭裁判所では「離婚相談」は行っていませんが、「離婚調停の手続き」については無料で詳しく教えてもらえます。

手続案内で相談できる内容
基本的な手続きについて
- 離婚調停とは何か(概要説明)
- 調停の流れと期間の目安
- 調停期日の進行方法
- 調停委員の役割
- 調停不成立の場合の次の手続き(審判・訴訟)
申立てに関する手続き
- どこの家庭裁判所に申立てすればよいか(管轄の確認)
- 申立書の書き方・記載方法
- 必要な添付書類の種類
- 戸籍謄本などの取得方法
- 手続きに必要な収入印紙の金額
- 郵便切手の金額(各裁判所に確認が必要)
- 書類の提出方法(持参・郵送)
- 受付時間
調停で決められる内容の説明
- 離婚そのものについて
- 親権者の指定
- 養育費の決定
- 面会交流の取り決め
- 財産分与の方法
- 慰謝料の請求
- 年金分割の手続き
- 婚姻費用の分担
調停成立後の手続き
- 10日以内の離婚届提出義務
- 調停調書謄本の取得方法
- 年金分割の請求手続き
- 届出先(市区町村役場)
手続案内では相談できないこと
手続案内では、離婚すべきかどうかの判断、慰謝料や養育費の適正金額、有利な条件で離婚する方法など、個別の事情に応じた法的アドバイスや判断を伴う相談は一切行っていません。また、相手方との交渉方法や調停での話し方のアドバイス、精神的なカウンセリングなどの継続的なサポートも提供していません。これらの相談が必要な場合は、弁護士や専門のカウンセラーに相談する必要があります。
参照: 最高裁判所「夫婦関係調整調停(離婚)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_01/index.html)
家庭裁判所で「離婚手続き」について相談をする方法
手続案内窓口の利用方法
各家庭裁判所には手続案内窓口が設置されており、平日の午前8時30分から午後5時まで利用できます。夫婦間、親族間の紛争や相続問題等について、家庭裁判所を利用する場合の申立手続の概要、申立書の記載方法などの案内を行っています。これについての費用は無料で、予約の必要はありません。

窓口での相談の流れ
- 受付で「離婚調停の手続きについて相談したい」旨を伝える
- 整理券を受け取り、順番を待つ
- 担当者から手続きの説明を受ける
- 申立書や必要書類について確認
- 不明な点について質問
窓口相談で準備しておくべきこと
- 基本的な状況の整理(別居の有無、子どもの有無など)
- 具体的に知りたい手続きの内容
- 手帳やメモ帳(説明内容を記録するため)
- 身分証明書(本人確認のため)
手続案内窓口では、手続きの方法は説明してもらえますが、離婚が可能か、慰謝料はいくらかなどの判断を伴う事項についてはお答えできません。あくまでも、家庭裁判所への事務手続きに関して教えてもらえるのみとなる点に注意しておきましょう。
参照:最高裁判所「東京家庭裁判所家事手続案内」( https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/kasai_tetuzuki/index.html )
参照:裁判所「窓口案内」(https://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/madoguti/index.html)
電話での問い合わせ
各家庭裁判所のウェブサイトに記載されている代表電話番号に連絡し、「手続案内」または「民事受付」につないでもらうことで、電話で相談することも可能です。

電話相談が可能な内容
- 管轄裁判所の確認
- 申立てに必要な書類の種類
- 費用(収入印紙・郵便切手の金額)
- 受付時間や方法
- 調停の大まかな流れ
電話での問い合わせ時の注意点
- 平日の業務時間内(午前8時30分~午後5時)に連絡
- 具体的な質問内容を事前に整理しておく
- 複雑な内容は来庁での相談を勧められる場合がある
- 個人的な事情についての相談は受けられない
家庭裁判所での離婚調停とは?
話し合いで解決しない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。家庭裁判所で行われる離婚調停の流れを説明します。
離婚調停の流れ
- 家庭裁判所への申立て(相手方の住所地管轄)
- 第1回調停期日の指定(申立てから1~2ヶ月後)
- 調停委員による話し合い(月1回程度)
- 合意成立または不成立
必要な費用
- 収入印紙:1,200円
- 郵便切手:各家庭裁判所により異なる
- 戸籍謄本等:450円
調停委員の役割
- 中立的な立場での話し合いの仲裁
- 法的な助言
- 合意に向けた提案
調停で決められる内容
離婚調停では、「離婚するか・しないか」だけでなく、以下の離婚条件についても同時に話し合うことができます。
- 親権者の指定
- 養育費の金額
- 面会交流の方法
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
離婚調停が不成立となった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
離婚したい場合の専門家への相談先は?
離婚は法的な問題であると同時に、感情面や生活面の対策も必要とされる複雑な問題です。そのため、相談先を家庭裁判所だけに限定するのではなく、弁護士やカウンセラー、自治体の相談窓口など複数の機関を上手に組み合わせることが重要です。

弁護士
離婚における法律上の手続きや制度をしっかり理解したい場合には、弁護士が最適な専門家となります。家庭裁判所での離婚調停や離婚訴訟に詳しい弁護士であれば、書類の準備や交渉のサポートなど、手続きを円滑に進めるアドバイスを受けることができます。
また、財産分与や慰謝料、養育費の算定など、金銭的トラブルになりやすい部分においては、法的な根拠を踏まえた主張や交渉が必要です。弁護士が介入することで、感情に流されずに論点を整理し、客観的かつ合理的な結論を目指しやすくなります。
初回の相談は無料で行っている場合も多いため、まずは初回相談を受けてみて、費用や対応方針を聞いてから依頼を検討するのがおすすめです。
 佐々木総合法律事務所/佐々木 規雄弁護士
佐々木総合法律事務所/佐々木 規雄弁護士弁護士は、相談者や依頼者の立場にたって、その人にとってのメリット、デメリットを考えていきます。
複数ある選択肢や進め方についても、弁護士から説明を受けることができ、自分で決定するための判断材料を提供してもらうこともできます。
弁護士は「あなたにとっての伴走者」といっても過言ではないかもしれません。


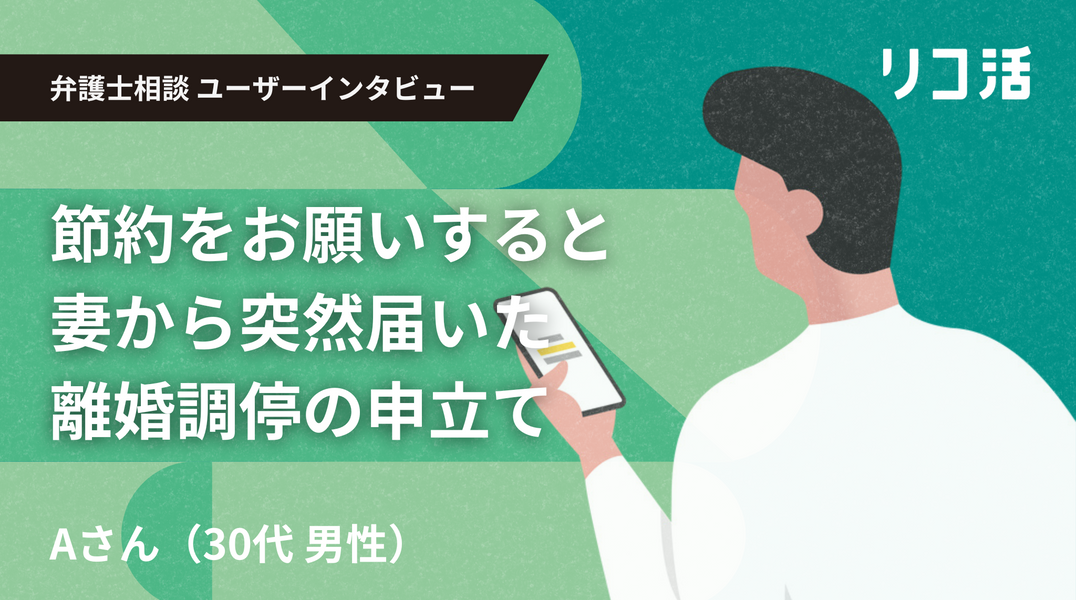
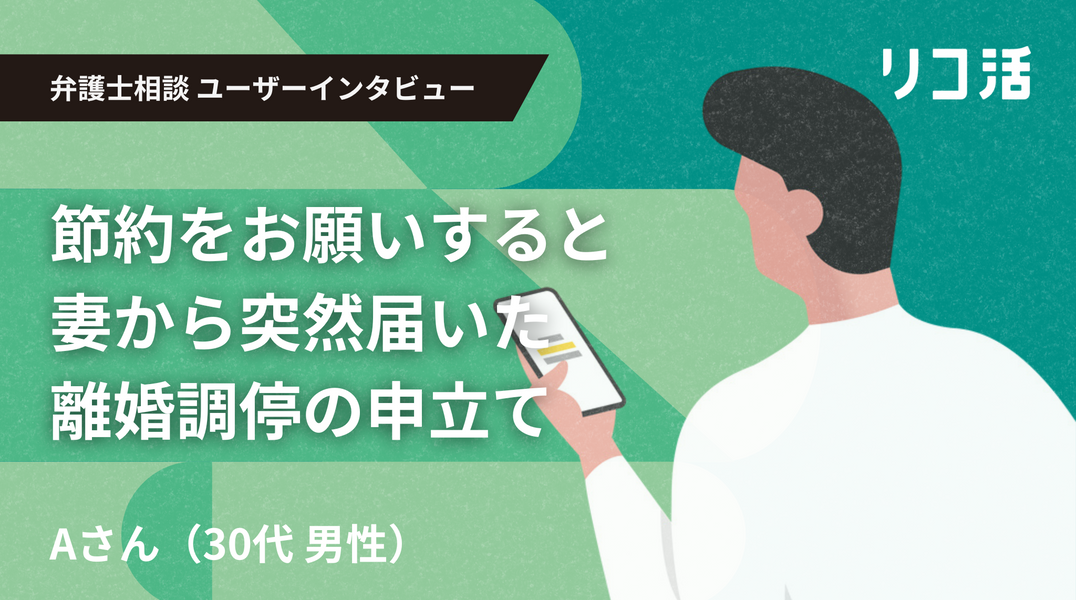
夫婦カウンセラー
夫婦カウンセラーは、主に感情面やコミュニケーション面のサポートを担当する専門家です。離婚を考える過程では、夫婦関係のわだかまりや心理的負担が大きくなる場合が多く、冷静な判断が難しくなることがあります。
カウンセリングでは、現在の夫婦関係を客観的に見つめ直したり、離婚が本当に必要かどうかをじっくり考えたりするサポートが受けられます。夫婦関係そのものを修復できる可能性があるならば、離婚を回避する道を探ることもあるでしょう。
また、離婚を不可避と判断したとしても、カウンセラーの助言を得ながら気持ちを整理することで、今後の新生活への心理的準備が進めやすくなります。弁護士への法的な相談と、メンタル面での夫婦カウンセラーへの相談を同時並行で行う方もいます。




ADR(裁判外紛争解決手続き)
ADRとは、裁判所以外の中立的な民間機関を通じて紛争を解決しようとする手続きのことです。民間の調停機関や団体が間に入って話し合いを進めるため、裁判所での調停よりも柔軟かつ短期間で解決する場合があります。
また、仲介人を通した当人同士の話し合いを基本とするため、対立構造が生じにくい点も特徴の一つです。
ただし、裁判所での調停と同様、合意に至らない場合は最終的に訴訟に進むこともあり得ます。双方が話し合いによって解決したいという意向をしっかり持っている場合に、特に有効な手段となるでしょう。
その他の相談窓口
市区町村の役所には、専門の相談員を置いている場合があり、公的機関の相談窓口では、夫婦関係や子どもの養育環境に関する基礎的な情報提供、各種サービスの案内などを無料で受けられることが多いです。
また、女性相談センターなど、DVや深刻なトラブルを抱えている方専用の窓口も存在します。相談員がケースに応じてシェルターの紹介や弁護士の手配などを行ってくれる場合もありますので、安全の確保が急務な場合にも頼りになります。
相談内容に応じて適切な団体や専門家へ案内してくれるため、どこに相談すればよいか迷うときは最初の窓口として活用してみるとよいかもしれません。
離婚までの流れ
離婚を検討している方が知っておくべき手続きの流れを段階別に解説します。離婚問題の解決には複数の選択肢があり、まずは話し合いから始まり、必要に応じて法的手続きへと進んでいきます。上の段階ほど当事者の合意を重視し、下に行くほど法的拘束力が強くなる点も覚えておきましょう。


1. 協議離婚
夫婦間の直接的な話し合いで離婚条件を決めます。協議離婚を成立させるためにも、夫婦カウンセラーのサポートを受けながら感情的な対立を避け、今後の方向性を検討する方法もあります。
協議離婚に合意できれば離婚届を提出するだけで離婚が成立し、最も簡単で費用も抑えられます。日本の離婚の約90%がこの協議離婚で成立しており、最も一般的な離婚方法です。
離婚後のトラブルを防ぐために、公正証書を作成しておくと安心です。
2. ADR(裁判外紛争解決手続き)
協議離婚の一種として、中立的な第三者の仲介を交えて離婚するADR(裁判外紛争解決手続き)という方法もあります。オンラインで対応でき、家庭裁判所の調停よりも柔軟な対応が可能で、比較的短期間での解決が期待できます。また、合意内容を記録した「合意書」が作成されます。
3. 調停
ADRでも解決しない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が間に入って話し合いを進めます。調停前置主義により、原則として裁判の前に調停を経る必要があります。家庭裁判所での調停は公的な手続きのため、調停調書には法的拘束力があります。
4. 裁判(審判・訴訟)
調停が不成立の場合、最終的に裁判所が離婚を判断します。法定離婚事由(不貞、悪意の遺棄、3年以上の生死不明など)が必要です。証拠に基づく立証が求められるため、弁護士への依頼がほぼ必須となります。
上の段階ほど当事者の合意を重視し、下に行くほど法的拘束力が強くなります。多くの場合、協議離婚で解決されます。
離婚したい場合の状況別 おすすめ相談先
離婚を考える背景や状況によって、最適な相談先は異なります。代表的なケースに応じておすすめの方法を解説します。ご自身の置かれた状況と照らし合わせながら、最適な選択肢を探してみてください。


相手と連絡を取りたくないケース
弁護士に依頼することで、相手方との直接的な連絡を避けながら離婚手続きを進められます。弁護士が代理人として交渉を行うため、精神的負担を大幅に軽減できます。
話し合いで解決したいケース
夫婦関係が比較的良好で感情的対立が少ない場合は、協議離婚での解決を目指せます。ただし、養育費や財産分与を曖昧にしたまま進めると後々トラブルになるため、合意内容の書面化と公正証書作成が重要です。
話し合いが平行線をたどる場合は、夫婦カウンセリングで問題を整理し、ADR(裁判外紛争解決手続き)の利用もおすすめです。家庭裁判所による調停よりも早期に柔軟な合意点を見つけられるでしょう。


子どもがいるケース
親権、養育費、面会交流といった問題は子どもの将来を左右するため、慎重な対応が必要です。弁護士に相談すれば、養育費算定表や法的基準に基づいたアドバイスを得られ、感情的な対立を軽減できるでしょう。
また、自治体の公的相談窓口の利用も有効です。問題がこじれる前に、早めの情報収集をおすすめします。




DVがあるケース
配偶者からの暴力がある場合、まずは自身と子どもの安全確保が最優先です。警察や自治体の女性相談センター、配偶者暴力相談支援センター、民間シェルターに相談し、必要に応じて保護措置を受けてください。
離婚手続きについては、DV事案に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。保護命令の申請や安全な環境下での離婚調停の進め方など、具体的な方策を得られます。子どもがいる場合は、加害者からの接近禁止も含め、子どもの安全を最優先に手続きを検討しましょう。
財産分与が複雑なケース
多額の財産や複雑な資産構成がある場合、弁護士への相談が必須です。会社経営や不動産投資が関わる場合は、弁護士に相談の上、税理士やファイナンシャルプランナーを交えた相談も検討しましょう。
財産隠しのリスクがある場合は、証拠書類の収集と離婚調停での法的手段も視野に入れる必要があります。
「家庭裁判所の離婚相談」に関するよくある質問(Q&A)
Q1. 家庭裁判所に離婚相談の電話をしても断られるのですか?
家庭裁判所では離婚相談そのものは行っていませんが、離婚調停の手続きについては電話で案内してもらえます。「離婚相談」ではなく「離婚調停の手続きについて教えてください」と伝えれば、必要書類や費用、申立て方法などを詳しく説明してもらえます。
Q2. 家庭裁判所以外で離婚相談できる無料の窓口はありますか?
はい、多数あります。市区町村の無料法律相談、法テラスの無料相談、弁護士会の無料相談会、自治体の家庭相談員などが利用できます。また、女性相談センターやDV相談支援センターでも離婚に関する相談を受け付けています。
Q3. 家庭裁判所で離婚調停を申し立てる前に、必ず他の相談先を利用する必要がありますか?
法的な義務はありませんが、調停前に協議離婚やADRでの解決を試すことをおすすめします。調停は時間と費用がかかるため、まずは夫婦カウンセラーや弁護士に相談して話し合いでの解決可能性を探ってみてください。それでも解決しない場合に家庭裁判所での調停を検討しましょう。
Q4. 家庭裁判所の離婚調停と離婚相談の違いは何ですか?
離婚調停は法的な手続きで、調停委員を通じて離婚条件を話し合う場です。一方、離婚相談は離婚すべきかどうかの判断や今後の方針についてアドバイスを受けることです。家庭裁判所は調停の場は提供しますが、相談業務は行っていません。相談が必要な場合は弁護士や夫婦カウンセラーを利用してください。
離婚を検討している場合は、適切な相談先を確認しましょう
離婚を検討している場合、まずはご自身の状況に応じた適切な相談先を選択することが重要です。
家庭裁判所の手続案内は無料で利用できるため、調停の申立て方法や必要書類について詳しく知りたい場合は積極的に活用してください。早めの適切な相談により、よりスムーズで納得のいく離婚問題の解決が可能になります。