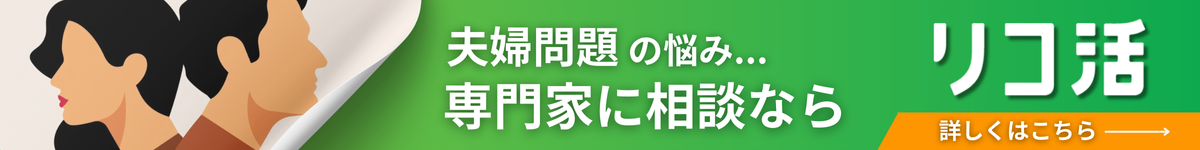パートナーから離婚を切り出されると、驚きや不安に駆られ、どう動けばよいのか分からなくなるものです。大切なのは、感情に流されずに自分自身の気持ちと向き合いながら、適切な行動を選択することです。
離婚を回避したい場合、または離婚を受け入れるかどうか悩む場合でも、事前に押さえておきたい情報や手順があります。本記事では、離婚するかどうか迷ったときに必要な初動から専門家の活用方法まで、体系的に解説します。
この記事でわかること
・離婚したいと言われた時の適切な初期対応と避けるべきNG行動
・夫婦関係修復のための具体的な方法
・離婚が避けられない場合の法的準備
鈴木 成公/新大塚法律事務所(第一東京弁護士会所属)
ホームページ:https://www.shin-ohtsuka.com/
離婚等の家族に関する案件や男女トラブルの案件を多く取り扱っている事務所です。法律的な観点だけでなく、人生の再出発に向けた総合的なアドバイスを様々な角度からさせていただきます。
詳しく見る
弁護士、依頼者がお互いに「正直であること」。信頼関係を築くことで、依頼者の目的を達成できると考えます。私は、依頼者の言葉を表面的に受け取り、その通りに進めていくことが「寄り添うこと」だとは思いません。依頼者の根底にある目的を把握し、良い着地点に運ぶ弁護士でありたいと思っています。

離婚したいと言われたら、まず取り組むべき3つのこと
離婚を切り出された時点で、衝動的に反応してしまうと、泥沼化や取り返しのつかない対立に発展する可能性があります。まずは今の夫婦関係やそれまでの経緯を客観的に振り返ることが欠かせません。
1.感情論を避けて冷静に対処する
「離婚したい」と言われた瞬間は、誰でも動揺してしまうものです。しかし、感情的な反応は状況を悪化させる可能性があります。まずは深呼吸をして、相手を責めたり感情的に反発したりするのではなく、冷静に話を聞く姿勢を保ちましょう。
2.離婚を切り出された理由や背景を振り返る
相手が離婚を切り出すには必ず理由があります。不倫や浮気、モラハラ、価値観の違い、家事や育児の分担問題など、離婚理由は様々です。相手から具体的な離婚理由を聞くとともに、これまでの夫婦関係を客観的に振り返り、問題の原因や背景を整理することが重要です。
3.相手の本気度を見極める
「離婚したい」という言葉が、一時的な感情から出たものなのか、それとも真剣に検討した結果なのかを見極める必要があります。相手の態度や具体的な行動(別居の提案、離婚届の準備、弁護士への相談など)から本気度を判断しましょう。相手の本気度によって、今後の対処法や方向性が変わってきます。
離婚を回避したい場合に行うアクション
一度切り出された離婚の話を白紙に戻すには、正しい手順と相応の努力が必要です。離婚を望まない場合は、法的・精神的な支援策を活用して関係改善を図りましょう。

離婚届不受理申出書を提出する
相手が勝手に離婚届を提出するリスクを防ぐため、役所に離婚届不受理申出書を提出できます。これにより一方的な離婚届が出されても受理されません。
離婚届不受理申出書には有効期間があるため、早めの提出と更新管理が必要です。相手が強い意志を示している場合は、突発的な離婚届提出を避けるために特に重要です。
ただし、この申出書は離婚そのものを解消するわけではありません。時間的猶予を得て話し合いをするための手段です。提出後は真剣に修復方策を探り、問題に向き合う努力が必要です。
夫婦円満調停(夫婦関係調整調停)を検討する
夫婦間の溝が深い場合でも、裁判所の夫婦円満調停を利用すれば第三者が入り公的な場で話し合いができます。調停委員が双方の意見を整理してくれるため、個人では行き詰まった問題解決が進むことも少なくありません。
夫婦円満調停のメリットは、非公開であることと専門家が仲介することです。相手と直接話し合うことが難しい場合でも、調停の場で必要な情報交換が進められます。
調停により完全な和解に至らずとも、一定の合意や改善策を見出し離婚を回避できるケースも多くあります。真剣に関係修復を望むなら、調停を前向きに活用しましょう。
夫婦カウンセリングを受ける
夫婦カウンセリングは、プロのカウンセラーの下で夫婦のコミュニケーションパターンや問題点を客観的に把握できる場です。お互いの言い分や感情を引き出しつつ、対立の根源を探ることが期待できます。
友人や家族のサポートも大切ですが、個人的な感情が入る場合があります。一方、カウンセリングでは第三者が中立的な立場でアドバイスを行うため、冷静な判断材料を得やすくなります。
客観的な視点を得ることで歩み寄りの糸口を見つけやすくなり、離婚回避への可能性を高める効果が期待できます。

夫婦間のコミュニケーションを再構築する具体的なステップ
1. 相手の話に耳を傾ける
相手が抱える不満や要望を正しく理解することから始めます。問題の本質に到達するためには、まず相手の気持ちを受け止めることが重要です。
2. 自分の意見を丁寧に伝える
自分自身の意見や希望も感情的にならず言葉を選んで話しましょう。相手との距離を広げることなく、建設的な対話を心がけます。
3. 日常的な会話を増やす工夫をする
スケジュールの共有や相手の趣味・興味への理解など、小さな歩み寄りを積み重ねます。日常的なコミュニケーションの量を増やすことが、関係修復の土台を築きます。
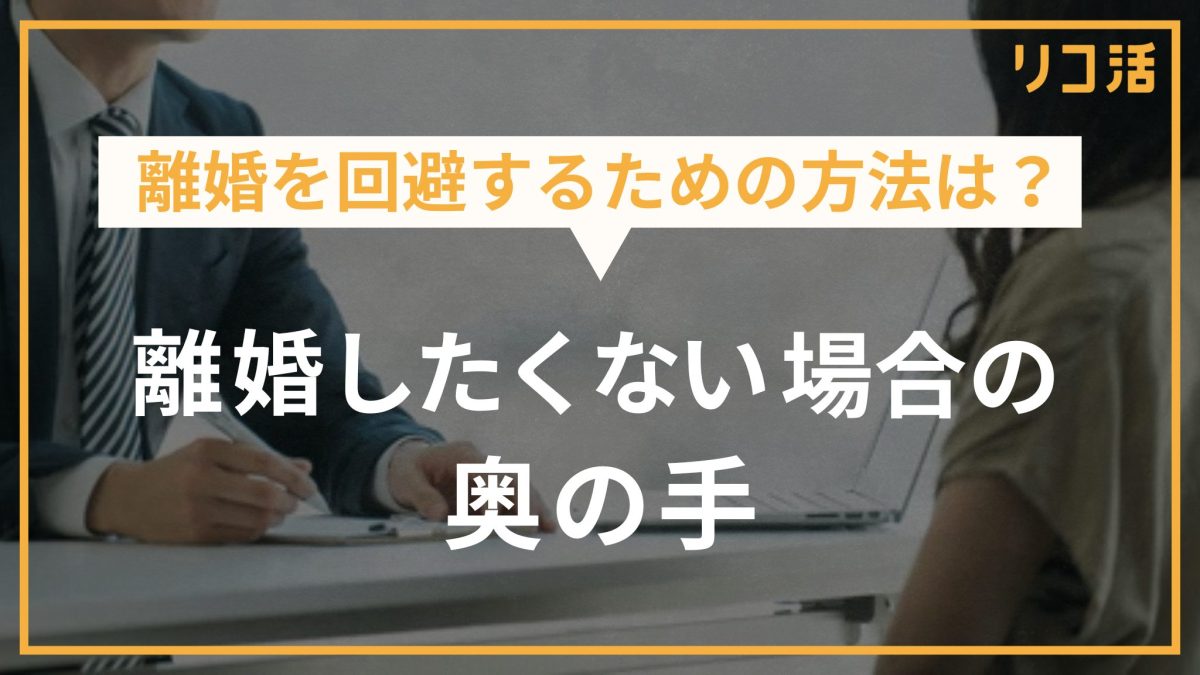
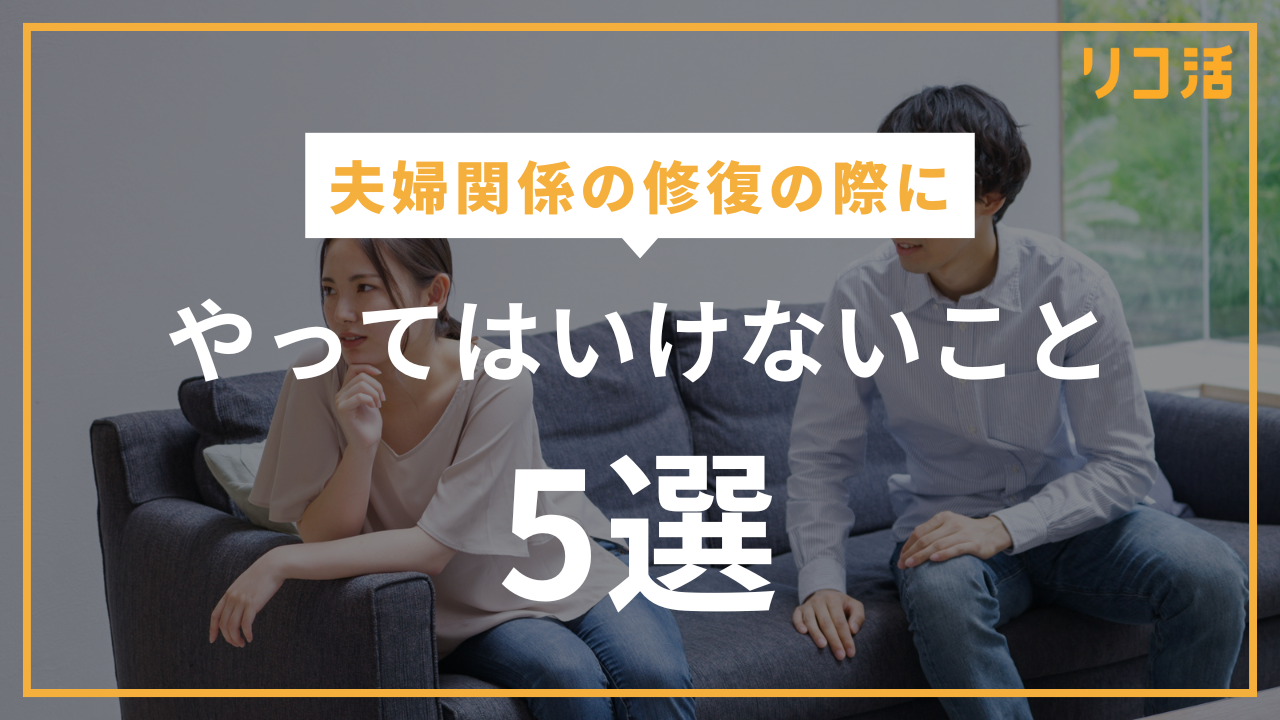
離婚したいと言われてからのNG行動
離婚したいと言われた時の対応によっては、状況をさらに悪化させる可能性があります。感情的になりやすい状況だからこそ、やってはいけない行動を理解しておくことが重要です。以下の行動は関係修復を困難にし、離婚条件でも不利になるリスクがあります。

感情的になって相手を責めたり怒鳴ったりする
感情的になって相手を責めたり怒鳴ったりすることは絶対に避けるべきです。攻撃的な言葉は相手との関係をさらに悪化させ、冷静な話し合いを不可能にします。感情的な反応は相手に恐怖心を与えるため、一度冷静になる時間を作ってから話し合うことが大切です。
一方的に離婚を拒否して話し合いを避ける
頭ごなしに拒否して話し合い自体を避けることは問題を先送りするだけです。話し合いを避け続けることで、相手は調停や裁判という法的手続きに進む可能性があります。まずは相手の気持ちを聞き、問題点を整理することから始める必要があるでしょう。
子どもを巻き込んで味方につけようとする
子どもを大人の問題に巻き込んで味方につけようとすることは最もやってはいけない行動です。相手の悪口を子どもに吹き込む行為は子どもの心を深く傷つけます。子どもを使って相手にプレッシャーをかけることは、親権判断で不利になる可能性もあるでしょう。
相手の行動を監視したりストーカー行為をする
相手の行動を過度に監視したりストーカー行為をすることは法的にも問題があります。携帯電話を勝手にチェックしたり、職場に押しかけるなどの行為は相手の人権を侵害します。このような行動は離婚理由を正当化してしまう結果になりかねません。
勝手に財産を処分したり隠したりする
共有財産を勝手に処分したり隠したりすることは法的に大きな問題となります。預金を勝手に引き出して隠す、不動産を無断で売却するなどの行為は財産隠しとみなされる可能性があります。財産分与で不利な扱いを受けるだけでなく、相手からの信頼を完全に失ってしまうでしょう。
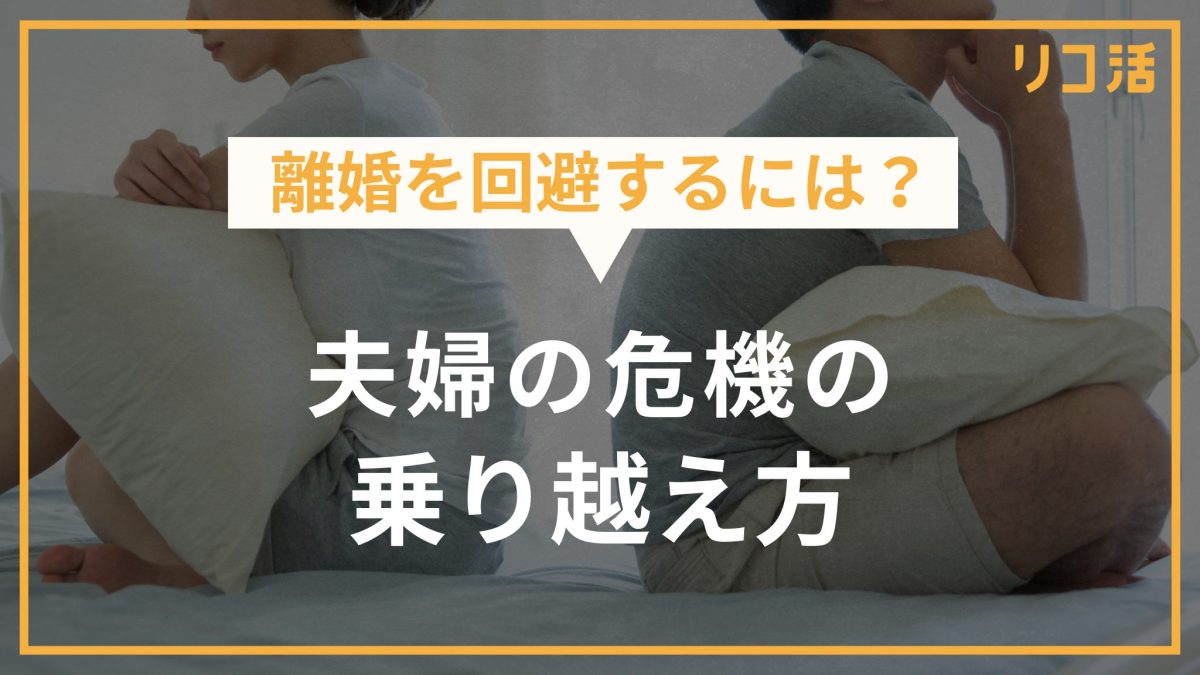
離婚したいと言われたときの夫婦間の話し合いのポイント
離婚したいと言われた場合、まずは冷静な話し合いが必要です。感情的な対応ではなく、具体的な問題点を整理し、関係修復の可能性を探ることが大切です。お互いの気持ちを理解し合うための建設的な対話を心がけましょう。
なお、二人だけでの話し合いが難しい場合は、夫婦カウンセリングを受けることをおすすめします。

価値観や将来像を共有する
結婚観や子育て観、今後の人生設計について率直に話し合いましょう。転職や転居への考え方、親との関係性、お互いの将来への期待など、これまで十分に話し合えていなかった価値観のズレを確認することが重要です。夫婦関係を続けていく上で、共通の目標や方向性を見つけられるかどうかがポイントになります。
経済面の不安・不満を具体的に確認する
家計管理の方法や収入への不満、将来のお金に対する不安について具体的に話し合います。仕事への取り組み方や家計への貢献度、教育費や住宅ローンなどの将来設計も含めて検討しましょう。経済的な問題は夫婦関係に大きな影響を与えるため、お互いが納得できる解決策を見つけることが必要です。
家事・育児分担の問題を整理する
日常的な家事や育児の分担について、現状の不満と改善点を整理します。子どもがいる場合は、養育や教育方針についても話し合いが必要です。お互いの仕事の忙しさや体力的な負担を考慮しながら、公平で現実的な役割分担を検討しましょう。一緒に家庭を築いていく意識を共有することが大切です。
コミュニケーション不足の原因を探る
夫婦間の会話の頻度や質について振り返り、コミュニケーションが不足している原因を探ります。お互いの時間の使い方や関係性を見直し、日常的な意見交換ができる環境を作れるかどうかを検討しましょう。パートナーとして理解し合うための具体的な方法を話し合い、関係修復への道筋を見つけることが重要です。
離婚したいと言われた時に子どもに配慮すべきこと
離婚問題が発生した際、最も大切なのは子どもへの配慮です。夫婦関係の問題は大人の事情であり、子どもには何の責任もありません。親権や養育費などの条件も重要ですが、まずは子どもの心と生活を守ることを最優先に考えましょう。

子どもの前での夫婦喧嘩を避ける
子どもの前で感情的になったり、相手を責めるような言葉を使ったりするのは絶対に避けましょう。子どもは両親の争いを見ることで深く傷つき、不安を感じます。離婚理由や夫婦関係の問題について話し合う際は、子どもがいない場所で行うことが必要です。冷静な対応を心がけ、子どもの前では普段通りの接し方を維持しましょう。
子どもに責任を感じさせない配慮をする
「パパとママがうまくいかないのは、あなたのせいではない」ということを明確に伝えることが重要です。子どもは自分が原因で両親が離婚するのではないかと不安になることがあります。
年齢に応じた適切な言葉で、これは大人の問題であり、子どもには何の責任もないことを繰り返し伝えましょう。子どもの気持ちを受け止め、安心感を与える対応が必要です。
子どもの生活の安定性を確保する
離婚による環境の変化が子どもに与える影響を最小限に抑えるため、可能な限り生活の安定性を保ちましょう。転校や転居を避ける、習い事や友人関係を継続させる、経済的な不安を子どもに感じさせないなどの配慮が必要です。
養育費や親権の取り決めも、子どもの将来と安定した生活を第一に考えて決定しましょう。
離婚を検討する場合は決まってから子どもに伝える
離婚について検討している段階では、子どもには伝えないことが重要です。夫婦の話し合いや調停で方向性が決まり、具体的な離婚条件や今後の生活について明確になってから子どもに説明しましょう。
不確定な情報は子どもの不安を増大させ、感情的な混乱を招く可能性があります。親権や面会の取り決め、新しい生活環境などが決定してから、年齢に応じた適切な言葉で伝えることが子どもの理解と受け入れにつながります。
子どもの心理的な変化に注意を払う
離婚問題が表面化してから、子どもの行動や感情の変化に細心の注意を払いましょう。食欲不振、睡眠障害、学校での問題行動、関係性の変化などが見られる場合があります。
必要に応じてカウンセラーや専門家への相談を検討し、子どもの心のケアを優先してください。お互いが子どもの理解に努め、適切なサポートを提供することが大切です。
離婚するか迷っているときに検討すべきこと
離婚したいと言われて動揺している時こそ、冷静な判断が必要です。感情的な反応ではなく、客観的な視点で現状を分析し、今後の人生について慎重に検討しましょう。夫婦関係の修復可能性や離婚後の生活への影響を総合的に考慮することが重要です。
一時的な感情か根本的な問題かを見極める
相手が離婚したいと言った理由が、一時的な感情によるものなのか、根本的な夫婦関係の破綻なのかを見極めることが重要です。ストレスや疲労、仕事上の問題などが原因で一時的に気持ちが不安定になっている可能性もあります。
不倫やモラハラ、価値観の根本的な違いなど、深刻な問題が背景にある場合は関係修復が困難な場合もあります。相手の本気度と問題の性質を慎重に分析しましょう。
離婚後の生活設計を具体的にシミュレーションする
離婚した場合の生活を具体的にシミュレーションし、現実的な見通しを立てることが必要です。住居の確保、仕事や収入の見通し、お金の管理方法などを詳細に検討します。一人で生活していけるだけの経済的基盤があるか、子どもがいる場合は育児と仕事の両立が可能かを現実的に判断することが必要です。理想ではなく、実際の生活レベルでの検討が重要です。
別居期間を設けて冷静に考える時間を作る
夫婦が一緒にいる状態では感情的になりやすいため、別居して冷静に考える時間を設けることが有効です。別居によりお互いの存在の大切さを再認識したり、関係性を客観視できる場合があります。
ただし、別居が長期化すると夫婦関係の修復がより困難になる可能性もあります。別居の期間や条件について事前に話し合いをし、今後の方向性を決める期限を設定することが大切です。
子どもへの影響を多角的に検討する
離婚が子どもに与える影響を多角的に検討し、子どもの将来と幸せを最優先に考えることが大切です。両親の離婚による心理的影響、生活環境の変化、教育機会への影響、経済的な変化などを総合的に判断します。
関係修復により安定した家庭を維持できる可能性があるなら、子どものためにも努力する価値があります。一方で、両親の不仲が続くことで子どもがストレスを感じている場合は、離婚が子どもにとって良い選択となる場合もあるでしょう。
離婚が避けられない場合を想定して準備しておくこと
離婚を回避する努力をしても関係修復が困難な場合は、現実的な準備を進める必要があります。感情的な混乱の中でも冷静に対処できるよう、法的手続きや生活基盤の確保について事前に検討しておくことが重要です。

弁護士への相談と法的サポートの確保
離婚問題が複雑化する前に、離婚に詳しい弁護士への相談を早めに行うことが重要です。離婚の方法(協議離婚、調停離婚、裁判離婚)や法的権利について正確な情報を得ることができます。
特に慰謝料請求や親権争いが予想される場合は、専門的なサポートが必要になるでしょう。弁護士費用についても事前に確認し、法テラスなどの公的支援制度の利用も検討してください。
 新大塚法律事務所 鈴木成公
新大塚法律事務所 鈴木成公離婚自体ができるかという点はもとより、財産分与、慰謝料、親権、養育費など、離婚の付随する事項は、専門的・技術的に難しい争点が少なくありません。専門家に相談する前の言動によって、その後に弁護士に依頼しても、挽回が難しくなるようなことも少なくありませんので、離婚を決意したら、配偶者に離婚を切り出す前に、弁護士に相談し、注意すべき事項、集めておくべき証拠、控えるべき行動などのアドバイスを受けることが重要です。


親権・養育費・財産分与の条件を整理する
離婚条件について具体的な希望と最低限の条件を整理し、交渉の優先順位を明確にしておくことが必要です。親権については子どもの意思や生活環境を考慮し、養育費は相場を調べて適正な金額を把握しなければなりません。
財産分与では共有財産の範囲と評価額を正確に算出し、住宅ローンや借金などの負債についても整理が求められます。感情論ではなく、現実的で実現可能な条件での交渉が重要になります。
離婚調停や裁判に備えた証拠収集
協議離婚で合意に至らない場合に備え、離婚理由を立証するための証拠を計画的に収集することが大切です。不倫の場合は写真や通信記録、モラハラやDVの場合は録音・録画や診断書、悪意の遺棄の場合は生活費の支払い記録などが有効でしょう。
ただし、証拠収集は法的に適切な方法で行う必要があるため、弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。
ADR(裁判外紛争解決手続き)を検討する
離婚調停以外にも、ADR(裁判外紛争解決手続き)を利用することで、より柔軟で迅速な解決が期待できます。ADRは民間の調停機関や弁護士会が提供する紛争解決サービスで、中立的な第三者が仲裁や調停を行います。
裁判所の調停よりも日程調整がしやすく、専門性の高い調停人による解決支援を受けることが可能です。当事者の合意に基づいた柔軟な解決策を見つけやすいというメリットがあります。
離婚後の住居と生活環境を確保する
離婚成立後の住居について具体的な計画を立て、安定した生活基盤を事前に確保しておくことが重要です。賃貸住宅の場合は契約条件や初期費用を確認し、持ち家の場合は売却や名義変更の手続きを検討する必要があります。
子どもがいる場合は転校の必要性や学校区の問題も考慮しなければなりません。収入に見合った現実的な住居選択と、新生活に必要な資金の準備が求められるでしょう。
弁護士や専門家に相談すべきタイミング


離婚問題では、早めの専門家への相談が重要です。法的な権利や手続きを正しく理解することで、不利な条件での離婚を避けることができます。
相手が調停を申し立てた場合、慰謝料や財産分与で争いが予想される場合、親権や養育費について合意が困難な場合は、弁護士への相談が必要でしょう。不倫やDV、モラハラなどの証拠収集が必要な場合も同様です。
夫婦カウンセリングは早めに受けることで気持ちの整理ができ、今後の方向性を冷静に判断することができます。弁護士とカウンセラーの両方に相談し、法的サポートと精神的サポートを併用することも有効でしょう。
離婚したいと言われた人のためのQ&A
Q1. 離婚したいと言われましたが、相手に新しい恋人がいるかもしれません。どうやって確認すればよいでしょうか?
A. 相手を問い詰めたり、勝手に携帯電話をチェックするのは避けましょう。まずは冷静に離婚理由について率直に聞くことが大切です。確実な証拠が必要な場合は、探偵事務所や弁護士への相談を検討してください。相手のプライバシーを侵害する行為は、逆にあなたが不利になる可能性があります。
Q2. 離婚届に署名してしまいましたが、やはり離婚したくありません。取り消すことはできますか?
A. まだ役所に提出されていなければ取り消し可能です。すぐに相手に連絡し、離婚届の提出を待ってもらいましょう。既に相手が離婚届を持っている場合は、離婚届不受理申出書を役所に提出してください。離婚届が既に受理された場合は、早急に弁護士に相談が必要です。
Q3. 離婚を避けるために別居を提案されましたが、別居すると離婚に不利になりませんか?
A. 別居自体が直ちに離婚に不利になるわけではありません。冷却期間として関係修復につながる場合もあります。ただし、長期化すると「婚姻関係が破綻している」と判断される可能性があるため、期間や条件を明確にし、定期的な話し合いの機会を設けることが重要でしょう。
Q4. 相手の両親が離婚を勧めているようです。義理の両親とも話し合うべきでしょうか?
A. 夫婦の問題に第三者を巻き込むことは、問題をより複雑にする可能性があります。まずは夫婦間での話し合いを優先してください。どうしても必要な場合は相手の同意を得てから行い、感情的にならないよう注意しましょう。夫婦カウンセリングなどの専門的なサポートを受ける方が建設的です。
Q5. 離婚したいと言われてから、相手が生活費を渡してくれなくなりました。どうすればよいですか?
A. 一方的な生活費の停止は「悪意の遺棄」にあたる可能性があります。まずは相手と話し合い、生活費の継続を求めましょう。解決しない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。生活に困っている場合は、早めに弁護士や家庭裁判所に相談してください。
離婚したいと言われたときに後悔しないための最適な対応
離婚話が出たときに慌てるのは当然ですが、その後の具体的な行動が重要になります。いかに冷静に状況を見極め、必要な支援や法的手続きを活用しながら、ベストな結論を導くかがポイントでしょう。
修復を目指すにしても離婚を選択するにしても、事前準備と正しい情報収集が欠かせません。
子どもがいる場合は特に慎重な対応が求められ、長期的な影響を考慮する必要があります。最終的な判断は自分自身が納得できるものであることが大切です。焦らず、周囲の助けや専門家の知識を借りながら、人生の重要な分岐点を乗り越えていきましょう。