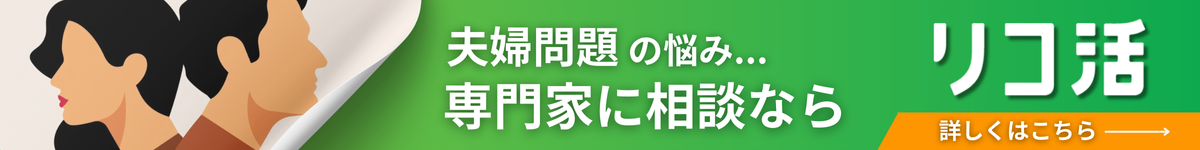子どもは家庭環境の影響を受けやすく、両親が不仲だと人格や性格にも悪影響が及ぶと言われます。両親の仲が悪い家庭で育った子どもの人格や性格に、どのような特徴が現れやすいのかを説明します。両親の仲が悪い家庭で育った子どもが悪影響を受けた場合の対処法も紹介します。

高草木 陽光
これまで9,000人以上のカウンセリングを行い、夫婦問題・家族問題で悩む人を解決に導くお手伝いをする夫婦カウンセラー。
詳しく見る
美容師、育毛カウンセラーを経て、結婚して専業主婦となるが、夫の束縛や価値観の押し付けに違和感を覚え「結婚生活とは何か」ということを深く考え始める。書籍に「なぜ夫は何もしないのか なぜ妻は理由もなく怒るのか」(左右社)、「心が折れそうな夫のためのモラハラ妻解決BOOK」(左右社)、メディア実績にNHK総合「あさイチ」、フジテレビ「ホンマでっか!?TV」、テレビ朝日「羽鳥慎一 モーニュングショー」、「ABEMA Prime」などがある。

家庭環境は、子どもの性格や人格形成に深く関係しています。特に子どもにとって1番身近な両親は、性格の形成に影響を与えやすい存在です。両親の仲が悪い家庭で育った子どもは「両親の喧嘩の原因は自分だ」「自分がいなければ両親は仲良くいられるのかも」と自分を否定し、甘えたい気持ちを我慢する場面が多いため、自己肯定感が低くなりがちだと言われます。
自己肯定感が低いと、失敗を恐れて引っ込み思案となり、新しいことに挑戦する勇気を持てない性格になりがちです。その一方で、承認欲求が強くなりがちで、周囲の評価を必要以上に気にするようになってしまうことがあります。このように、両親の仲が悪い家庭環境は、子どもの将来の人間関係や結婚観にまで影響を及ぼす可能性があるのです。
両親の仲が悪い家庭で育った子どもの特徴
両親の仲が悪い家庭で育った子どもは、安心して甘えられる機会が少なく、甘えたい気持ちを我慢してきたので、上手に感情が出せなくなることがあります。このため、人間関係の構築がうまくいかず、周りと意見が合わなかったり人付き合いが苦手だったりといった特徴がみられるようになります。主な特徴を4つ紹介します。

素直な気持ちを表現するのが苦手
両親の仲が悪い家庭で育った子どもは、素直に自分の気持ちを相手に表現するのが苦手です。そのため、自分の感情や意見を隠して我慢することがあります。これは1番近い存在の両親に素直に甘えられず我慢をしてきたために、自分の素直な気持ちを表現する方法を十分に身に付けられなかったのが理由です。
常に父親や母親の顔色を伺いながら生活してきたため、自分の本当の感じや思いを抑え込む習慣が身についてしまい、大人になっても感情表現が難しくなります。
人間関係に苦労しやすい
両親の仲が悪い家庭で育った子どもは、人間関係に苦労しやすいという特徴があります。両親の不仲や夫婦喧嘩が日常的にあると、子どもは両親にどう接していいのかわからなくなり、やがて、他人とは関わらない方がいいという考えになりがちです。
そうして、子どもの頃から人付き合いを避けてしまうと、友達や周りの人との関係を構築する方法を学ぶ機会を失い、大人になっても人とどう接していいかわからなくなってしまいます。特に親密な人間関係においては、お互いの感情や意見を率直に伝え合うことが難しく、関係が深まりにくいことも特徴です。
恋愛や結婚に対して消極的になる
仲が良く幸せそうな両親を見ている子どもは結婚に憧れを持てますが、両親の仲が悪い家庭で育った子どもは「結婚=幸せ」と考えられず、恋愛や結婚に対して消極的になります。不仲な両親を見て育つと、結婚願望が低下し、自分も同じように不幸になるのではないかという不安を抱えがちです。
また、異性に恋愛的な好意を寄せられても、自己肯定感が低いため「自分なんかが好かれるわけがない」という考えになり回避してしまう傾向にあります。愛情表現の健全なモデルを見る機会が少なかったことも、恋愛関係に消極的になる一因です。
対人関係のトラブルが多くなる
家庭は子どもにとって、本来、安らぎを覚える場所であるはずです。ところが、両親の仲が悪い家庭で育った子どもは、家庭で落ち着くことができません。むしろ、両親の怒鳴り合いや暴力を目にして、常に緊張状態に置かれる子どももいます。
家で心を休ませることができない子どもは、ストレスから情緒不安定になってしまうことがあります。そのため、子どもの頃から学校などで対人トラブルを起こし、大人になっても社会生活に支障を来たす場合があります。DV(家庭内暴力)を目撃して育った場合は、自分自身も感情のコントロールが難しくなり、トラウマとなって長期的に影響することもあります。
アダルトチルドレンとの関連
両親の仲が悪い家庭で育った方の中には、「アダルトチルドレン」(AC)の特徴を持つ人も多くいます。これは、機能不全家族で育ったことによる心理的特性で、大人になっても子ども時代の環境の影響が続いている状態を指します。
アダルトチルドレンは、「大人になった問題を抱えた家庭の子ども」という意味で、年齢的には大人でありながら、心理的・感情的な面では子どもの頃の家庭環境の影響を強く受けている状態を表します。両親の不仲や離婚、DV、依存症など、様々な家庭の問題が背景にあります。

アダルトチルドレンに見られる主な特徴
- 過剰な責任感:家族の問題を自分で何とかしようとする傾向
- 他者の評価に敏感:常に他人の顔色を伺い、自分の価値を外部の評価に求める
- 自己肯定感の低さ:自分を大切にできず、「自分は愛される価値がない」と感じる
- 感情表現の困難:自分の本当の感情を認識できなかったり、表現できなかったりする
- 境界線の問題:自分と他者の境界があいまいで、「No」と言えない、または極端に距離を置く
- 完璧主義:ミスを恐れ、常に完璧を求める
- コントロールへの執着:不安から状況をコントロールしようとする
- 親密な関係への恐れ:親密になることで傷つくことを恐れる
両親の仲が悪い家庭で悪影響を受けた子どもへの対応
両親の仲が悪い家庭で育った子どもが全員、人間関係や恋愛で困難を抱えるというわけではありません。影響をあまり受けずに育つ子どもがいますし、周囲の働きかけや本人の努力で問題を克服する子どももいます。両親の仲が悪い家庭で悪影響を受けた子どもへの対応を紹介します。

自己理解と受容を促す
両親の仲が悪い家庭で育った子どもへの接し方で最も重要なのは、自己理解と受容を促すことです。子どもが自分の感情や行動パターンを理解し、家庭の問題は自分のせいではないと認識できるよう手助けしましょう。トラウマとなっている体験は少しずつ整理していくことが大切です。
幼少期の辛い体験は自己肯定感の低下につながりますが、自分を理解し受け入れることで、徐々に自分を好きになる第一歩となるでしょう。
健全な人間関係構築のスキルを育む
不仲な関係だけでなく、健全な関係性を学べるよう、子ども自身が良い人間関係を築くことが大切です。両親の仲が悪い家庭で育った場合でも、安全で安定した環境の中で、少しずつ信頼関係を築く経験を積ませましょう。
自分と他者との適切な境界線の設定方法を教え、お互いを尊重したコミュニケーション方法を身につけられるよう支援します。特に感情表現や素直な気持ちの伝え方が苦手な子どもには、それらを練習する機会を提供しましょう。
自己肯定感を高める
両親の仲が悪い家庭で育った子どもは、自己肯定感が低い傾向があるため、自分を責めやすい傾向にあります。自分を信用できなければ、他人を信用することは難しいので、まず自分を許して大切にするよう声をかけましょう。
子どもの長所を積極的に認め、小さな成功や成長を一緒に喜ぶ習慣をつけることが大切です。自分にとって心地よい環境や人間関係を選ぶことの重要性を教え、自己選択の機会を増やしましょう。
「自分は愛される価値がある」と実感できる経験を積み重ねることで、徐々に自己肯定感が高まります。常に他人の顔色を伺う子どもには、自分の気持ちを優先することの大切さを伝える機会を作りましょう。
専門家のサポートを活用する
子どもの状況に応じて、カウンセリングや心理療法などの専門的支援を検討することが効果的です。同じような経験を持つ子どもたちのサポートグループへの参加も有効で、体験を共有することで安心感を得られます。
両親の仲が悪い家庭で育った子どものサポートには、専門的な知識やスキルが必要なこともあります、カウンセラーなどの専門家のサポートを受けるのも効果が期待できます。本人だけでカウンセリングを受ける方法もありますが、子どもが未成年の場合は、両親と一緒に受けたほうがいいでしょう。
また、専門家ではなくても、子どもの周りに信頼できる大人がいる場合は、その人に話を聞いてもらう機会を作りましょう。親には話せないことも第三者になら話せることは多々あります。
 夫婦カウンセラー高草木 陽光
夫婦カウンセラー高草木 陽光幼い頃から子どもと適切な距離感で関わり、抱きしめたり話を聞いてあげたりすることで愛着が形成され、「自分は愛されている」「大切にされている」という自己好感が満たされます。
しかし、残念ながら愛情表現が下手な親もいます。そんな親を恨み続けながら生きている人もいますが、現在も悶々としているのなら感情をぶつけてみるのもよし、「そういう人」と諦めるもよし。大丈夫!自分次第で今後の人生を変えることは可能なのです。
両親の仲が悪い家庭で育ち、親の離婚を経験した人の体験談
これまでリコ活では、両親の仲が悪く、親の離婚を経験した方々に取材や調査を行いました。ぜひ、記事をご覧ください。


小1で両親が離婚した井上さんは、母に引き取られ再婚相手と暮らすも後に絶縁。実父とは一度も再会せず、今も会いたいとは思わないそうです。複雑な家族関係を経て、22歳になった現在も母への思いや複雑な家族観を抱えながら生きています。


当時小学6年生だった中沢さんは、母から突然の離婚と東京への引越しを告げられ夜逃げ同然で転居。父の金銭トラブルが原因だが、母の浮気にも気づいていました。都会での苦労を乗り越えながら、母への複雑な思いを抱き続けています。


父親の暴力から母と妹を守るため筋トレに励んだという南さん。その経験をもとに、ひとり親同士が気軽に相談できるアプリ「ペアチル」を開発しました。


10歳で親の離婚を経験した羽津さんは、母の不在と経済的困難に直面し、奨学金を勝手に使われるなどの苦労を経て、母への愛情と裏切りの感情が交錯する中で、自分の存在価値を模索し続けていました。


中学1年で親の離婚を経験した南波さん。父の暴力と母の自傷行為に挟まれた幼少期を経て、進学を諦め就職。現在は画家を目指し、母との関係を保ちながら、自分の人生を切り拓いています。


親の離婚経験者1,005人への調査で、約7割が両親の離婚を肯定的に捉えていることが判明しました。離婚後、親の性格が明るくなったとの声が多い一方、経済的困難や親との関係性に悩むケースも多く、子どもへの影響の大きさが浮き彫りになりました。
両親の仲が悪い家庭環境で育ったからといって、人生が決定づけられるわけではない
両親の仲が悪い家庭で育った経験は確かに辛いものですが、それが必ずしも将来の人生を決定づけるわけではありません。適切なサポートを得ることで、多くの人が過去の経験を乗り越え、健全な人間関係を築いています。
大切なのは、過去の経験を認識しつつも、それに縛られず、自分自身の幸せな人生を選択していくことではないでしょうか。両親の仲の悪い家庭で育ったからといって、幸せになる権利を奪うことはありません。