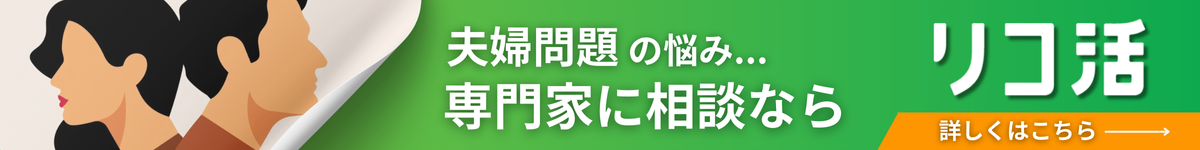離婚における養育費は、子どもの安定した生活と成長を支える重要な経済的支援ですが、場合によっては養育費の免除や減額が認められることもあります。支払い義務があるとはいえ、多くの方が経済事情の変化や予期せぬトラブルに直面することも少なくありません。
本記事では、法律上の支払い義務から免除・減額が認められるケース、また手続き方法まで、養育費に関する幅広い情報を整理して解説します。
佐々木 裕介/チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所(第二東京弁護士会所属)
ホームページ:https://law-childsupport.com/
「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。
詳しく見る
協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。
子連れ離婚をしたシングルマザーのうち、養育費を1回でももらったことがある人は全体の4割ほど。さらにそのうち、6~7割の人が支払い停止や一方的な減額をされています。このような状況の中、離婚後の生活に不安を感じている方も多いと思います。 不安を解消できるよう、丁寧に、安価に、ちゃんとした離婚をするお手伝いをするとともに、離婚後も長期スパンで養育費がきちんともらえる体制作りをサポートします。 離婚後も、安心して暮らしていくお手伝いをしたいと思っています。一緒に幸せをつかみに行きましょう。
【裁判所を使わず協議離婚対応】【養育費保証ご相談可】【法テラス利用可】

養育費を払う義務の基本
まずは養育費の意義や支払い義務の根拠、面会交流との関連など、基礎的なポイントを押さえておきましょう。
養育費とは、離婚後に子どもと同居していない親が子どもの成長に必要な費用を負担するために支払う金銭的義務です。子どもの健全な成長をサポートするための費用であり、どちらの親も子どもとの関係を絶つことなく支える意義があります。したがって、結婚の継続とは関係なく、子どもの権利として保障されるものです。
日本の法律では、民法において親の扶養義務が明示(民法第877条)されており、離婚後も子どもの扶養が続くことが定められています。仮に親権を持たないとしても、子どもが成人し自立するまで、またはそれに準じた年齢や状況を迎えるまで、経済的な負担を分担しなければなりません。これが養育費を払う義務の基本的な根拠となります。
また、面会交流は子どもの精神的安定に寄与すると考えられており、子どもの福祉の観点から尊重されるべき権利です。ただし、面会交流が実現されない場合であっても、養育費の支払い義務は原則として影響を受けません。これは養育費が親の事情よりも、子どもの生活を優先して考えられているためです。
養育費を払わなくてもいいとされやすい8つのケース
養育費は子どもの基本的権利として扱われますが、支払う側がやむを得ない事情を抱えている場合や、子ども側が社会的に自立している場合など、例外的に支払い義務が終わるケースがあります。どの場合であっても、家庭裁判所への申立や当事者間の合意など、正式な手続きを経ることが原則です。
一度取り決めた内容であっても、一定の条件を満たす場合、法的または合意により養育費の免除や打ち切りが認められることがあります。
法律上または実務上で認められやすいとされる典型的なケースをいくつか取り上げます。養育費支払いの打ち切りや免除が適切かどうかを判断する際の参考にしてください。

1. 子どもが成人して自立した場合
子どもが法律上の成人年齢(18歳)に達して社会人になると、社会的・経済的に自立したとみなされる可能性が高まります。この場合、親権者からの監護が終了し、扶養義務が軽減されることがありますが、一般的に高校在学中の18歳の誕生日に扶養義務が終了することはありません。
また、大学在学中や就職準備中などの場合には一般的に養育費の支払義務は継続しますので、一律に成人と同時に養育費の支払い義務が打ち切られることはありません。学費や生活費が必要とされる状況かどうかを総合的に判断することが重要です。家庭裁判所でも、個別の事情を考慮して判断されます。
2. 子どもが就職して経済的に自立した場合
子どもが正規雇用されて安定収入を得るなど、生活を十分に維持できる状態になった場合、養育費の免除や減額、あるいは完全な打ち切りが検討されることがあります。実際には、就職の形態や収入額、生活状況などを基に、具体的にどの程度自立しているかが判断されます。
この場合、養育費の義務者は、相手方との話し合いや家庭裁判所への調停申立てを通じて、支払い義務の見直しを求めることができます。
3. 監護親(権利者)の収入が高い場合
子どもを養育している側の収入が十分に高く、子どもの生活水準に不足がないと判断される場合には、支払い側が養育費を負担しなくても問題ないと認められることがあります。監護親の年収や資産状況によっては、養育費の減額や免除の可能性が生じます。
ただし、裁判所が両親の収入状況や財産を詳細に見極めて総合的に判断するため、単に年収が高いからといって免除が自動的に認められるわけではありません。
4. 子どもが再婚相手と養子縁組をした場合
監護親が再婚し、再婚相手と子どもが法的に養子縁組を行った場合、特に「特別養子縁組」のケースでは、実親としての法的関係が消滅するため、養育費の支払い義務がなくなることがあります。これは子どもが二重に養育費を受け取る必要がないという考えからであり、新たな親が実子と同じように育てる意思と経済的能力があるかどうかが判断材料となります。
ただし、「普通養子縁組」の場合は実親との法的関係が継続するため、扶養義務が完全に消滅するわけではない点に注意が必要です。

5. 子どもが実子でないことが判明した場合
離婚後にDNA鑑定などで子どもが実子ではなかったと分かった場合、法的には血縁関係がないため扶養義務が生じないことがあります。親子関係不存在確認の手続きを経ることで、法的な親子関係が否定されれば、養育費の支払い義務も消滅する可能性があります。
ただし、離婚前に育てていた実績や養育の意思があったかどうかなど、個別の事情により裁判所の判断が変わるため、必ずしも支払い義務が完全に否定されるとは限らず、子どもの福祉を考慮した判断がなされます。
6. 病気やケガなどで支払う側の収入が激減した場合
義務者が支払い能力を大幅に失うほどの病気やケガにより、収入が著しく下がった場合には、養育費の一時的な免除や減額が認められることがあります。このような事情変更は養育費の「変更事由」として考慮されます。
裁判所や相手方への交渉では、医療費や収入の状況など具体的資料を提示し、支払い能力の低下を証明することが必要となります。ただし、回復後には再度支払い義務が発生する可能性もあるため、状況に応じた対応が求められることを留意しておきましょう。

7. 生活保護を受給している場合
生活保護を受給するほど経済的に困窮している場合、支払い能力が厳しく制限されているとみなされ、養育費を負担することが困難だと判断される可能性があります。生活保護制度では最低限の生活を保障するための給付が行われるため、その状況下で養育費まで支払うことは現実的に難しいとされることがあります。
ただし、この場合も単に受給しているだけではなく、収入や資産状況など支払能力の有無を厳密に確認されるため、最終的な判断はケースごとに異なります。
8.相手方と支払免除に合意している場合
離婚時の取り決めにおいて、財産分与を多めに受け渡す、あるいは面会交流の条件を広く認めるなどの代償として、相手方が「養育費を請求しない」という合意をすることがあります。公正証書などの債務名義を作成する際にもこうした条件が含まれることがあります。
しかし、養育費は本来子どもの権利でもあるため、その合意が子どもの利益を著しく損なうと判断されれば、後になって家庭裁判所で無効とされる場合もあるため注意が必要です。
一度取り決めた養育費を減額・免除する方法
離婚時に公正証書や調停で定められた養育費であっても、時間が経つにつれて経済状況や家族構成が変化することは珍しくありません。こうした事情変更が大きい場合には、離婚協議や裁判で一度決まった養育費でも、双方の事情が変わった場合には減額や免除が可能です。
ただし、当初の取り決めを無条件で変更することは認められず、あくまで正当な理由が必要となり、理由を裏付ける客観的な証拠や収入証明を準備しておくことで、スムーズに話し合いが進む可能性が高まります。
裁判所を通さなくても話し合いで合意する方法もあれば、相手が合意しない場合には減額調停を行うなど、法的手続きをするパターンもあります。

話し合いや合意での免除
まずは当事者同士の話し合いによる解決を試みるのが一般的です。支払い状況や子どもの年齢、経済状況などを示す書類をもとに相手方と協議を行い、減額や免除の合意が得られれば新たに書面化しておくと後々のトラブルを回避できます。
減額調停や審判で認められるケース
話し合いが決裂した場合は、家庭裁判所に「養育費減額調停」や審判を申立てる手段があります。ここで経済状況の激変や子どもの自立など、事情の変化を立証することで、裁判所が減額または免除を認める場合があります。
裁判手続きにおける注意点
裁判所に申立を行う際には、確定申告書や源泉徴収票などの収入証明、医療費や生活保護受給証明など、客観的な資料が求められます。また、手続きには時間と費用がかかるため、できるだけ話し合いで妥協点を見いだすほうがスムーズな場合も少なくありません。
弁護士や専門家への相談の重要性
養育費の減額や免除は法律的にも複雑な要素を含むため、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談することが望ましいです。書類作成や手続きの進め方だけでなく、相手方との交渉戦略なども適切にアドバイスしてもらえるため、結果的にスムーズな解決に近づく可能性が高くなります。
 チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所 佐々木 裕介
チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所 佐々木 裕介特に養育費の減額手続は、当初の合意から「事情の変更」があったことを主張する必要があります。弁護士に相談するメリットは、何が事情の変更に該当するのか、裁判所がどのように評価するのか、正当な変更理由になるかなどを判断した上で、証拠の整理や主張の組み立てが可能になるということです。




免除や減額が認められないケース
支払い義務を何とかして回避したいと考える人もいますが、理由次第では裁判所が容認しないこともあります。法律が定める扶養義務は、子どもの最善の利益を守るという強い原則によって支えられているため、少しの事情変更や親同士の対立では支払い義務が消えない場合が多いためです。
養育費支払免除や減額が認められないケースに当てはまる人でも、一方的にあきらめるのではなく、できる限りの手続きを踏んだり、専門家に相談したりすることが大切です。
面会交流を拒否された
相手方が子どもとの面会交流を認めないからといって、養育費の支払い義務が免除されるわけではありません。
裁判所は養育費を「子どもの健全な成長に必要な生活費」、面会交流を「子どもの精神的安定と親子関係維持のための権利」と別個に捉えており、基本的には別問題として扱います。監護親による面会交流の拒否は不当な行為ではありますが、それによって子どもの生活費までもが減額される理由にはならないというのが家庭裁判所の一貫した立場です。
このような場合は、養育費の支払いを継続しながら、別途調停や審判で面会交流の実現を求めるのが適切な対応となります。


借金や自己破産を理由にする
自己破産をしても養育費の債務は免責されにくく、借金返済が苦しいという理由だけで免除・減額は認められないのが通例です。
裁判所は子どもの権利を最優先に考えるため、親の経済事情でも正当な理由がなければ支払い義務は継続します。養育費は子どもの生活保持義務から生じる特別な債務として扱われるため、破産法上も「非免責債権」とされています。
義務者の生活状況が一時的に悪化した場合でも、裁判所は子どもの利益を守る観点から、借金の内容や発生原因、返済計画などを詳細に検討し、可能な限り養育費の確保を図る判断がなされることが多いでしょう。
一方的に収入を減らした
養育費の支払いを逃れるために退職する、あるいは自営業の収入を低く申告するといった意図的な行為は減額・免除の対象とはなりません。
特に、養育費の支払いを避けるための意図的な転職や職業選択の変更は、「義務の不当回避」と見なされる傾向があります。裁判所は、過去の収入実績や本人の能力、資格などから客観的に見て得られるはずの「潜在的稼働能力」を基準に判断することもあり、正当な理由がないと判断した場合は免除どころか義務者に不利な判断を下す可能性があるため注意が必要です。
養育費を支払わないリスクとは?
養育費の不払いは子どもの生活に直接影響を及ぼすため、強い社会的・法的制裁の対象となる可能性があります。相手からの請求を無視し続けると、最終的には強制執行による財産差し押さえなどに発展することもあるでしょう。
養育費の不払いに関する具体的なリスクについて確認しておきましょう。


遅延損害金や滞納分の一括請求
養育費の不払いが続くと、未払い分を一度に請求されたり、支払期限の遅れに対して遅延損害金(延滞利息)が課されたりする場合があります。民法上、養育費債権には年3%の法定利息が発生するため、長期間滞納すると負担が大きくなります。
相手方が公正証書や調停調書、審判書などの債務名義を手元に持っている場合には、請求の強制力が高くなり、裁判所を通じた法的手続きもスムーズに進められるため、支払い義務者としては不利な立場に置かれます。滞納が始まったら早期に相手方と連絡を取り、支払い計画の再交渉や減額の相談をするなど、すみやかに適切な対処をすることが大切です。
強制執行や財産差し押さえの可能性
養育費の滞納が続くと、権利者(監護親)が裁判所の許可を得て強制執行を申し立てる可能性があります。強制執行が認められると、給与や賞与などの定期的な収入、預貯金口座の残高、場合によっては自宅や車などの財産が差し押さえの対象となり得ます。
特に直接強制となる給与の差し押さえは、勤務先にも滞納事実が知られることになり、社会的信用にも影響します。一度差し押さえが実行されると、手取り収入の大幅な減少など生活が大きく制限されるほか、差し押さえ解除のための手続きも必要になるため、状況が悪化する前に履行勧告などの制度を利用するなど、早期の解決策を講じることが重要です。
ネガティブな印象を与える
養育費の滞納が直接、親権変更や面会交流の権利を失う法的な原因になるわけではありませんが、養育費の支払い状況は親としての責任感や子どもへの愛情を示す重要な指標と見なされるため、将来的に親権変更や面会交流の条件を交渉する際に不利に働くことが多いのが現実です。
特に、子どもが成長するにつれて「お金を払ってくれない親」というネガティブな印象が子どもの心に残り、親子関係の修復にもマイナスの影響が及ぶ恐れがあります。長期的な親子関係を維持するためにも、可能な限り支払い義務を果たすことが望ましいでしょう。
養育費の減額交渉の進め方
養育費を支払う側として経済的な理由がある場合には、感情的にならずに適切な手段をとることでトラブルを最小限に抑えられます。実際に不払いが発生した場合や、支払額の交渉を行う際の進め方を紹介します。


減額交渉の適切な進め方
支払い能力に変化が生じた場合は、まず相手方に対して直接または弁護士を通じて事情を説明し、減額交渉を申し入れることが第一歩です。
この際、単に「支払いが厳しい」といった抽象的な理由ではなく、収入減少の証明書類(給与明細や離職票など)や新たな家計状況を具体的に示し、誠意をもって交渉することが重要です。話し合いで合意できれば、新たな公正証書を作成して条件を更新することで、後のトラブルを防止できます。
家庭裁判所での調停申立ての流れ
直接交渉で合意に至らない場合は、家庭裁判所での養育費減額調停を申し立てることが考えられます。調停では第三者である調停委員が間に入ることで冷静な話し合いが可能になり、双方が納得できる解決策を探ります。
申立ての際は、収入の変化や新たな家族を扶養する義務が生じたことなど、減額を求める具体的な理由と証拠を準備しておくことが大切です。調停で合意に至らない場合は審判に移行しますが、適切な証拠があれば裁判官による客観的な判断が期待できるでしょう。
養育費の支払いが困難になった場合の対応
一時的に支払いが困難になった場合は、できるだけ早く相手方に状況を伝え、分割払いや支払い猶予など代替案を提案することが重要です。突然の支払い停止は相手方の不信感を招き、法的手続きへと発展するリスクが高まります。
どうしても連絡が取りづらい場合は、内容証明郵便で現在の状況と今後の支払い見通しを伝えることも一つの方法です。誠意ある対応を示すことで、相手方も柔軟な対応をしてくれる可能性が高まります。
相手方から強制執行の申立てがあった場合の対応
相手方から履行勧告や強制執行の申立てがされた場合でも、慌てずに対応することが大切です。まず、家庭裁判所からの履行勧告状が届いたら、指定された日時に出向いて状況を説明し、可能な支払い条件を提案しましょう。
強制執行が始まると、給与や預金の差し押さえによって生活が一層厳しくなる恐れがあるため、早期解決が望ましいでしょう。法的手続きが進んでいる場合は、弁護士に相談して適切な対応を検討することをおすすめします。
専門家への相談
養育費の支払いや減額交渉に関する悩みは、一人で抱え込まずに専門家に相談することが解決への近道です。弁護士は養育費問題に関する無料相談窓口を設けていることも多く、初期段階でのアドバイスを受けられます。
特に事情が複雑な場合や、相手方が強硬な態度を取っている場合は、早めに弁護士のサポートを受けることで、自分の権利を守りながら適切な解決策を見つけることができるでしょう。


離婚後の養育費についてのQ&A
離婚や養育費の支払いをめぐっては、多くの人が似たような質問や不安を抱えます。一度知っておくことで、いざというときに焦らずに対処できる可能性が高まるでしょう。養育費をめぐる疑問をQ&A形式でまとめました。


Q1. 相場より高い養育費は払わなくてもいい?
裁判所の算定表を大きく超える額が定められたとしても、当事者間の合意や子どもの具体的な教育・生活費用によっては正当化される場合があります。一方的に「高すぎる」と感じても、算定表との比較や実際の家計状況を踏まえた交渉が必要です。
Q2. 面会交流を拒否されているのに支払う必要はある?
面会の拒否は別の法的問題であり、養育費の支払い義務を消滅させる理由にはなりません。もし面会交流が不当に妨害されていると感じる場合は、面会交流調停など別の手続きを活用して対処する必要があります。
Q3. 未婚の場合でも養育費は支払わなければならない?
婚姻関係の有無を問わず、親子関係が認知されていれば扶養義務は生じます。つまり、未婚であっても父親として認知している場合は、法律上の扶養義務を果たす必要があります。
Q4. 「払わない」と口約束したら免除になる?
口頭だけの合意はトラブルの原因になりやすく、法的に有効とは限りません。必ず正式な書面に残し、公正証書や調停調書などの形で証拠化しておくことをおすすめします。
Q5. 自己破産したら養育費の支払い義務は消える?
自己破産しても養育費債務は優先的に扱われるため、一般的な借金と異なり免責されません。子どもの権利保護という観点から、経済的に厳しい状況でも支払義務は基本的に残ります。
Q6. 子どもから直接請求されることはある?
子どもが成年に達した後、自らの権利として直接請求するケースも考えられます。その場合は裁判所で手続きを踏む必要がありますが、子どもが強い意志を持って請求を行う場合もあるでしょう。
Q7. 再婚後に離縁した場合も免除は続く?
一度は再婚相手と養子縁組をして養育費の免除が認められたとしても、離縁によって再び実親が扶養義務を負う可能性があります。そのため、再婚で養子縁組が成立しても、離縁の可能性を考慮しておく必要はあります。
養育費を払わなくてよいか迷う場合は専門家へ相談を
離婚後の養育費は、親同士の関係がどうであれ、子どもの生活を守るために欠かせない支援です。経済的な理由によっては支払いの見直しや免除が検討されることがありますが、裁判所は子どもの福祉を優先した判断を下します。
養育費問題で困ったときは、相手方との話し合いだけで解決できない場合でも、家庭裁判所の調停や審判、専門家のサポートなど多くの方法があります。感情的な対立だけでなく、適切な手続きを踏むことが最終的には自分の負担を減らす手段にもなるでしょう。