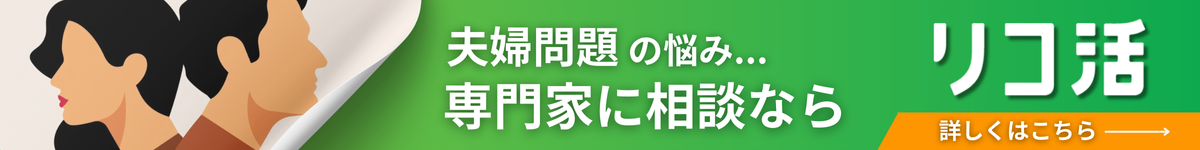離婚後の子どもの生活を支えるために必要な養育費ですが、実際にいつまで支払うべきなのでしょうか。ここでは支払い期間の一般的な考え方や、特別な事情がある場合の延長、再婚時の扱いなど、押さえておきたいポイントを解説していきます。
佐々木 裕介/チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所(第二東京弁護士会所属)
ホームページ:https://law-childsupport.com/
「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。
詳しく見る
協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。
子連れ離婚をしたシングルマザーのうち、養育費を1回でももらったことがある人は全体の4割ほど。さらにそのうち、6~7割の人が支払い停止や一方的な減額をされています。このような状況の中、離婚後の生活に不安を感じている方も多いと思います。 不安を解消できるよう、丁寧に、安価に、ちゃんとした離婚をするお手伝いをするとともに、離婚後も長期スパンで養育費がきちんともらえる体制作りをサポートします。 離婚後も、安心して暮らしていくお手伝いをしたいと思っています。一緒に幸せをつかみに行きましょう。
【裁判所を使わず協議離婚対応】【養育費保証ご相談可】【法テラス利用可】

養育費とは?基本的な定義と支払い義務
まずは養育費の基本的な定義や支払い義務について確認しましょう。養育費とは、子どもの健全な成長を支えるために必要となる生活費や教育費などを、離れて暮らす親が負担するお金のことです。両親が離婚し親権が一方の親に移る場合でも、子どもの幸せを守る責任は双方が担っています。
法律上、親には「生活保持義務」があり、子どもが自力で生計を立てられない間は生活を保障する必要があります。この義務を怠ると、子どもの生活に深刻な影響を与えるだけでなく、後のトラブルにつながることも少なくありません。
適切な養育費の金額や支払い方法は、協議や調停などで定められますが、協議離婚の場合、後々の未払いリスクを減らすためにも、法的に効力のある公正証書を作成することが一般的です。
生活保持義務と扶養義務の違い
「生活保持義務」とは、親が子どもに対して自分と同水準の生活を保障する責任を指します。一方、「扶養義務」は、生活できない状態にある親族を経済的に助ける広い意味合いを含むものです。
養育費においては主に生活保持義務が適用され、親が自分の生活費を削ってでも子どもの生活を維持する必要があると解釈されます。これは、子どもの将来を守るためにも重要な考え方です。
離婚後でも親であることに変わりはありませんから、子どもが十分な生活を送れるよう、両者が責任を分担していくことが求められます。
養育費はいつまで?支払い開始と終了のタイミング
養育費の支払いが始まる時期や、どのようなタイミングで終了するのかを押さえておきましょう。

【養育費支払い開始時期】離婚・別居のタイミング
養育費の支払いは、夫婦が離婚した時点から発生します。他方で、婚姻中であっても別居期間中の夫婦間での支払いは必要で、これを法的に婚姻費用の支払いといいます。別居時点で婚姻費用に関する協議が行われていれば、その合意内容に沿って別居時点から婚姻費用の支払いを開始することもあります。
離婚調停などを前提にしている場合は、離婚調停や裁判所の離婚判決が下りた後に養育費の支払いを正式に始める場合もあれば、離婚調停中に婚姻費用の仮払いを開始することも一般的です。
【養育費終了時期】基本は高校卒業または大学卒業まで
養育費は「未成年の子どもが経済的に自立するまで」という考え方が基本で、実務上は、子どもが高校卒業までまたは大学卒業までとの合意をするケースが多いですが、20歳を目安に支払われるケースもあります。
実際には法律で明確に定められているわけではなく、当事者同士の合意や家庭裁判所の判断が入りますが、子どもが就職して社会人として独立した時点で終了とする例が多いのが現状です。
養育費の支払い期間は家庭の事情や考え方に左右されるため、後から意見の食い違いが生じないよう、事前にしっかりと話し合っておくことが望ましいでしょう。
成年年齢引き下げの影響は?
2022年の民法改正により成年年齢が20歳から18歳に変更されましたが、養育費が18歳で打ち切られるかというと必ずしもそうではありません。あくまで子どもの経済的自立が焦点となります。
子どもが高校を卒業後すぐに定職に就き、自立した場合には18歳の後、最初に到来する3月(高校を卒業する月)で終了とするケースもあるかもしれません。一方で、大学進学を希望し、学費負担が必要な場合には20歳以上になっても継続する可能性があります。
結局のところ成年年齢の引き下げが与える影響は限定的といえ、個別事情によって支払い期間が変わるという点を留意しておきましょう。

進学・留年により学生期間が長期化するケース
留年や大学院への進学などにより、当初想定していた以上に在学期間が延びるケースも考えられます。こうした場面で支払いを継続すべきかどうかは、家庭の状況や子どもの進路に対する考え方によって判断が異なります。
特に留年の場合は、父母それぞれの責任分担をどのように考えるかが問題になりがちです。子どもの学業努力不足が理由なのか、それとも家庭の都合があったのかを総合的に判断します。
計画外の進学や延長が生じる可能性も踏まえ、定期的に協議や話し合いの場を設けることが、長い目で見て円満な解決につながるでしょう。
子どもに障害がある場合

子どもが身体的・知的・精神的な障害を持っている場合、就職や自立が難しく、通常より長く養育費の負担期間を確保する必要が生じることがあります。障害の程度が重いほど、自立が困難であると見なされ、養育費の継続が必要になる可能性が高まるでしょう。
その際は、医療費や介護費用なども考慮したうえで、公的支援制度と併用しながら、どの程度の費用を実際に負担すべきかを検討し、当事者間で話し合いが必要になります。
養育費の額に上乗せして支払うのか、あるいは一時金として別途援助するのかなど具体的に話し合うほか、単に期間を延ばすだけでなく、負担額そのものの見直しや増額を検討する場合もあるでしょう。
先の見通しを立てるのが難しいケースも少なくありませんが、定期的に状況を確認し、必要に応じて協議・調停で見直しを行うことが重要です。
結婚・就職により子どもが早期に自立した場合はどうなる?

子どもが早い段階で自立した場合、支払い期間が短縮される場合があります。
子どもが高校卒業後すぐに就職し、自力で生活を営めるようになった場合、養育費の必要性がなくなることがあるためです。ただし、判断基準としては給与水準や経済的な安定度がポイントとなります。
たとえばアルバイトやフリーターなどの非正規雇用で生活が不安定な状態であれば、「未成熟子」とされ、自立とは見なされない可能性もあるため、養育費をもらえる可能性があるでしょう。
結婚した場合は原則として経済的な自立が前提となるため、養育費の打ち切りが認められるケースが多いです。ただし、妊娠や出産など特別な事情がある場合には話し合いが必要となることもあります。また、結婚相手の経済事情や夫婦の稼ぎなど、個別事情によって結論は変わってきます。
再婚で養育費はどう変わる?
養育費がいつまでもらえるか気になる方の中には、親が再婚すると、養育費の支払い義務が気になる方もいるかもしれません。養育費を受け取る側と支払う側、それぞれのケースについて解説します。

養育費を受け取る(債権者)側が再婚した場合
養育費を受け取る側の親が再婚し、新たな配偶者の収入で子どもの生活が十分にまかなえる場合、支払い側としては「子どもの生活が担保されている」として減額を求めることができるかもしれません。
ただし、再婚相手が子どもを正式に養子縁組していない場合は、法的な扶養義務が働きにくいこともあり、一概に減額が認められるわけではありません。現状の収入や子どもの状態を踏まえた実際的な判断が求められるため、減額を希望する場合は書類や証拠を揃えたうえで調停などを利用することが多いです。
養育費を支払う側(債務者)が再婚した場合
養育費を支払う側が再婚した場合、新たな配偶者や子どもを扶養しなければならないことで、経済面で余裕がなくなることが考えられ、こうした状況変化にともない、養育費の減額を家庭裁判所に申し立てることが可能となります。
ただし、再婚相手の収入に頼る余地があると判断されれば、必ずしも減額が認められるわけではありません。調停では、公平な負担になるよう、再婚後の生活費を含む家計状況を細かく検討されます。
養子縁組で養育費はどうなる?
親が再婚相手と子どもを養子縁組した場合、新たに法律上の親子関係が成立します。これにより、実親は扶養義務を免除される可能性があります。
ただし、養子縁組の時期や養育費の取り決めの内容によっては、すぐに免除されないケースもあるため、個別の事情をよく確認する必要があります。養子縁組を検討する際には、再婚相手・実親・子ども、それぞれの意向を尊重しながら、法的な影響を踏まえて慎重に決定する必要があります。

養育費減額・増額の手続き

手続きの流れ
養育費の変更手続きはまず当事者間の話し合いから始めるのが理想的です。お互いに納得できる金額で合意できれば、その内容を公正証書として残しておくことで法的効力を持たせることができます。この公正証書には強制執行認諾文言を入れておくことで、万が一支払いがなされない場合の対策にもなります。
話し合いでの合意が難しい場合は、家庭裁判所に「養育費変更調停」を申し立てることになります。調停員が間に入り、養育費の減額・増額についての話し合いを進めます。
調停でも合意に至らなければ審判手続きに移行します。審判では裁判官が双方の提出した証拠に基づいて判断し、養育費の金額を決定します。審判結果に不服がある場合は、審判書の正本を受け取ってから2週間以内に即時抗告することが可能です。
過去の未払い養育費を請求する場合は、状況によって地方裁判所での強制執行手続きとなることもあります。この場合は弁護士に依頼することが一般的です。
弁護士への相談がおすすめ
養育費変更の手続きは法律的な専門知識が必要なため、早い段階で弁護士に相談することがおすすめです。弁護士は適切な証拠収集の方法や申立書の作成、交渉戦略などをアドバイスできます。特に相手方が応じず争いが予想される場合は、専門家のサポートがあると心強いでしょう。
 チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所 佐々木 裕介
チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所 佐々木 裕介特に養育費変更手続は、当初の合意から「事情の変更」があったことを主張する必要があります。弁護士に相談するメリットは、何が事情の変更に該当するのか、裁判所がどのように評価するのか、正当な変更理由になるかなどを判断した上で、証拠の整理や主張の組み立てが可能になるということです。


公正証書の作成・強制執行のメリット
養育費の支払いは長期間続くため、将来的に未払いとなるリスクは否定できません。このリスクに備えるために、養育費の取り決めは公正証書として残しておくことが非常に重要です。
公正証書は公証人役場で作成される法的効力を持つ文書です。特に「強制執行認諾文言」を入れておくことで、支払いが滞った場合に裁判所での訴訟手続きを経ずに、直ちに差し押さえなどの強制執行手続きに移行することができ、時間と費用を大幅に節約できます。
また、公正証書は単なる強制力だけでなく、心理的な抑止効果も期待できます。支払い義務者に法的責任の重さを認識させ、支払いを継続する動機づけとなります。子どもの生活を安定させるための重要な保険として、離婚時には必ず公正証書の作成を検討すべきでしょう。
公正証書を作成していなかったら?
養育費の取り決めを公正証書にしていない場合、支払いが滞ると回収手続きが複雑になります。私的な合意書や口頭の約束だけでは、すぐに強制執行することができません。未払いが発生した場合、まず家庭裁判所で調停を申し立て、それでも解決しなければ審判へと進む必要があります。
この法的手続きには通常数か月かかり、その間の生活費が不足する可能性があります。また「そのような金額で合意した覚えはない」などと支払い義務者が主張すれば、取り決め内容の立証自体が困難になることも少なくありませんし、原則として調停手続中の双方の収入に鑑みて養育費算定表に基づいた金額決定手続きになります。
調停や審判で養育費が認められれば、調停調書や審判書に基づいて強制執行が可能になります。しかし、これらの手続きには申立費用や弁護士費用、何度も裁判所へ出向く時間的負担が生じます。ただし、公正証書がない状態でも諦めず、法的手続きを進めることが大切です。
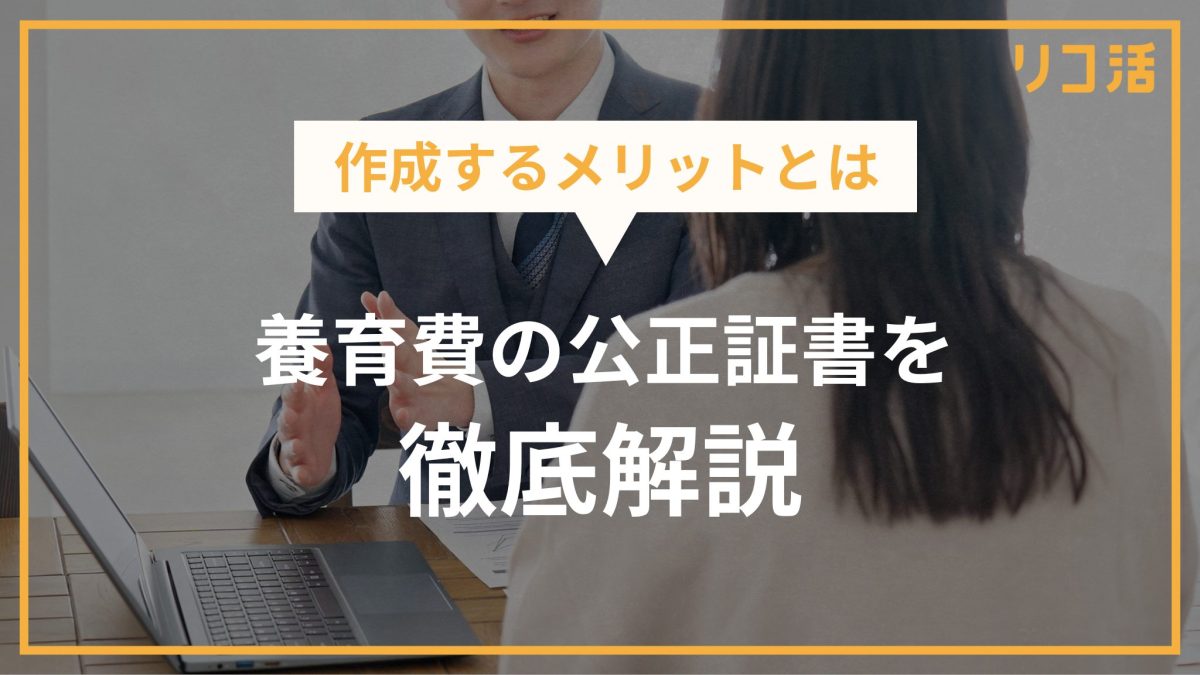
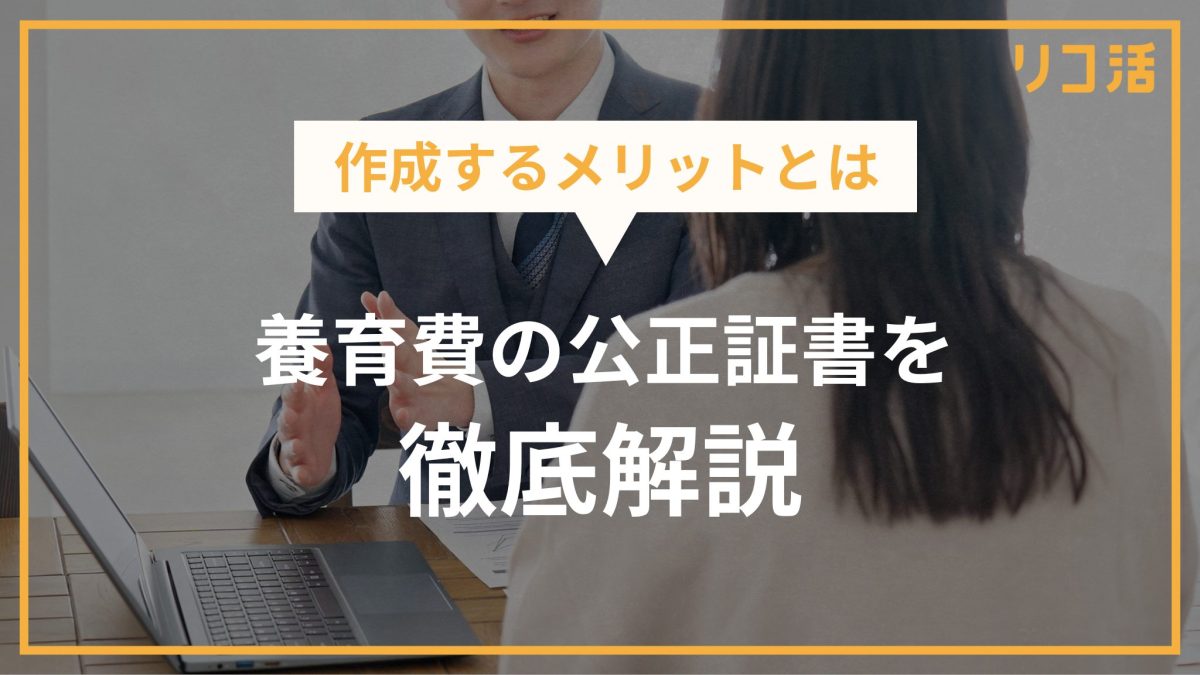
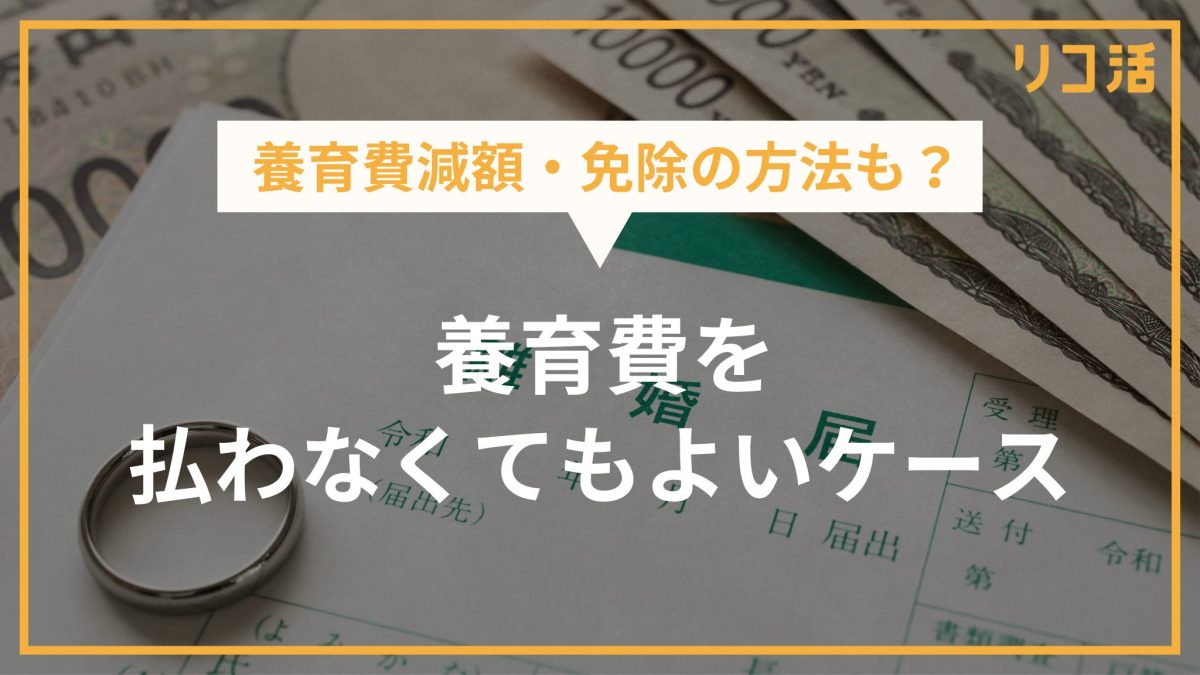
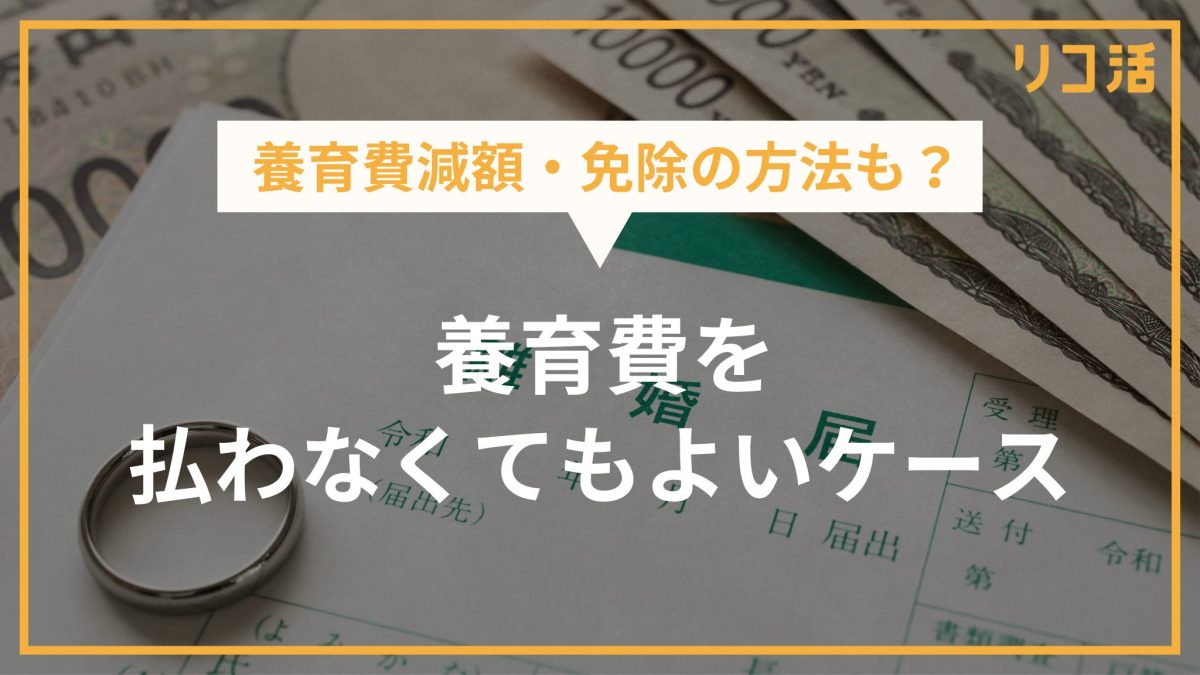
未払い養育費の請求期限はいつまで?
養育費が支払われないケースは少なくありません。未払い分をいつまで請求できるのか、どのような手続きが必要なのかを理解しておきましょう。


養育費請求の時効期限
養育費の請求権には時効があります。時効期間は以下の通りです。
- 通常の養育費:5年間
- 調停調書や審判で定められた養育費:10年間
時効の起算点は「各支払期日の翌日」となります。例えば、毎月25日が支払日なら、26日から時効が進行します。つまり、各月の支払いごとに別々に時効が進行していくことになります。
時効を中断させる方法
養育費の未払いが続いている場合、以下の手順で時効を中断させることもできます。
- 内容証明郵便で請求する(債務の承認を得る)
- 調停を申し立てる
- 支払督促や訴訟を提起する
これらの法的手続きにより、時効の進行を止めることができます。請求の意思表示を相手に示し、記録に残すことが大切です。
未払い養育費の請求手続き
- 証拠の収集・整理
養育費の取り決め文書(公正証書、調停調書など)と未払い記録(支払記録、振込履歴、メールやLINEのやり取りなど)を整理します。
- 当事者間の交渉
まずは相手に直接請求します。内容証明郵便を使えば、請求の記録が残ります。
- 法的手続きの検討
交渉で解決しない場合、以下の選択肢があります。
- 家庭裁判所での調停(養育費請求調停)
- 公正証書があれば強制執行手続き
- 少額訴訟や通常訴訟
- 弁護士への相談
未払い額が高額である場合や相手が長期間支払いを拒否している場合、相手の所在や財産状況が不明な場合は弁護士に相談することがおすすめです。弁護士が法的な専門知識に基づくアドバイスや調停・訴訟の代理人となることで心理的負担を軽減してくれます。
未払い養育費の請求は子どもの権利を守るための重要な手続きです。長期間放置せず、必要に応じて専門家のサポートを受けながら進めることが大切です。


請求時の注意点
未払いが長期間続いている場合は、一括での支払いが難しいケースがあるため、分割払いでの合意も視野に入れ、現実的な解決策を探ることが大切です。
また、相手の資力状況によっては、強制執行しても十分な回収ができない可能性もあります。相手の財産状況を事前に調査できると効果的でしょう。
何より大切なのは、記録をきちんと残し、早めに対応することです。未払いが発生したら、すぐに適切な対応を取りましょう。状況に応じた方法で、子どもに必要な養育費を確保することが重要です。
養育費をいつまでもらえるか公正証書を残し、適切な対応を
養育費の支払い期間を理解し、トラブルを避けるためにも適切な手続きを踏むことが大切です。
養育費は子どもの生活を支える非常に重要な制度です。成年年齢の引き下げや大学進学、再婚などによって支払い期間や金額が変化する可能性がありますが、それぞれの事情に合った対応をすることが大切と言えます。
支払いが困難になった場合や子どもの医療費が増えた場合など、後からでも協議や調停を通じて条件を変更することは可能です。相手への配慮や合意形成が円滑に進むよう、専門家を交えるのも一案でしょう。
未払いが生じた場合には時効や強制執行の問題が絡んでくるため、早めの対応が重要です。お互いの義務と権利を尊重し、子どもの最善の利益を考えながら話し合いを進めてください。