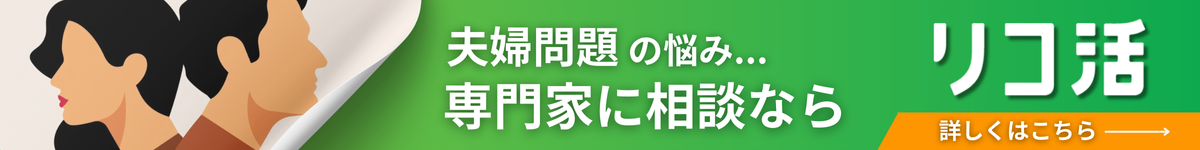熟年離婚は、長年連れ添ってきた夫婦が高齢期に差し掛かる頃に離婚を決断するもので、近年増加傾向にあります。特に妻が離婚を切り出すケースも少なくありません。長い年月を一緒に過ごしながらも、思いやりや関心のすれ違いが積み重なっていくと、熟年離婚へとつながる可能性が高まります。
本記事では、熟年離婚を検討する妻の側から、基礎知識や心構え、具体的なステップについて整理します。後悔のない決断をするためには、法律的視点だけでなく心の面での整理も大切です。本記事を通じて、ご自身に合った判断材料を集め、納得のいく結論を導くための参考になれば幸いです。
本記事でわかること
・熟年離婚の増加背景と妻が離婚を決断する主な理由
・財産分与・年金分割で妻が損しないための具体的な知識
・慰謝料請求の条件と現実的な相場感
・離婚前に準備すべき重要なポイントと必要な証拠
・子どもへの影響を最小化する配慮事項
離婚・相続・交通事故など、人生の転機に寄り添う法的サポートを提供。依頼者との信頼関係を重視し、専門的な情報をわかりやすく伝える姿勢に定評がある。
詳しく見る
子どもの権利委員会に所属し、離婚に伴う子どもの問題にも積極的に取り組む。敷居の低い相談スタイルと温かな人柄で、地域に根ざした弁護活動を続けている。

熟年離婚とは?その背景と増加の理由
まずは熟年離婚の定義や、なぜ近年増えているのかについて整理しましょう。
熟年離婚の定義
夫婦の年齢に関わらず、熟年離婚とは、一般的に結婚してから20年以上が経過した夫婦が離婚を選択することを指します。
厚生労働省の人口動態統計によると、同居期間20年以上の夫婦の離婚件数は、昭和60年は約2万件でしたが、令和元年には約4万件と1.97倍に増加しており、その増加は顕著です。
2022年の同居20年以上の離婚は約3万9千件に上り、全体(同居期間不詳を除く)の23.5%と過去最高になり、4組に1組が熟年夫婦となっています。これらの統計からも、熟年離婚が決して珍しいケースではないことがわかります。
出典:
– 厚生労働省 [人口動態統計月報年計(概数)の概況](https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai19/index.html)」令和元年・令和4年
– 厚生労働省 [令和4年度 離婚に関する統計の概況](https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/rikon22/index.html)
– 神戸新聞 [熟年離婚件数が高止まり 同居20年以上の割合、過去最高に](https://www.kobe-np.co.jp/news/richa/lifedesign/202502/0018652309.shtml)」2025年2月19日
熟年離婚が近年増えている社会的背景
熟年離婚が増加している背景には、複数の社会的要因が影響しています。
高齢化の影響
以前は夫婦のどちらかが早期に亡くなるケースが多く、熟年夫婦の母数が今よりも少なかったのですが、高齢化によって夫婦が共に高齢期を迎える機会が増え、離婚を検討する期間も長くなりました。
かつては妻が夫に嫌気が差しても耐えていたケースでも、お互いに長生きして共に過ごす時間が長いことを考えると我慢できず離婚に踏み切るケースもあるようです。
女性の社会進出と経済的自立
専業主婦として夫に経済的に依存していた時代から変化し、自分で収入を得られる女性が増えました。90年代以降、女性の社会進出が進み経済力が向上したことも重要な要因でしょう。これにより離婚への心理的・経済的ハードルが大幅に下がったのです。
年金分割制度の導入
2007年4月に始まった年金分割制度も熟年離婚を後押ししています。中高年女性にとって離婚後の老後生活費は大きな不安要素でしたが、年金分割により一定の年金を確保できるようになり、安心して離婚を選択する女性が増加しました。
出典:
ー法務省「年金分割」
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00019.html#:~:text=%EF%BC%88%EF%BC%A1%EF%BC%89-,%E5%B9%B4%E9%87%91%E5%88%86%E5%89%B2%E3%81%AF%EF%BC%8C%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AB%EF%BC%8C%E3%81%8A%E4%BA%8C%E4%BA%BA,%E4%BA%BA%E3%81%A7%E5%88%86%E5%89%B2%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)
価値観の変化と多様な生き方の受容
子どもが独立し夫婦二人だけになったとき、「一緒にいる意味があるのだろうか?」という問いが生じやすくなります。そんな中で、日本の家族観・夫婦観が「一度結婚したら生涯添い遂げるべき」というものから「自分らしく生きる」価値観へと移行していることも熟年離婚増加の背景として挙げられるでしょう。
【体験談あり】妻が熟年離婚を望む主な原因
妻側から離婚を切り出すケースでは、夫の定年退職や生活リズムの変化が転機となることが多く見られます。長年にわたって家事や育児、さらには介護などの負担を担ってきた妻が、蓄積されたストレスや不満を抱えながら、人生の節目で「このまま同じ生活を続けたくない」という気持ちを抱くようになるようです。
特に結婚生活が長いほど、夫婦間での思いやりや配慮が薄れがちになり、関係の悪化に気づかないまま時間が経過してしまうケースも少なくありません。

夫への不満・価値観のずれ
長年連れ添っていると、「言葉にしなくても分かり合える」と思いがちですが、実際には小さな不満ほど伝わりづらいものです。妻が抱える「夫婦間の家事負担のバランス」や「夫の言動に対する思いやりの欠如」は、時間とともに大きくなり、やがて決定的な亀裂を生むこともあります。こうした価値観のズレは意識的に話し合わない限り、夫婦関係を静かに蝕んでいきます。

夫はいつの間にか「お疲れさま」も「ありがとう」も言わなくなりました。私が家事をするのが当たり前だと思っているようで、「手伝おうか?」の一言もありません。40年間こんな調子だったのに、今さら変わるはずもない。残りの人生を、感謝もされずに家政婦のように過ごすのかと思うと、絶望的な気持ちになりました。
(63歳・女性)
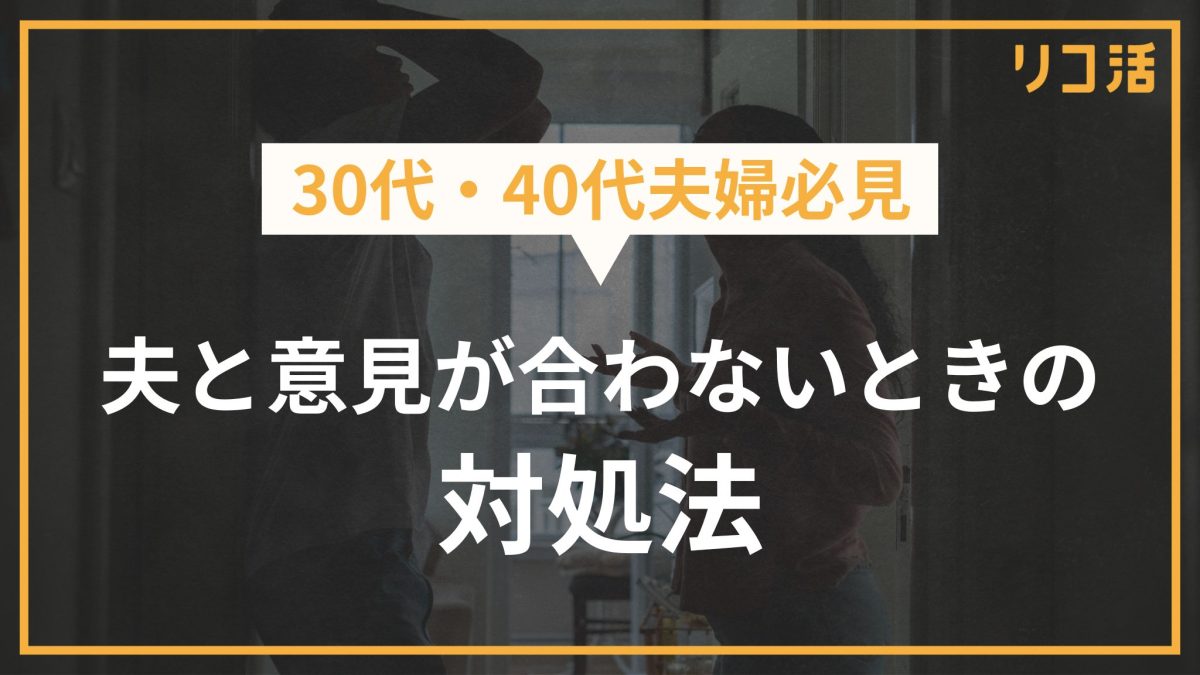
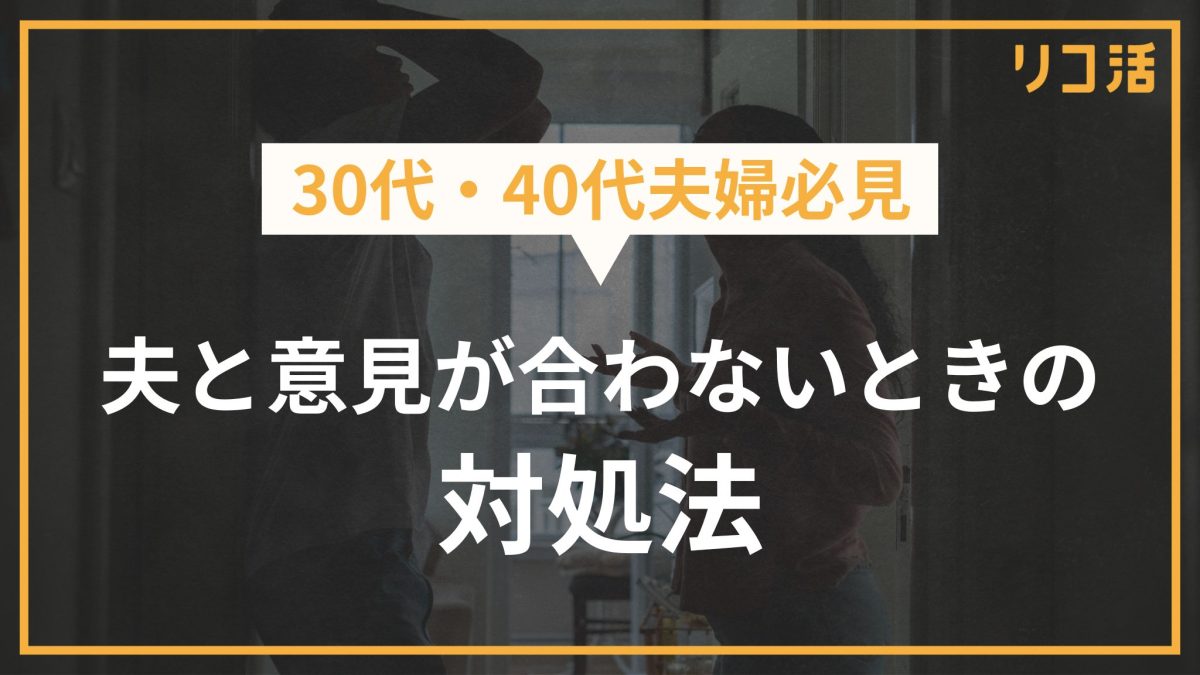
定年退職や子どもの独立
夫の定年退職によって、夫婦が一緒に過ごす時間が増えると、お互いの生活リズムや嗜好の違いが浮き彫りになります。「毎日夫が家にいるのがストレス」「夫の時間の使い方が理解できない」といった不満の声も少なくありません。また、子どもの独立も大きな転機です。育児中心の生活から解放されることで、妻は自分の人生を見直すようになります。



子どもが巣立って「ようやく自分の時間が持てる」と思ったら、夫が定年退職。私は仕事がありますが、夫は家にいてろくに家事もしません。朝晩「飯は?」と聞かれる生活に、心がすり減っていきました。この人と残りの人生を過ごしたくない、そう思うようになって、弁護士さんに相談中です。
(52歳・女性)
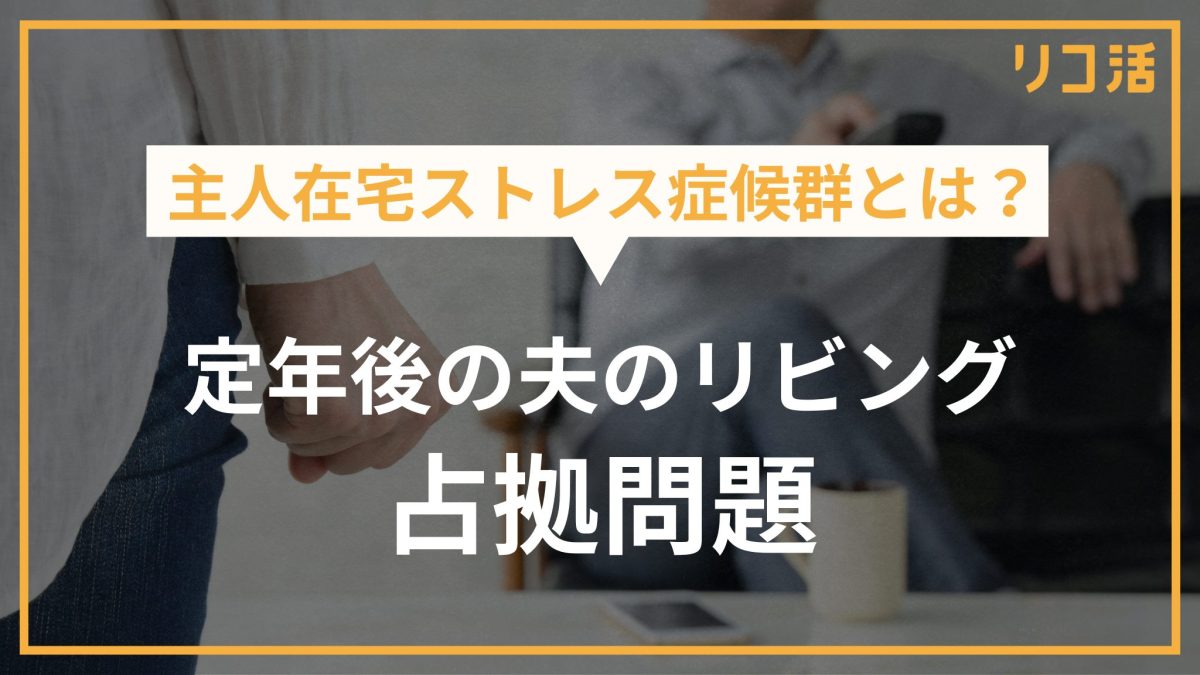
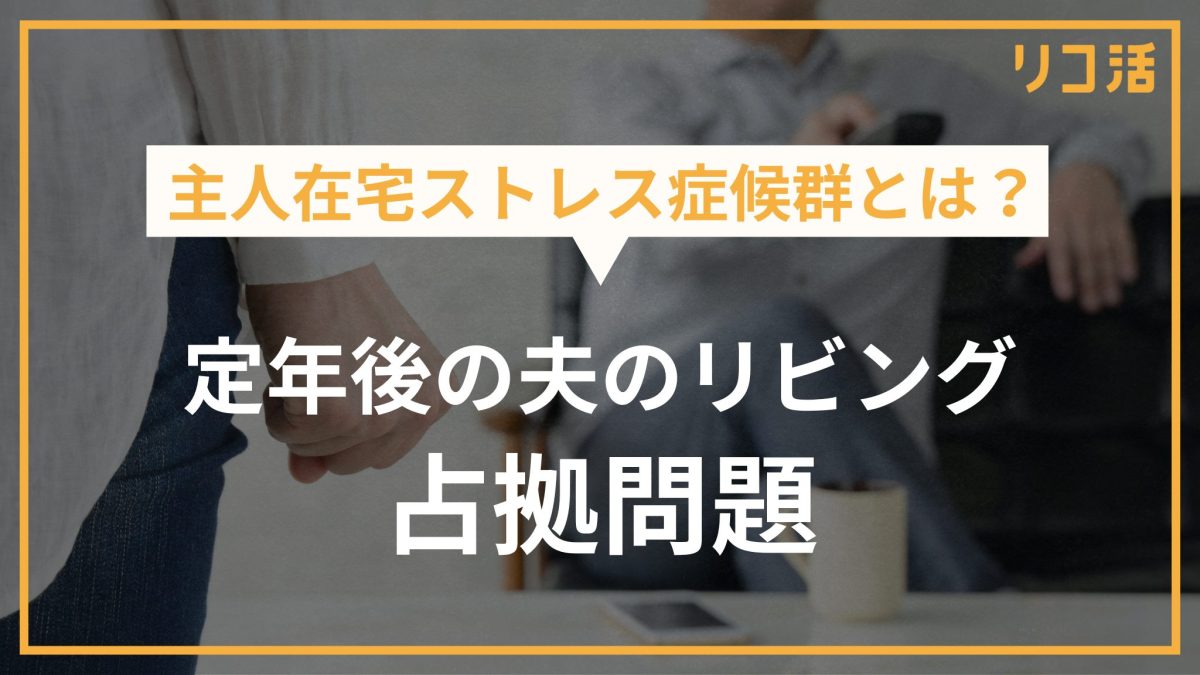
浮気やセックスレスなど夫婦間トラブル
夫の浮気などの不貞行為は、法的にも慰謝料請求の根拠となる大きな問題です。特に、長年信頼してきた相手に裏切られたときの精神的ショックは大きく、離婚を決断する妻も少なくありません。また、セックスレスによる身体的・精神的な距離も、夫婦関係の冷え込みを深刻化させる原因となります。



スマホを肌身離さず持つようになった夫の不審な行動に違和感を抱き、探偵をつけたところ浮気が発覚。私と体の関係は10年以上なく、心もすでに離れていました。何のために一緒にいるのか、自分の人生を取り戻すしかないと決意しました。
(45歳・女性)
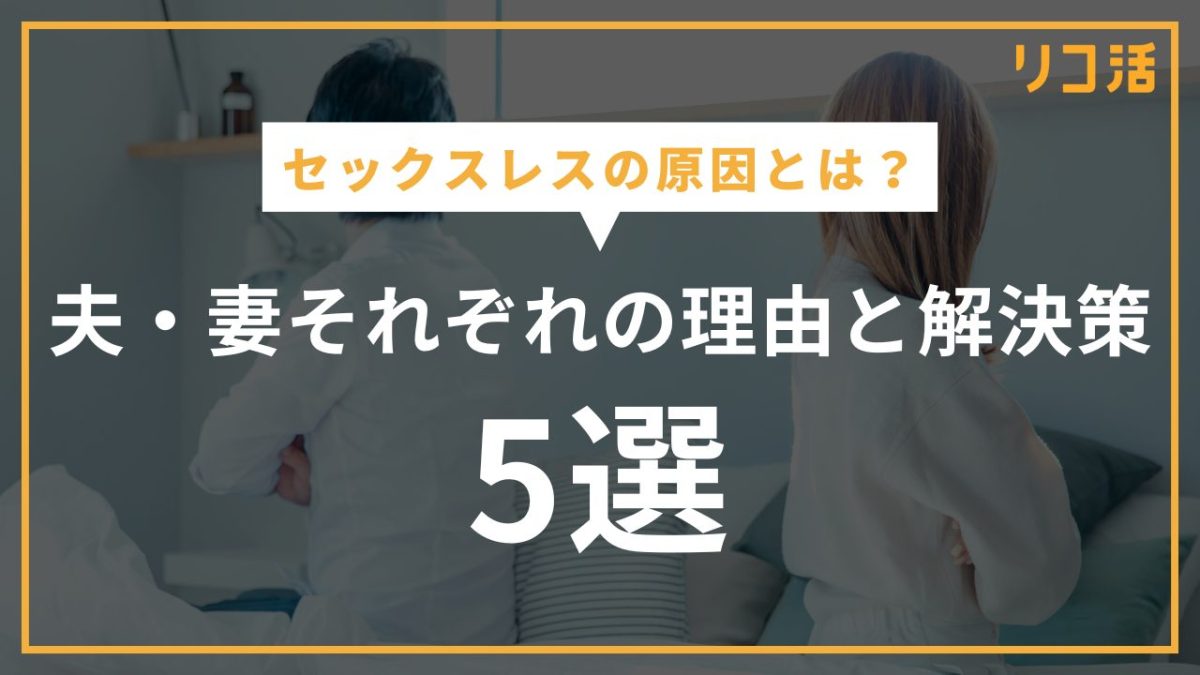
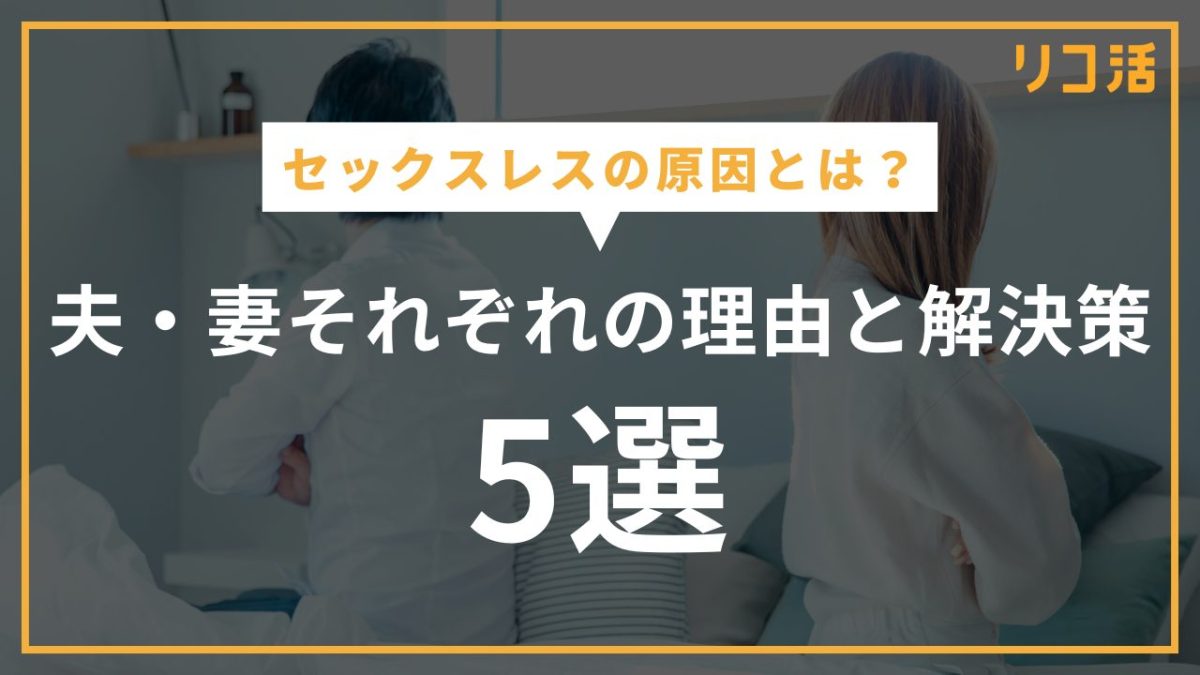
介護負担と老後への不安
平均寿命が延び、親や配偶者の介護が必要になる家庭も増えています。夫やその親の介護を担うのは、多くの場合妻です。その負担は体力的にも精神的にも大きく、将来への不安から熟年離婚を選ぶ妻も少なくありません。また、老後の資金問題も深刻です。夫が資金計画を立てていない場合、経済的な不安が妻の決断を後押しすることもあります。



義母が要介護状態になったとき、夫は「よろしく頼む」と言いました。パート勤務だからといって介護も家事も全部私任せ。あまりにも無責任な夫に絶望しました。「老後は一人で自由に生きたい」と、子どもたちに離婚を考えていることを伝えました。
体験談(55歳・女性)
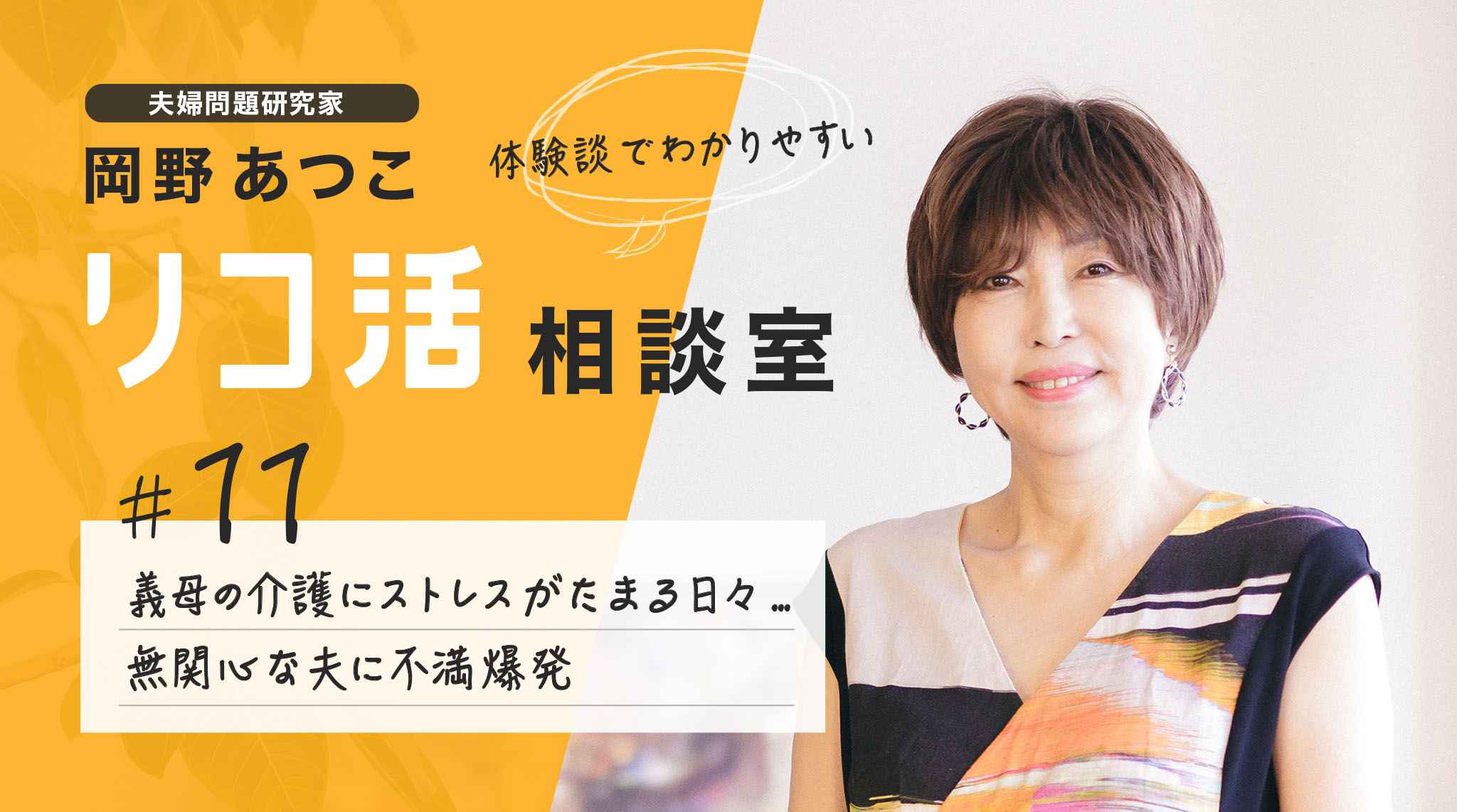
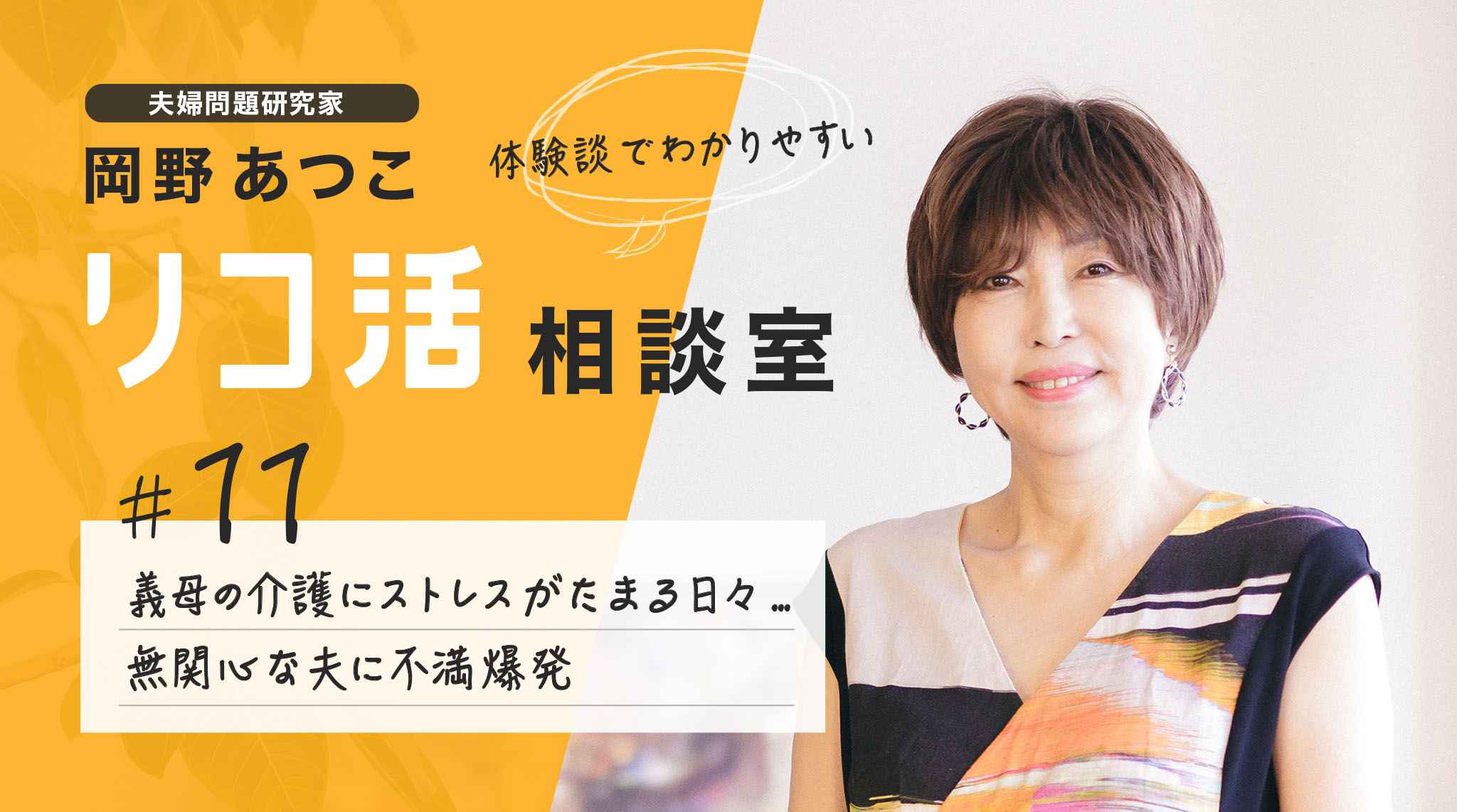
離婚前に考慮すべき準備と対策
離婚の話し合いに入る前に、押さえておきたい事前準備と対策についてお伝えします。


夫婦カウンセリングを検討する
離婚を迷っている段階では、弁護士よりも夫婦カウンセラーへの相談がおすすめです。夫婦問題の専門家であるカウンセラーが客観的な立場から、根本的な問題を探り、離婚すべきかどうかアドバイスを提供します。
特に熟年離婚の場合は、離婚後妻の収入だけで生活を送ることができるのか、具体的に検討する必要があるでしょう。夫婦カウンセリングを受けることで、離婚するにしても修復するにしても、どのように話し合いを進めればいいかなど、具体的な解決策が見つかることもあります。
また、もし離婚を選択することになっても、心の問題と法的な問題を整理して進めることができるため、余計な心労を軽減できるでしょう。
共有財産の一覧化
離婚を検討している場合、離婚協議を有利に進めるには、まずは夫婦が築いた共有財産を正確に把握する必要があります。銀行口座の残高や不動産の名義、年金加入記録など、リスト化しておくと交渉がスムーズになるでしょう。
特に婚姻期間中に得た資産は、原則として夫婦双方に分与する権利があります。自分だけでなく夫名義のものも含め、可能な限り情報を集め「どの財産が共有か」を明確にしておきましょう。
別居期間や生活費負担への注意点
離婚協議を進める中で、別居という形を先にとる場合もあります。その際に生活費や住宅の契約名義など、誰がどのように負担するのかを明確にすることが大切です。放置すると夫婦間の信頼関係がさらに悪化し、交渉がこじれる原因になります。
別居期間中は婚姻費用として夫が妻に一定額を支払う義務を負うケースがあります。家庭裁判所の調停などで具体的な金額や支払い方法を定め、後々のトラブルを防ぐのがおすすめです。
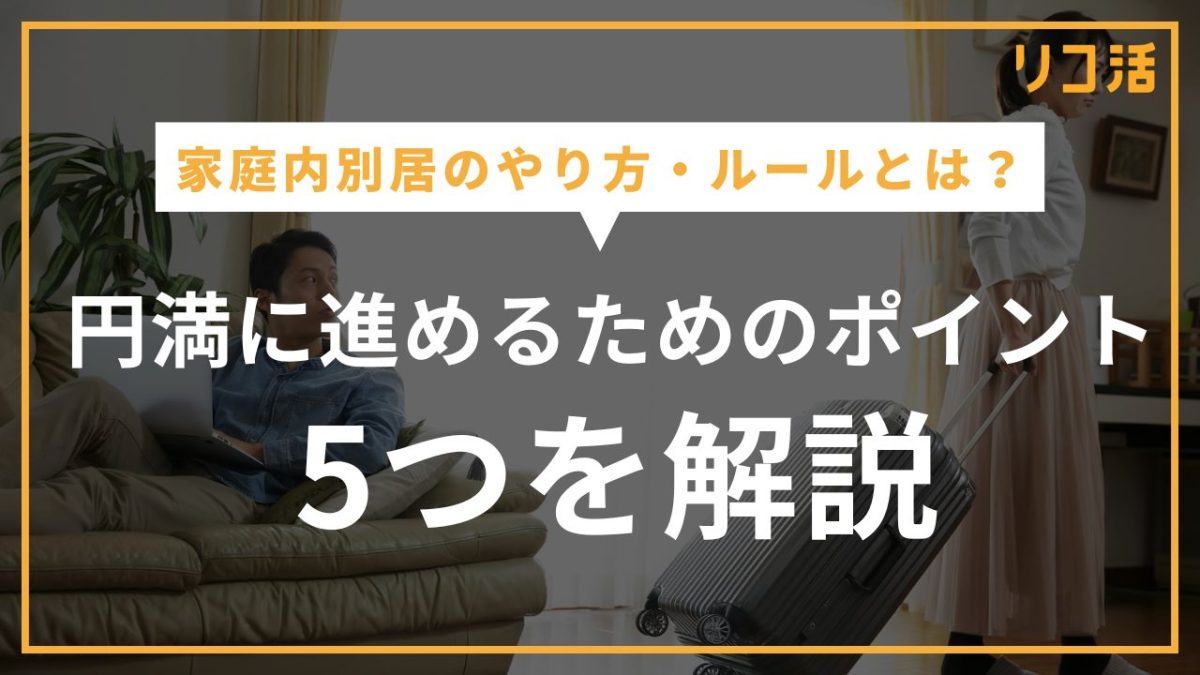
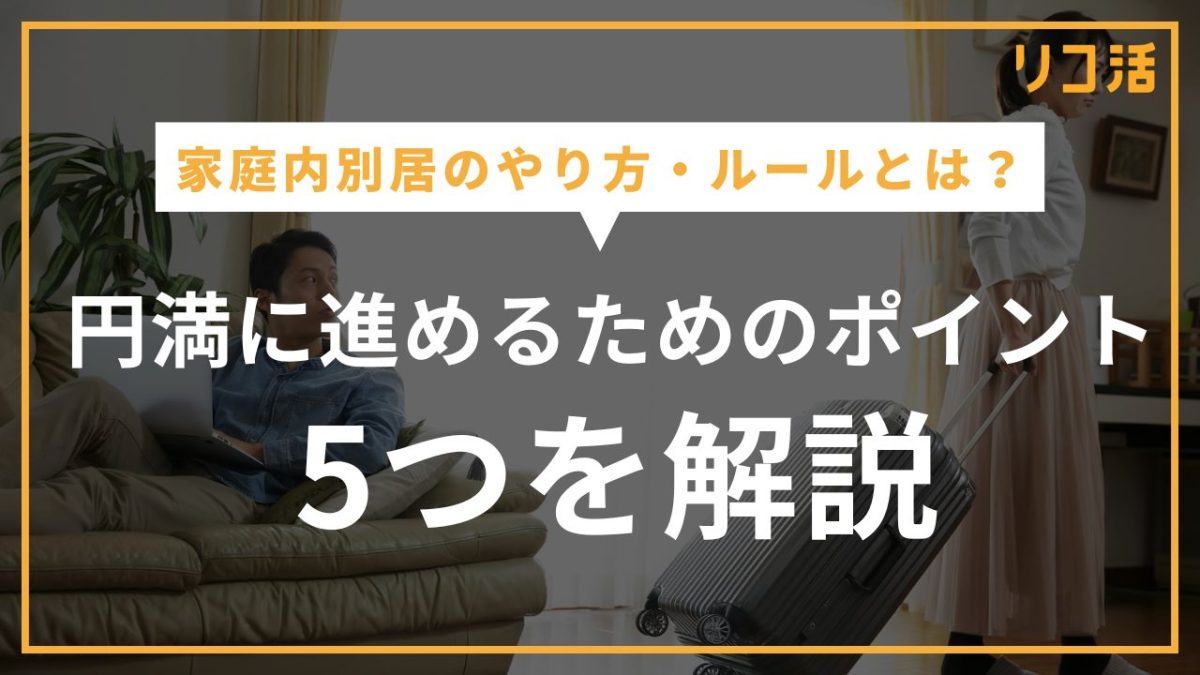
財産分与で損をしないための知識
財産分与は、夫婦が協力して築いた財産を離婚の際に分割する手続きです。熟年離婚の場合、結婚生活が長期間に及ぶため、家や貯蓄、株式や退職金など多岐にわたる財産が対象となります。
適正な財産分与を受けるには、まず「共有財産」と「個人の特有財産」を正しく区別することが重要です。また、妻が専業主婦またはパート勤務であっても、その内助の功は財産形成に大きく貢献していると認められるのが一般的です。
正しい知識を持って交渉すれば、離婚後の生活費や将来の資金を確保しやすくなるでしょう。



我が国では、かつて男性が家の外で働き、女性が家庭を守るという価値観が当たり前でした。そのため、夫が築いてきた財産について、離婚時には原則、財産分与の対象になるということは、違和感があるかもしれません。
しかし、夫が財産を築いてこれたのも妻による協力があってこそといえる場合には、離婚時に妻にも分与する必要があります。
共有財産と特有財産の違い
共有財産とは
婚姻期間中に夫婦が共同で得た財産を指します。以下のようなものが該当します。
- 不動産:夫婦で住むために購入した自宅など
- 預貯金:夫婦どちらかが働いて得た給料からの貯蓄
- 株式・投資信託:婚姻期間中に購入したもの
- 保険の解約返戻金:婚姻期間中に積み立てた部分
- 退職金:婚姻期間に対応する部分
特有財産とは
財産分与の対象にならない個人の財産です。
- 結婚前から所有していた財産
- 相続や贈与で得た財産
- 個人的な趣味のコレクション(価値が高い場合は要注意)
注意すべきポイント
熟年離婚では、特有財産と共有財産の区別が複雑になりがちです。特に長期間にわたりローン返済を続けてきたケースなどは、どの部分が共有財産に当たるのかを慎重に確認することが大切です。
専業主婦の貢献度はどう評価される?
専業主婦として家事や育児を一手に引き受けてきた妻の役割は、夫の労働を支え、家庭を維持するうえで重要な貢献と見なされます。そのため、外で得た収入ばかりを重視するのではなく、専業主婦としての貢献度も財産分与に考慮されるのが一般的です。
正当な評価を得るために準備しておくこと
適切な評価を受けるためには、これまでの生活の実態を具体的に示す必要があります。
有効な証拠となるもの
- 家計簿:家計管理の実態
- 日記:家事や育児の記録
- レシートや領収書:生活費の支出記録
- 子どもの成長記録:育児への関与度
- 介護記録:両親の介護を担当していた場合
これらの書類は、専業主婦としての貢献を客観的に示す重要な証拠として活用できます。
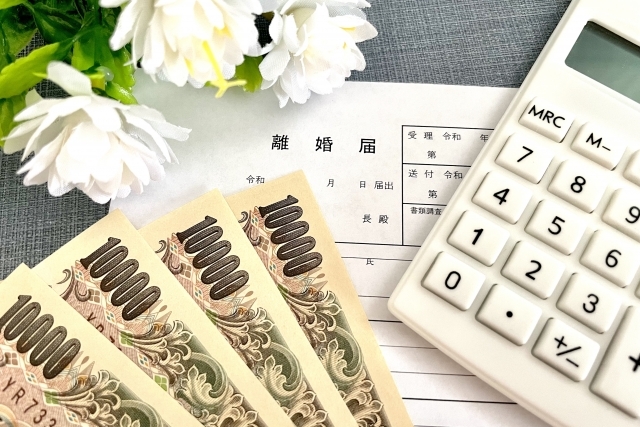
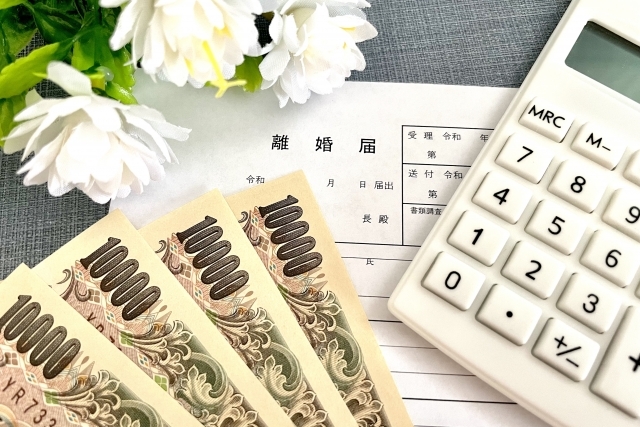
年金分割と老後資金の考え方
熟年離婚では、離婚後の長期的な生活設計が何より重要です。特に年金分割制度を活用することで、専業主婦であっても老後の安定した収入源を確保できる可能性があります。
早めに制度を理解し、適切な手続きを行うことで、離婚後も安心して暮らせる基盤を築きましょう。


年金分割の仕組みと手続き
年金分割制度とは
年金分割は、婚姻期間中の厚生年金保険料の納付実績を夫婦で分け合う制度です。専業主婦であっても、夫婦で協力して築いてきた年金記録の一部を受け取る権利があります。
手続きの流れ
- 離婚成立後に年金事務所で申請
- 必要書類の準備
- 年金手帳
- 離婚届受理証明書
- 戸籍謄本
- 年金分割のための情報通知書
- 分割割合の決定(最大50%まで)
- 年金記録の分割実行
注意すべきポイント
- 手続きには期限があります(離婚成立から2年以内)
- 分割割合の合意や手続きのタイミングによって、受給開始時期や金額に影響が出る場合があります
- 制度の詳細は複雑なため、年金事務所や専門家への相談をおすすめします
離婚後を見据えた生活設計のポイント
離婚後の住居をどうするかは、老後の安心にも直結します。新たな物件を借りるのか、実家がある場合は実家へ戻るのか、兄妹や子どもに頼るのか、収入状況を踏まえて計画的に検討しましょう。また、思わぬ医療費や介護費用がかさむ可能性も考慮すべき点です。
健康保険や年金に加えて、積立貯蓄や投資などで十分な生活費を確保する工夫も欠かせません。万が一に備える保険や、公的制度の利用も含めて総合的に考え、衝動的に離婚を選択するのではなく、離婚後も安定した生活を送れるような基盤があるのか確認しておくと安心です。
熟年離婚で慰謝料は請求できる?条件と相場とは
熟年離婚において慰謝料を請求できるかどうかは、相手に法的な離婚事由があるかがポイントになります。
ただし、慰謝料は「思ったより少額だった」というケースも多いため、現実的な期待値を持って準備することが大切です。


慰謝料が認められやすい条件
慰謝料を請求するには、明確な法的離婚事由が必要です。以下が離婚事由として認められやすい例です。
- 不貞行為(浮気・不倫)
- 暴力(DV)
- 精神的暴力(モラルハラスメント)
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、家出など)
- その他の重大な事由
一方で、性格の不一致、価値観のすれ違い、愛情の冷却、親族との不仲といった理由では、慰謝料請求は困難とされています。これらは夫婦双方に責任があると見なされがちで、一方的な精神的苦痛とは認められにくいからです。
慰謝料の相場
熟年離婚における慰謝料の相場は数十万円から数百万円程度ですが、ケースによって大きく異なります。金額を左右する要因として、離婚事由の重大性(不貞の期間や暴力の程度)、婚姻期間の長さ、精神的苦痛の程度(うつ病など具体的な被害)、相手の資産状況や社会的地位などが挙げられます。
ただし、慰謝料は離婚後の生活費の全てを賄うものではないことを理解しておくことが重要です。あくまで精神的苦痛に対する賠償であり、生活保障とは性質が異なります。
慰謝料請求に必要な証拠と立証の手順
慰謝料を請求するにあたり、浮気の場合は写真やメール、SNSでのやりとりなどの証拠が求められます。暴力やハラスメントの場合は診断書や録音データが有力な証拠になります。いずれにしても、感情に流されず冷静に記録をとることが重要です。
慰謝料請求を検討する場合は、弁護士や法テラス、必要に応じて探偵などの専門家への早期相談が重要です。証拠の整理と時系列の作成、相手方への慰謝料請求、話し合いでの解決または調停・訴訟という流れで進めていきます。
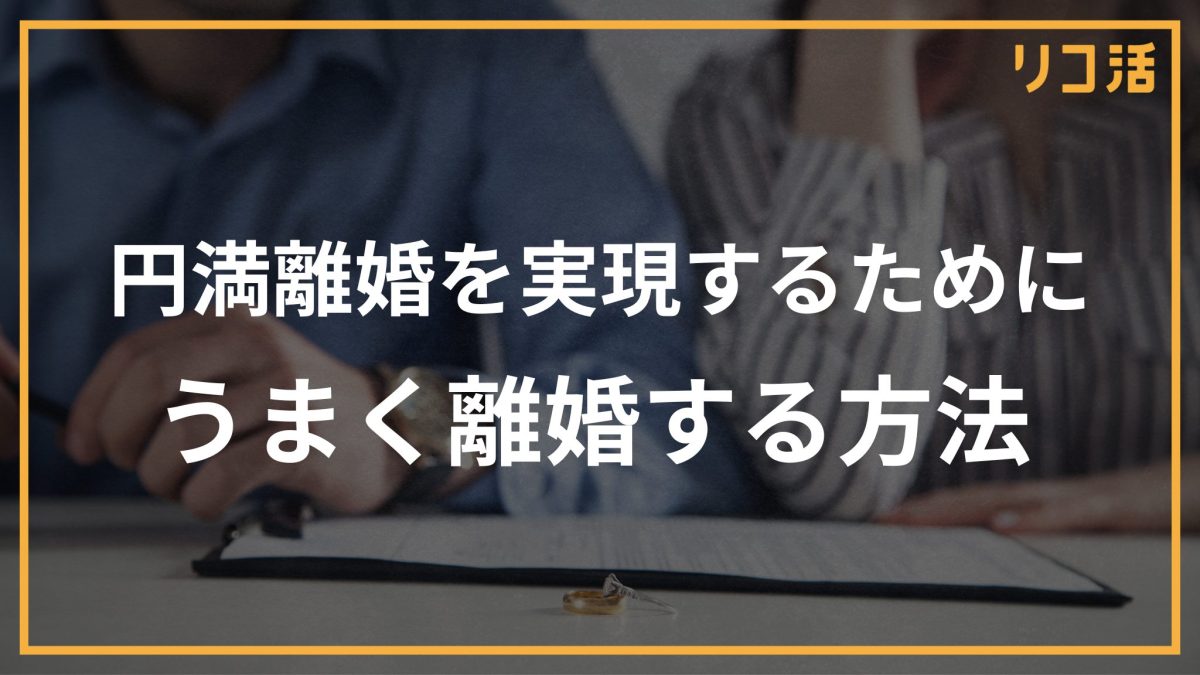
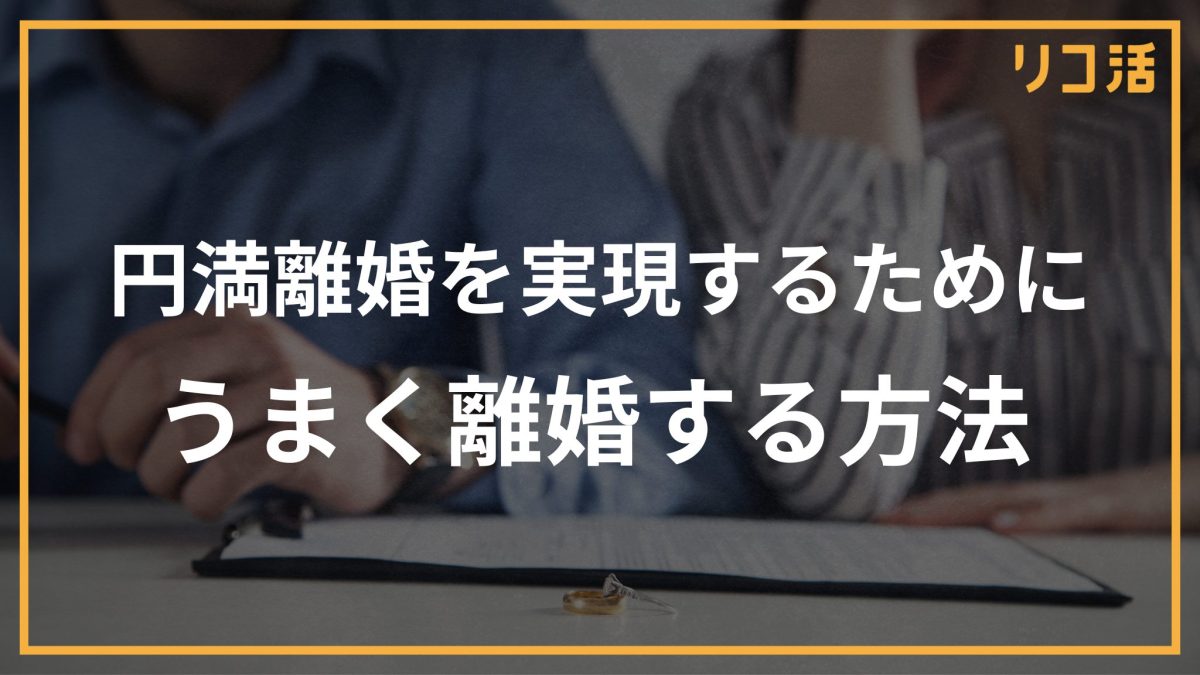
子どもへの影響を最小化するには
離婚において大切なのは、家族全体の今後の関係をなるべく円満に保つことではないでしょうか。特に親権や養育費など、未成年の子どもの問題は慎重に話し合う必要があります。一方で、成人した子どもがいる場合でも、それぞれの感情や生活に大きな変化をもたらす可能性は否めません。


未成年の子どもがいる場合の取決め
熟年離婚であっても、子どもが未成年の場合は親権者の決定、養育費、面会交流について明確に取り決める必要があります。これらの合意事項は必ず公正証書などの公的文書にしておきましょう。
子どもの心のケアも重要な課題です。未成年とはいえ既に自我が確立している年齢の子どもは、両親の離婚を複雑な感情で受け止めがちです。可能な範囲で子どもの気持ちを聞き取り、新しい生活への適応をサポートすることが親としての責任といえるでしょう。


成人した子へ配慮するポイント
子どもが成人している場合でも、両親の離婚が心情に影響することは少なくありません。結婚に対するイメージや、実家との関わり方が変化するなど、新たな問題が生じることもあります。
子どもが独り立ちしているからこそ、両親と距離を置きがちになる一方で、実は内心では動揺しているケースもあります。離婚を進める際には、子どもが遠慮なく意見や不安を話せるような機会を設けることが望ましいでしょう。
妻が熟年離婚を考えるときによくある質問(Q&A)
Q1. 熟年離婚を考える妻はどのタイミングで弁護士に相談すべきですか?
A. 離婚を本格的に検討し始めた段階で早めの相談をおすすめします。夫が離婚に応じない、財産隠しの疑い、不貞やDVがある、年金分割の手続きが不安な場合は迷わず相談しましょう。初回相談30分程度で今後の方針を明確にできるでしょう。
Q2. 熟年離婚における妻の平均的な離婚後の生活費はどの程度必要ですか?
A. 一人暮らしで月15〜20万円程度が目安です。住居費5〜8万円、食費・生活費5〜7万円、医療・保険料2〜3万円、その他3〜5万円です。年金分割により受給できる年金額も考慮し、不足分を貯蓄や就労収入で補う計画を立てることが重要です。
Q3. 熟年離婚後、妻が再婚する可能性や注意点はありますか?
A. 熟年離婚後の再婚率は低いですが、中高年の再婚は増加傾向にあります。注意点は年金分割の受給権が再婚で失われる可能性、相手の財産状況や介護リスク、遺産相続の複雑化です。再婚前に法的影響を確認しましょう。
Q4. 熟年離婚で妻が住宅ローンの残る家に住み続けることは可能ですか?
A. 可能ですが条件があります。ローンの名義変更、妻の返済能力、夫の同意が必要です。リスクとして競売の可能性、審査の難しさ、維持費負担があります。多くの場合、売却して現金分割する方が現実的です。
Q5. 熟年離婚を決断した妻が家族や親戚にどう説明すればよいですか?
A. 段階的に説明しましょう。まず成人した子どもに理由を率直に話し理解を求めます。親族には感情的にならず「お互いの幸せのため」と前向きに説明。近所や知人には「新しい人生を歩みます」程度で十分です。離婚が決定事項であることを明確に伝えることが重要です。
熟年離婚を決断する妻が知っておくべきこと
熟年離婚を検討する妻にとって、この決断は人生の重要な転機となります。長年の結婚生活を終える選択には、法律面・経済面・心理面での十分な準備が欠かせません。
まずはなぜ離婚を考えているのかを冷静に整理し、財産分与や年金分割などの制度を正しく理解することが大切です。特に専業主婦として家庭を支えてきた妻の場合、離婚後の生活設計をしっかりと立てる必要があります。
熟年離婚では妻が主体的に行動することが成功の鍵となります。夫との話し合いを進めながら、必要に応じて弁護士などの専門家に相談し、自分の権利を適切に守りましょう。