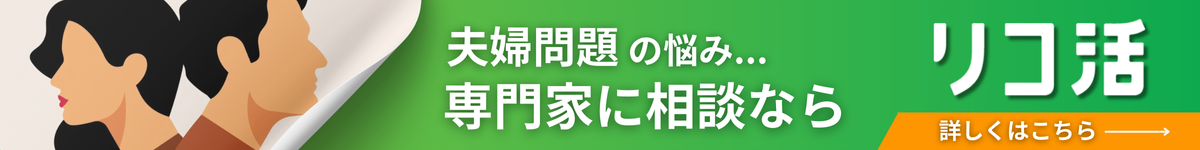2024年に成立した改正民法により、これまで離婚後は単独親権のみが認められていましたが、2026年5月までに施行される新制度では、共同親権を選択することも可能になります。この法改正では、子どもの最善の利益を確保するため、親権制度の見直しだけでなく、養育費の支払確保に向けた法定養育費制度の創設や先取特権の付与など、実効性のある対策も導入されます。本記事では、共同親権の基本的な仕組みや運用方法、法定養育費の特徴、養育費の支払いを確保するための先取特権制度、そして既に離婚している場合の対応について、法務省の資料に基づいて解説します。
※この記事は2025年5月20日時点の情報に基づいて作成されています。法改正の内容は2026年5月までに施行される予定であり、今後、詳細な省令等が定められる可能性がありますので、最新情報は法務省ホームページ等でご確認ください。
佐々木 裕介/チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所(第二東京弁護士会所属)
ホームページ:https://law-childsupport.com/
「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。
詳しく見る
協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。
子連れ離婚をしたシングルマザーのうち、養育費を1回でももらったことがある人は全体の4割ほど。さらにそのうち、6~7割の人が支払い停止や一方的な減額をされています。このような状況の中、離婚後の生活に不安を感じている方も多いと思います。 不安を解消できるよう、丁寧に、安価に、ちゃんとした離婚をするお手伝いをするとともに、離婚後も長期スパンで養育費がきちんともらえる体制作りをサポートします。 離婚後も、安心して暮らしていくお手伝いをしたいと思っています。一緒に幸せをつかみに行きましょう。
【裁判所を使わず協議離婚対応】【養育費保証ご相談可】【法テラス利用可】

共同親権とは?単独親権との違い
まずは、親権の基本的な仕組みを理解し、共同親権と単独親権の違いを押さえておきましょう。
親権には「財産管理権」と「身上監護権」の大きく二つの権限が含まれます。財産管理権は子どもが所有する財産や貯金、保険などを管理する権能を指し、身上監護権は子どもの身の回りの世話や教育、健康管理などを行う権能を意味します。
日本ではこれまで離婚後は「単独親権」が法的に義務付けられてきましたが、2024年に成立した改正民法により、2026年4月からは共同親権制度が選択可能となる見通しです。共同親権では離婚後も両親が親権を共有し、子どもの教育や成長に双方が継続的に関わります。
両親が子どもへの責任を継続して負うことで、面会交流や教育方針の決定がスムーズになると期待されます。
単独親権の場合、親権を持たない側の親は子どもの重大な事柄にかかわりにくくなる一方で、意思決定がシンプルであるというメリットがあります。これに対して共同親権では、両親が協力して子どもを支えるため、子どもの養育環境が複数の視点からカバーされやすいと言えます。ただし、親同士の対立が激しい場合は、その調整が難航しトラブルに発展するリスクも高まるでしょう。
どちらの制度も子どもの福祉を考慮したものであることは共通していますが、家庭環境や父母の関係性により最適解は変わってくるでしょう。子どもの最善の利益を常に念頭に置いたうえで、より良い選択をすることが大切です。
ただし、共同親権を全面的に導入するにあたっては、DVや虐待のリスクが懸念される場合への対応が課題となります。法改正では、こうしたハイリスクなケースでは共同親権を適用しない方針が示されており、安全保障のための特別な措置も検討中です。

共同親権における養育費の考え方

共同親権下でも養育費の支払い義務は続きます。どのように支払いや金額を決めるか、その考え方を見ていきましょう。
共同親権であっても、子どもの養育費に関する父母の負担義務は基本的に変わりません。むしろ、離婚後も両親が共通の責任を持つため、子どもに必要な費用をどのように分担するかはより明確にする必要があるでしょう。
子どもの成長に伴い、教育費や生活費は変動していくため、一度決めた金額でも状況に応じた見直しが必要になるケースがあります。家庭裁判所に調停を申し立てることで調整が可能ですが、日頃から父母同士のコミュニケーションを深めておくことで、簡潔に合意形成ができることも多いです。あくまで子どもの最善の利益を基準に、費用負担のあり方を考える姿勢が大切になってきます。
新たに導入される「法定養育費」制度とは?
2024年に成立した改正民法では、離婚後の子どもの養育に関する重要な変更として「法定養育費」制度の導入が見込まれています。この制度により、離婚時に養育費の取り決めがされていない場合でも、子どもの監護を主として行う親は、相手に対して一定額の養育費を請求できるようになります。
法務省から公表されている資料を元に、2024年に成立した民法等改正法における養育費に関する新制度について説明します。
法定養育費の特徴
基本的な仕組み
- 離婚時に養育費の取り決めをしていなくても自動的に発生する制度
- 子どもと同居する親が別居親に請求できる法的権利
適用期間
- 開始: 離婚の日から自動的に発生
- 終了: 次のいずれか早い日まで
- 父母が正式に養育費の取り決めをした時
- 家庭裁判所の養育費審判が確定した時
- 子どもが18歳になった時
毎月末に、その月分の法定養育費を支払う必要があり、金額は今後、法務省令で定められる予定です。
支払い免除の条件
以下の場合は、法定養育費の全部または一部の支払いを拒むことができます。
- 支払い能力がない場合(収入が極めて少ない等)
- 支払いにより自分の生活が著しく困窮する場合(生活保護受給中など)
改正法の適用対象
- 改正法施行後(2026年5月までに施行予定)に離婚したケースのみに適用
- 施行前に離婚した場合は対象外
この制度は、養育費の取り決めをするまでの「暫定的・補充的」なものであり、最終的には父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、収入などを踏まえた適正な額の取り決めをすることが推奨されています。
養育費を優先して回収する「先取特権」の強化
さらに、既定の支払いが滞った場合に備えて、先取特権という形で養育費が優先的に回収される仕組みも強化される方向です。これは未払い状態が続いたときに、子どもの生活が大きく損なわれるのを防ぐ目的があります。改正内容が確定すれば、親としての責任を果たさない相手に対して迅速な法的対応が可能になると考えられています。
ただし、先取特権の行使には一定の手続きが必要となる見込みです。財産の差し押さえなどを検討する場合には、公正証書や調停調書やその他の合意書などを通じて養育費の債権を明示しておくことが重要になります。各家庭の事情によっては例外や考慮すべきこともあるため、弁護士などのサポートを受けつつ具体的な対応策を検討するのが望ましいでしょう。
先取特権の特徴
現行制度下では、離婚時に債務名義(公正証書や調停調書)を作成しないケースも多く、そのような場合に支払義務者に対する強制執行手続をすることはできませんでした。改正が進めば、このような問題を大幅に軽減できると見られています。未払いが続くことで子どもの生活が圧迫される事態を早期に防ぐことが、改正の大きな狙いの一つです。
改正法では、養育費債権に「先取特権」という優先権が付与されます。特徴は以下の通りです。
- 養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づき、債務名義(公正証書や調停調書など)がなくても差し押さえ手続きが可能になる
- 改正法施行前に取り決めされた養育費については、施行後に発生する分からこの制度が適用される
※先取特権が付与される養育費の額は法務省令で今後定められる予定
裁判手続きの簡素化・効率化
現行制度下では、相手の勤務先や口座情報などを得るのに時間と手間がかかり、執行手続きが長引くことも少なくありませんでした。改正が進めば、このような問題を大幅に軽減できると見られています。未払いが続くことで子どもの生活が圧迫される事態を早期に防ぐことが、改正の大きな狙いの一つです。
養育費の回収をスムーズにするため、裁判所の手続きも以下のように改善される見込みです。
- 家庭裁判所が当事者に収入情報の開示を命じることが可能になる
- 地方裁判所への1回の申立てで以下の一連の手続きを申請可能になる
- 財産開示手続(養育費支払義務者の財産開示)
- 情報提供命令(市区町村に対する給与情報提供命令)
- 債権差押命令(判明した給与債権の差し押さえ)
これらの変更により、離婚後も子どもが必要な経済的支援を受けられる可能性が高まり、未払い養育費の問題に効果的に対処できると期待されるほか、当事者のみならず、司法機関の負担を減らす効果も期待されています。
ただし、改正民法は2026年5月までに施行される予定で、法定養育費の規定は改正法施行後に離婚したケースにのみ適用される予定です。既に離婚している場合は、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより養育費の取り決めを行う必要があるため注意が必要です。
出典:法務省民事局「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(2024 年 12 月発行)https://www.moj.go.jp/content/001428136.pdf
養育費と面会交流の関係、共同親権で変わることは?

子どもの成長に不可欠な面会交流と養育費の結び付き、共同親権の導入で想定される変化を改めて押さえておきましょう。
離婚後の面会交流は、子どもにとって親との結び付きや安心感を保つ重要な時間になります。共同親権が導入されることで、父母のどちらも法的に子どもに関与する権利と義務を持つため、面会交流の機会が増えることが期待されています。子どもに直接会って生活状況を知ることが、養育費の支払い意識を高める効果もあるという指摘もあるようです。
ただし、養育費と面会交流は本来別の問題であり、双方を結びつけることは望ましくありません。面会交流が行われないからといって養育費を支払わない、あるいは養育費を支払わないから面会交流を拒否するといった行為は、子どもの利益を損ねることにつながります。
共同親権の導入により、お互いの責任が明確化されることで、こうしたトラブルの解消につながる可能性があります。
大切なのは、面会交流や養育費の取り決めが子どもの成長と幸福にどのような影響を与えるかを考えることです。子ども自身の気持ちや生活サイクル、学業などを考慮し、父母が協力して最適な環境を作らなければなりません。共同親権の制度導入は、その協力関係を法律面から後押しする仕組みと言えるでしょう。


すでに離婚済みの場合はどうなる?

改正民法が施行された後でも、すでに離婚して単独親権となっている場合は、自動的に共同親権に変わることはありません。しかし、一定の条件のもとで共同親権への変更が検討できる可能性があります。
法務省の資料によれば、すでに離婚している場合の親権変更は、「家庭裁判所が、こども自身やその親族の申立てに基づいて、こどもの利益のための必要性を踏まえて」判断されます。つまり、当事者である父母の合意だけでは変更できず、家庭裁判所の審判を通じた手続きが必要となるのです。
特に重要なのは、子どもの利益を最優先に考慮するという点でしょう。家庭裁判所は、父母と子どもとの関係や、父母間の関係など様々な事情を考慮した上で判断を下します。例えば、長期間にわたって養育費の支払いを怠っていた場合は、共同親権への変更が認められにくい可能性があります。
また、法務省の資料では、「虐待やDVのおそれがあるときや、父母が共同して親権を行うことが困難であるとき」には、共同親権への変更は認められないと明記されています。これは子どもの安全と健全な成長環境を守るための重要な制限です。
共同親権への変更を検討する場合は、子どもの安定した生活環境や心理的な影響を十分に考慮し、子どもの意向も尊重することが大切です。何よりも、親権形態の変更が子どもにとって本当に有益なのかどうかという観点から慎重に判断する必要があります。
出典:法務省民事局「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(2024 年 12 月発行)https://www.moj.go.jp/content/001428136.pdf
養育費の未払いを防ぐための対策と法的措置
養育費の未払い問題は深刻化するケースが多々あります。事前に合意書を作成する方法や、強制執行などの法的措置について確認しましょう。
まず予防策として最も効果的なのは、離婚時に公正証書や調停調書という法的効力のある文書で養育費の取り決めを明確にしておくことです。特に、公正証書に「強制執行認諾文言」を付けることで、支払いが滞った場合に裁判所を通じた差押え手続きがスムーズに行えます。
2024年の改正民法ではさらに、離婚後、法律上当然に「法定養育費」が発生し、かつ、養育費債権に「先取特権」が付与されることで、従来よりも簡易な手続きで差押えができるようになります。
 チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所 佐々木 裕介
チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所 佐々木 裕介子どもの別居親(多くが父親)にとっては、事前に反論の機会もないまま裁判所で債権差押命令等が発令され自身の勤務先に突然差押通知が届く可能性もありますので、離婚時に正しく合意文書を作らないリスクが高まります。他方、子どもの同居親(多くが母親)にとっては、離婚時に合意文書を作成せずに債権差押命令の申立てすることが選択肢として提示されるものの、その金額は法務省で定められる金額に限定されることから、依然として、離婚時に合意文書を作成する必要性は高いと言えます。
また、支払いを確実にするための実践的な工夫として、口座振替や自動送金の仕組みづくりや、定期的な収入状況・子どもの成長に応じた見直しの機会を設けることも有効です。特に、失業や病気など予期せぬ事態が発生した場合には、早い段階で話し合いや再調停を行い、現実的な支払い計画を再設定することが大切です。
万が一、未払いが発生した場合の対応としては、改正法による情報開示手続きの簡素化が助けになります。一度の申立てで財産開示、給与情報の提供命令、差押えまでの一連の手続きが申請できるようになるため、子どもの生活を守るための迅速な対応が可能になります。
養育費の支払いは親としての重要な責務であり、子どもの健やかな成長を支える基盤です。事前の備えと適切な法的措置を組み合わせることで、安定した養育環境を整えることができるでしょう。


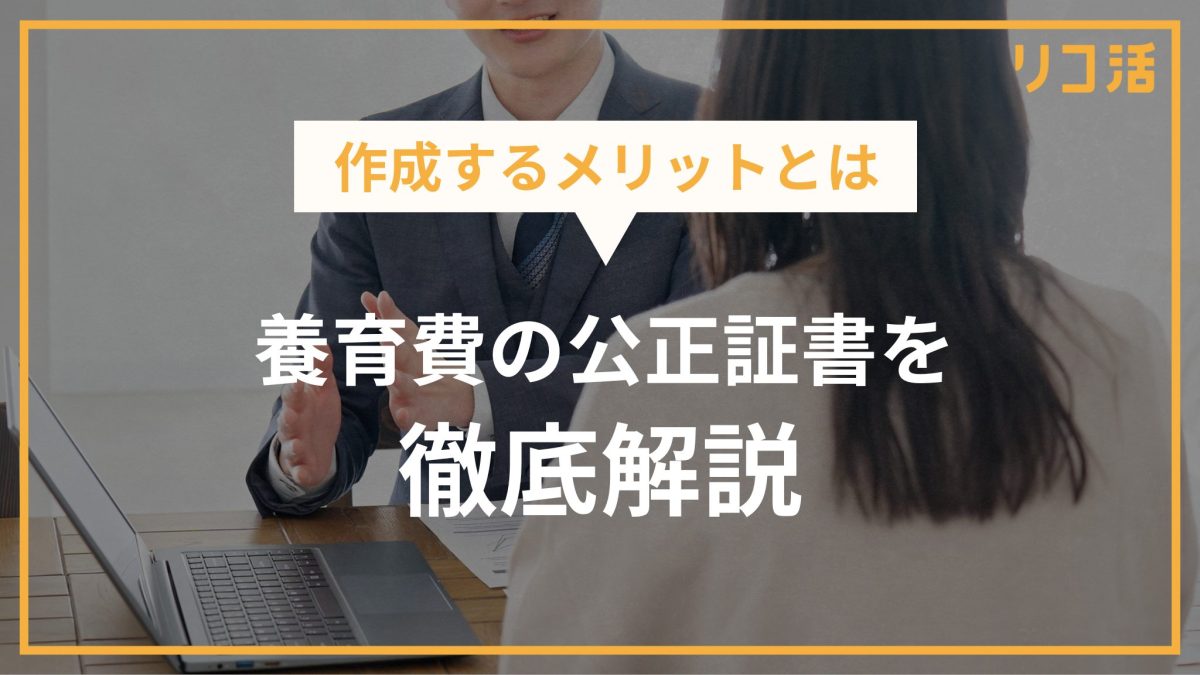
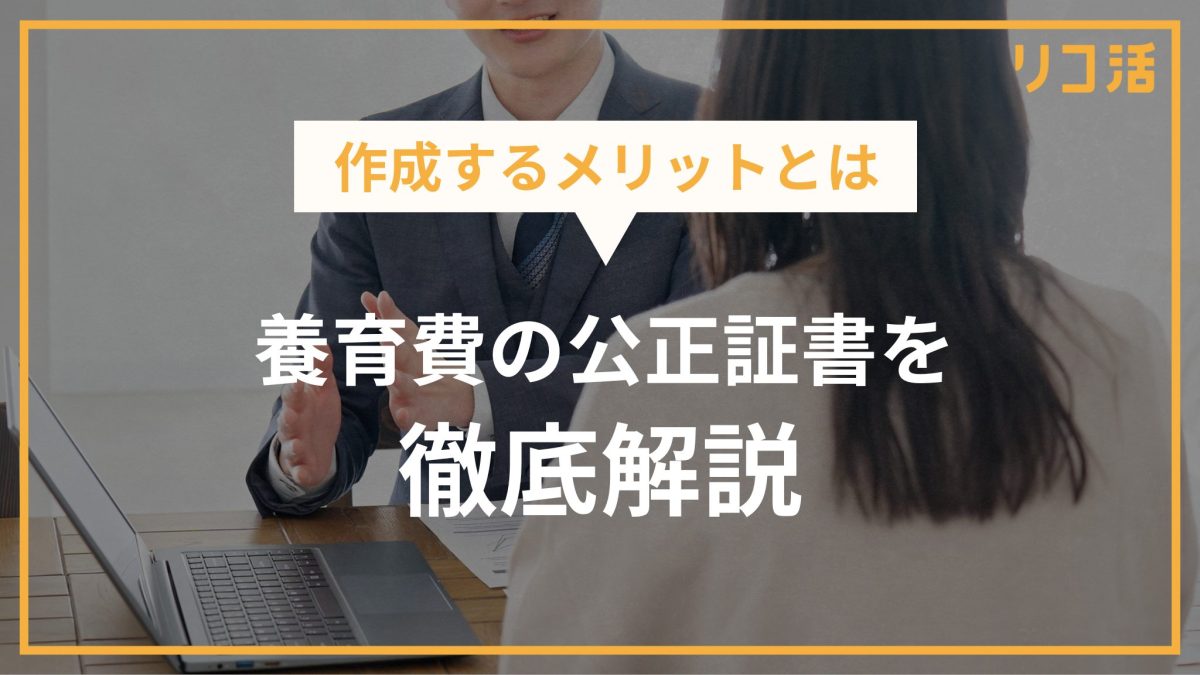
離婚後も父母が子育てを行う「共同養育」とは


親権の形態にかかわらず、離婚後も共に子どもを育てる「共同養育」という考え方があります。その概要を見てみましょう。
共同養育とは、親権の形態にかかわらず、離婚後も父母が協力して子どもを育てることを指します。たとえ単独親権であっても、面会交流や教育面での協力を保つことで、子どもに二人の親の愛情とサポートを提供できる仕組みです。欧米では共同親権と並行して、この共同養育の考え方が一般的に浸透しています。
共同養育を実践するためには、父母の間に最低限の信頼関係やコミュニケーション手段が確保されていることが前提となります。連絡ツールを整備したり、定期的に子どもの近況を共有する仕組みを作ることで、離れて暮らす親でも子どもの成長過程に深く関わることが可能です。子どものイベントや進学先の話し合いなどでも、お互いに協調しやすくなるでしょう。
実際には、対立が激しくて思うように進まないケースもあるかもしれません。しかし、子どもの視点に立てば、父母がそれぞれの役割を果たすことで得られる安心感や学習支援などの恩恵は大きいはずです。離婚後も、子どもが健やかに成長できるように父母双方が努力を続けることが、結果的には最も望ましい選択と言えるのではないでしょうか。


共同親権と共同養育の違い
共同親権は法律上の制度として、父母が子どもの親権を共有する仕組みを指します。一方、共同養育は法的な枠組みに限らず、離婚後も父母が協力して子どもを育てる実践的な概念です。両者は密接に関連していますが、厳密には重なる部分と異なる部分があります。
共同親権の場合、教育方針や医療行為などの重要事項を合意のもとで決めていくことが法律で明示されます。しかし、共同養育は法的強制力が必ずしも伴わず、父母の自主的な協力関係に依存する要素が大きいです。法改正によって共同親権が広がっても、実際の養育現場では共同養育をどれだけ実践できるかがカギとなります。
最終的には、子どもの幸福を目指すのが両制度の共通目的といえます。共同親権が機能していても、父母が対立していては子どもに悪影響が及びかねません。逆に、単独親権であっても共同養育をうまく進められるケースはありますので、家族の実情に即した柔軟な対応が求められるでしょう。


養育費が守られることにより、子どもが安心して過ごせるように
共同親権に関連する法改正により、離婚後も父母が子どもに対して法的に対等な責任を負うことで、面会交流や養育費の支払いがより確実に行われることが期待されます。しかし、DVや虐待のリスクが存在する場合には適用が制限されるなど、慎重な運用も必要であることは忘れてはならない点です。
養育費に関しては、標準額の提示や先取特権の強化などによって、子どもが安定した生活を送るための仕組みが整えられる見込みです。両親が協力しながら子どもの経済的な基盤を固める意義は、将来の進学や就職にも影響するかもしれません。
何よりも大切なのは、子どもの最善の利益を第一に考える姿勢です。法制度が整ったとしても、父母が互いの立場を尊重し、適切にコミュニケーションを図らなければ、共同親権や共同養育は十分に機能しません。これからの社会では、離婚後も相手を尊重、協力しながら柔軟な対応をし、子どもにとって最良の環境を整えることが求められるでしょう。